第三者弁済(だいさんしゃべんさい)について詳しく解説
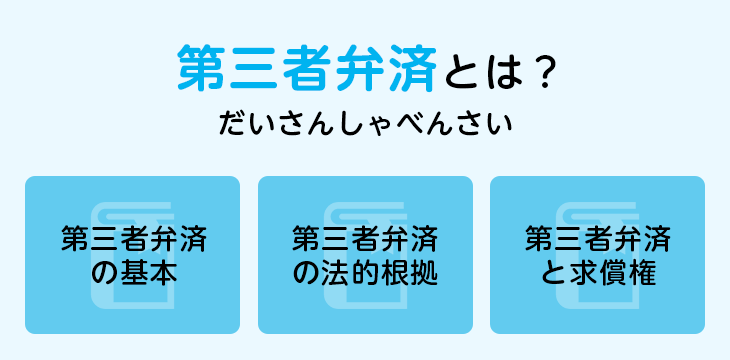
第三者弁済とは、債務者本人ではなく、第三者(家族や知人など)が債務者に代わって債務を返済することです。債務整理や過払い金請求の場面でも重要な概念となります。
第三者弁済は民法上の制度として認められており、債権者の同意がなくても原則として可能です。ただし、特定の状況下では制限が設けられることもあります。
第三者弁済の基本
第三者弁済は、債務者以外の第三者が債務者の債務を弁済することを指します。例えば、多重債務に苦しむ家族のために、親や配偶者が借金を返済するようなケースが当てはまります。
第三者弁済には主に2つの種類があります。一つは債務者の依頼や同意を得て行う「委託を受けた第三者による弁済」、もう一つは債務者の意思に関わらず第三者が独自の判断で行う「委託を受けない第三者による弁済」です。
| 第三者弁済の種類 |
|
|---|---|
| 第三者弁済の効果 |
|
上記の表は第三者弁済の基本的な種類と効果をまとめたものです。第三者弁済が行われると、債務そのものは消滅しますが、弁済した第三者に求償権が発生する場合があります。
第三者弁済の法的根拠
第三者弁済は民法第474条に規定されています。この条文によれば、債務の弁済は第三者でも行うことができるとされています。
| 民法第474条 | 「債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。」 |
|---|
上記の条文は第三者弁済の法的根拠となる民法の条文です。原則として誰でも他人の債務を弁済することができますが、例外も設けられています。
例外として、債務の性質上第三者による弁済が適さない場合や、当事者間で第三者弁済を認めない合意がある場合には、第三者弁済が制限されることがあります。
第三者弁済が認められる場合と認められない場合
第三者弁済は原則として認められていますが、すべての状況で可能というわけではありません。特に債務整理の過程では注意が必要です。
第三者弁済が認められる一般的なケース
- 債務者の委託を受けて家族や知人が弁済する場合
- 保証人が保証債務を履行する場合
- 債務者の利益を図るために第三者が弁済する場合
- 通常の金銭債務の弁済
上記は第三者弁済が一般的に認められるケースです。特に家族間の援助や保証人による保証債務の履行は、よく見られる第三者弁済の例です。
第三者弁済が認められないケース
- 債務の性質上、本人による履行が必要な場合(芸術作品の制作など)
- 債権者と債務者の間で第三者弁済を禁止する特約がある場合
- 債権者が第三者からの弁済を拒絶する正当な理由がある場合
- 個人再生手続中や自己破産申立後の特定の債務
上記は第三者弁済が認められないケースです。特に債務整理手続中は、債権者間の公平な扱いを確保するために第三者弁済が制限されることがあります。
第三者弁済と求償権
第三者が債務者に代わって弁済を行った場合、その第三者は原則として債務者に対して求償権を取得します。求償権とは、第三者が支払った金額を債務者に請求できる権利のことです。
求償権の発生は第三者弁済を行った状況によって異なります。債務者の依頼を受けて弁済した場合と、依頼なく弁済した場合で扱いが変わります。
- 委託を受けた弁済:債務者の依頼や同意を得て弁済した場合、第三者は当然に求償権を取得します。
- 委託を受けない弁済:債務者の意思に関わらず弁済した場合、債務者の利益となる限度で求償権を取得します。
- 債権者の承諾を得た弁済:特別な場合には、第三者が債権者から債権を譲り受けることもあります(弁済による代位)。
上記は第三者弁済における求償権の発生パターンを示しています。特に家族間での第三者弁済では、後のトラブルを避けるために求償権の扱いを事前に明確にしておくことが重要です。
債務整理における第三者弁済の注意点
債務整理を検討している場合や手続中の場合、第三者弁済には特に注意が必要です。状況によっては債務整理の手続きに悪影響を及ぼす可能性があります。
| 個人再生における注意点 |
|
|---|---|
| 自己破産における注意点 |
|
上記の表は債務整理手続における第三者弁済の主な注意点をまとめたものです。債務整理中に第三者弁済を検討する場合は、必ず専門家に相談することをおすすめします。
特に破産手続では、破産申立前の一定期間内に行われた第三者弁済が否認される可能性があります。これは債権者間の公平性を確保するための規定です。
よくある質問
Q1. 第三者弁済をすると、債務者の信用情報に影響はありますか?
第三者弁済であっても、元々の返済期日に間に合わなかった場合は、債務者の信用情報に延滞情報として登録される可能性があります。第三者が弁済しても、債務者本人の返済責任や信用情報への影響は基本的に変わりません。
Q2. 債務者が自己破産する予定ですが、親が借金を返済したいと言っています。問題ありませんか?
自己破産を検討している場合、破産申立前の親族による第三者弁済は偏頗弁済とみなされるリスクがあります。破産申立前の一定期間内の弁済は否認される可能性もあるため、事前に専門家への相談をおすすめします。
Q3. 第三者弁済をした場合、弁済した金額を債務者に請求できますか?
債務者の依頼や同意を得て弁済した場合は、原則として債務者に対して求償権を取得します。依頼なく弁済した場合でも、債務者の利益となる限度で求償権が発生します。ただし、贈与の意思で弁済した場合は求償権は発生しません。
Q4. 過払い金請求中に、第三者が残債を弁済することはできますか?
過払い金請求中でも、第三者弁済は基本的に可能です。ただし、過払い金が発生している可能性がある場合、第三者弁済より先に過払い金を清算するほうが合理的なケースもあります。専門家に相談することをおすすめします。
Q5. 任意整理中に家族が一部の債務を第三者弁済することは可能ですか?
任意整理中の第三者弁済は基本的に可能ですが、特定の債権者だけを優遇すると他の債権者との交渉に悪影響を及ぼす可能性があります。任意整理を担当している専門家に事前に相談することが重要です。
まとめ
第三者弁済は、債務者本人ではなく第三者(主に家族や知人)が債務者に代わって債務を返済する制度です。民法第474条に基づき認められており、原則として債権者の同意なく行うことができます。
第三者弁済には「委託を受けた弁済」と「委託を受けない弁済」があり、どちらの場合も債務自体は消滅しますが、弁済した第三者には債務者に対する求償権が発生する場合があります。
債務整理の手続中は第三者弁済に関して特別な注意が必要です。個人再生や自己破産の手続中は、再生計画外の弁済や偏頗弁済とみなされるリスクがあります。特に破産申立前の一定期間内に行われた第三者弁済は否認されることもあります。
また、第三者弁済を行っても債務者の信用情報への影響は基本的に変わりません。延滞が発生した場合は、第三者が後から弁済しても信用情報には延滞として記録されます。
第三者弁済を検討する際は、債務整理の方針や求償権の扱いについて事前に専門家に相談することをおすすめします。特に家族間での第三者弁済では、後のトラブルを避けるために弁済の意図(贈与か求償を前提とするか)を明確にしておくことが重要です。
借金問題に強い杉山事務所の無料相談
| おすすめの理由 |
|---|
| 毎月1万件以上の豊富な実績 |
| 初期費用や相談料が無料 |
| 過払い金の回収額が毎月1億円以上 |



