相保証(あいほしょう)について詳しく解説
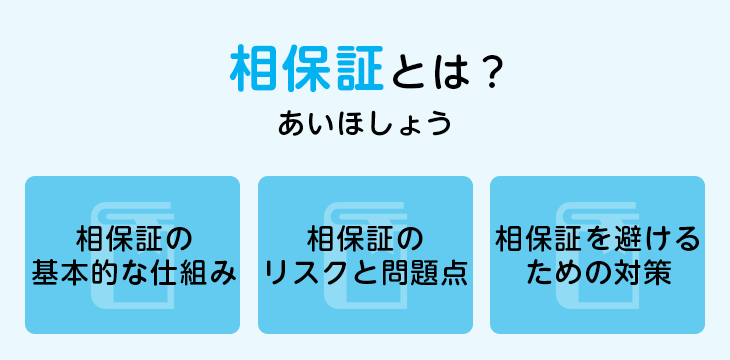
相保証とは、お互いが相手の保証人になる関係のことを指します。債務整理や過払い金請求を考える上で、この仕組みを理解することは非常に重要です。相保証関係にある場合、どちらかが返済不能になると、もう一方が責任を負うことになります。
相保証の基本的な仕組み
相保証とは、友人や知人、家族など親しい間柄の人同士が、互いにローンやクレジットの保証人になることです。例えば、AさんがBさんの借金の保証人となり、同時にBさんもAさんの借金の保証人になるという関係です。
この仕組みは主に消費者金融やカードローンなどで見られることがあります。一見すると「お互いさま」の関係に思えますが、実際には双方にとって大きなリスクをはらんでいます。
| 相保証の一般的な例 | 友人同士でのカードローン、親族間での住宅ローン、会社の同僚間での事業資金など |
|---|---|
| 法的位置づけ |
|
上記の表は相保証の基本的な例と法的な位置づけを示しています。それぞれの保証契約は独立しているため、一方の契約が無効になっても、もう一方の契約は有効なままである点に注意が必要です。
相保証のリスクと問題点
相保証には多くのリスクが伴います。最も大きな問題は、「連鎖倒産」のようなリスクです。一方が返済不能になると、保証人であるもう一方も支払い義務を負うことになります。
例えば、AさんとBさんが相保証関係にある場合、Aさんが返済できなくなると、Bさんが代わりに返済する義務を負います。しかし、BさんもAさんの借金を負担することで経済的に苦しくなり、自分の借金も返済できなくなる可能性があります。
- 両者ともに返済能力を失うリスク
- 一方の債務整理が他方に影響する
- 人間関係の悪化や断絶
- 保証債務の範囲が予想以上に広がる可能性
相保証関係にある場合、上記のようなリスクが存在します。特に人間関係への影響は深刻で、親しい間柄が金銭問題によって壊れてしまうケースも少なくありません。
債務整理時の相保証の影響
債務整理を行う場合、相保証関係にあると様々な影響が生じます。特に注意すべきなのは、自己破産や任意整理などの債務整理を行うと、保証人に返済義務が移ることです。
| 債務整理の種類 | 相保証人への影響 |
|---|---|
| 自己破産 |
|
| 個人再生 |
|
| 任意整理 |
|
上記の表は、各債務整理方法における相保証人への影響を示しています。どの方法を選択する場合でも、相保証人には大きな負担がかかることが分かります。
特に自己破産の場合、主債務者は免責されても保証人の責任は免除されないため、保証人が全額の返済を求められることになります。このことから、債務整理を検討する際は、相保証関係にある人との話し合いが非常に重要です。
過払い金請求と相保証の関係
過払い金請求を行う場合でも、相保証関係が影響することがあります。過払い金が発生していた場合、主債務者に返還されるのが原則ですが、保証人が代位弁済していた場合は状況が変わります。
- 主債務者が過払い金請求を行い、返還金を受け取る
- 保証人が代位弁済していた場合、その範囲内で保証人に返還請求権が移る可能性がある
- 保証人自身も過払い金が発生していた場合は、別途請求が必要
- 保証人と主債務者の間で返還金の取り扱いについて紛争が生じるケースもある
過払い金請求においても相保証関係が複雑な影響を及ぼすことがあります。債権者、主債務者、保証人の三者間の権利関係を正確に把握することが重要です。
相保証を避けるための対策
相保証のリスクを考えると、できる限り相保証関係を避けることが望ましいと言えます。以下に相保証を避けるための対策をご紹介します。
- 第三者の保証人を立てる(親族など)
- 物的担保を提供する(不動産など)
- 保証会社や信用保証協会を利用する
- 無担保・無保証のローン商品を選ぶ
- 少額から借入を始め、信用実績を積む
上記のリストは相保証を避けるための主な対策です。特に保証会社の利用は、個人間の保証関係を作らずに済むため、人間関係を守る点でもおすすめの方法です。
また、そもそも借入を減らす生活設計を心がけることも重要です。無理のない返済計画を立て、計画的な資金管理を行うことで、借入自体を最小限に抑えることができます。
相保証に関する法律の最新動向
近年、保証人保護の観点から、保証制度に関する法改正が行われています。2020年4月に施行された改正民法では、個人保証に関する規制が強化されました。
| 改正民法のポイント | 相保証への影響 |
|---|---|
| 事業用融資の保証制限 |
|
| 極度額の設定義務 |
|
| 情報提供義務 |
|
上記の表は、改正民法における保証制度の変更点と相保証への影響を示しています。これらの法改正により、無理な相保証が結ばれるリスクは以前よりも低減されています。
ただし、すでに結ばれている保証契約については原則として旧法が適用されるため、既存の相保証関係については注意が必要です。法律の適用関係については、専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
相保証は、お互いが相手の保証人となる関係であり、一見便利に思えますが、実際には多くのリスクを伴います。特に債務整理を行う場合、相保証関係にあるともう一方に大きな負担がかかることになります。
自己破産や個人再生などの債務整理を検討する際は、相保証関係にある人への影響を十分に考慮する必要があります。相保証人との間で事前に十分な話し合いを行い、双方にとって最適な解決策を見つけることが重要です。
近年の法改正により保証人保護の規制は強化されていますが、既存の相保証関係については引き続き注意が必要です。借入を行う際は、相保証ではなく保証会社の利用など、他の選択肢を検討することをおすすめします。
債務問題は一人で抱え込まず、早めに専門家に相談することが解決への第一歩です。司法書士や弁護士などの専門家に相談し、自分の状況に合った最適な解決策を見つけましょう。
借金問題に強い杉山事務所の無料相談
| おすすめの理由 |
|---|
| 毎月1万件以上の豊富な実績 |
| 初期費用や相談料が無料 |
| 過払い金の回収額が毎月1億円以上 |



