検認(けんにん)とは?
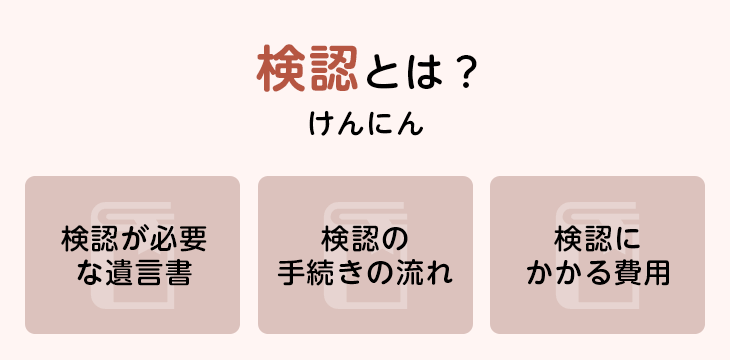
検認とは、遺言書の形式や存在を家庭裁判所が確認し、正式に証明する手続きです。この手続きは、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合に必要となります。
相続人が遺言書を発見した場合、原則として家庭裁判所での検認手続きを経なければ、遺言の内容を実行することができません。検認は遺言の有効性を確認するものではなく、あくまで遺言書の形式的な確認を行うための手続きです。
検認とは?
検認とは、遺言書の存在と内容を家庭裁判所が公的に確認し、記録する手続きです。この手続きは民法第1004条に規定されており、遺言書の偽造や変造、破棄を防ぐことを目的としています。
検認では、遺言書の形式的な確認を行うだけで、遺言書の内容が法的に有効かどうかを判断するものではありません。つまり、検認を経た遺言書であっても、内容に問題があれば無効となる可能性はあります。
| 検認の目的 | 遺言書の偽造・変造・破棄を防止し、遺言の内容を公的に確認すること |
|---|---|
| 検認の効果 |
|
上記の表は、検認の目的と効果をまとめたものです。検認は単なる形式的な手続きではなく、相続手続きを円滑に進めるための重要なステップといえます。
検認が必要な遺言書と不要な遺言書
すべての遺言書に検認が必要というわけではありません。遺言書の種類によって、検認が必要な場合と不要な場合があります。
| 検認が必要な遺言書 |
|
|---|---|
| 検認が不要な遺言書 |
|
この表は、検認が必要な遺言書と不要な遺言書を示しています。公正証書遺言は、公証人が関与して作成されるため、その存在と内容が公的に証明されていることから検認が不要です。また、2020年7月に施行された自筆証書遺言の法務局保管制度を利用した場合も検認は不要となります。
自筆証書遺言の検認
自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自筆で書き、押印して作成する遺言書です。この遺言書は、相続人などが発見した場合、速やかに家庭裁判所に提出して検認手続きを行わなければなりません。
なお、2019年1月の民法改正により、財産目録については自筆でなくてもよいことになりました。パソコンで作成したり、通帳のコピーを添付したりすることも可能です。ただし、この場合も遺言者の署名と押印が各ページに必要です。
法務局保管制度による自筆証書遺言
2020年7月10日からスタートした自筆証書遺言の法務局保管制度を利用した場合は、検認が不要となりました。この制度を利用すると、遺言書が法務局で厳重に保管され、相続開始後に相続人等が法務局から遺言書の原本の閲覧や正本の交付を受けることができます。
この制度を利用することで、遺言書の紛失や隠匿、偽造などのリスクを回避でき、また検認手続きの手間も省けるというメリットがあります。
検認の手続きの流れ
検認手続きは、以下の流れで進められます。遺言書を発見した場合は、速やかに手続きを開始することが大切です。
- 遺言書の発見:遺言書を発見した相続人または遺言執行者は、速やかに家庭裁判所に提出する必要があります
- 申立書の提出:亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、検認の申立書を提出します
- 必要書類の準備:遺言書原本、申立人の戸籍謄本、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本などを準備します
- 検認期日の指定:裁判所から検認期日の通知が届きます
- 検認期日の出頭:申立人は指定された日時に裁判所に出頭し、裁判官が遺言書を確認します
- 相続人への通知:裁判所から相続人全員に検認の日時が通知され、できる限り全員の立会いが求められます
- 検認調書の作成:検認の結果は調書として作成され、遺言書には検認済みの証明印が押されます
- 遺言書の返還:検認後、遺言書は申立人に返還されます
上記は検認手続きの一般的な流れです。実際の手続きは、ケースによって若干異なる場合があります。初めての方は、専門家(司法書士や弁護士など)に相談することをおすすめします。
申立てに必要な書類
- 検認申立書(裁判所に備え付けの書式あり)
- 遺言書の原本
- 亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 申立人の印鑑(認印可)
- 収入印紙と郵便切手(裁判所によって金額が異なります)
この書類リストは検認申立てに一般的に必要な書類です。裁判所によって追加の書類が求められる場合もありますので、事前に管轄の家庭裁判所に確認することをおすすめします。
検認手続きにかかる費用
検認手続きにかかる費用は主に以下の通りです。予算を検討する際の参考にしてください。
| 収入印紙代 | 800円(検認申立手数料) |
|---|---|
| 郵便切手代 | 相続人の人数によって異なる(数百円〜数千円程度) |
| 戸籍謄本等の取得費用 | 1通450円程度(必要な通数は相続人の人数などによって異なります) |
| 交通費 | 裁判所への往復交通費 |
| 専門家に依頼する場合 | 司法書士や弁護士に依頼する場合は別途報酬が必要(5万円〜10万円程度) |
上記の費用は一般的な目安です。実際の費用は、相続人の人数や状況によって変動します。特に専門家に依頼する場合は、事前に見積もりを確認することをおすすめします。
検認を行わないとどうなるのか
検認が必要な遺言書について検認手続きを行わないと、以下のようなリスクや問題が生じる可能性があります。
- 遺言の効力が否定される可能性がある(遺言自体が無効になるわけではないが、検認を経ていない遺言書に基づく手続きは受け付けられないことがある)
- 相続登記や名義変更などの手続きができない場合がある
- 遺言の内容に疑義が生じた際に、証明が困難になる
- 遺言書を提出しなかった場合、過料(5万円以下)が科される可能性がある
- 相続人間のトラブルの原因となる可能性がある
上記のリストは、検認を行わない場合のリスクを示しています。検認は面倒な手続きに感じるかもしれませんが、後々のトラブルを防ぐために重要な手続きです。特に相続財産が多い場合や、相続人間の関係が良好でない場合は、必ず検認手続きを行うことをおすすめします。
よくある質問
Q1. 検認は誰が申し立てるものですか?
検認の申立ては、遺言書を発見した相続人や遺言執行者が行うのが一般的です。ただし、相続人であれば誰でも申し立てることができます。遺言書を発見した人には、速やかに検認の申立てを行う義務があります。
Q2. 検認手続きにはどのくらい時間がかかりますか?
検認手続きにかかる時間は、裁判所の混雑状況や相続人の人数などによって異なります。一般的には、申立てから検認期日までに1〜2ヶ月程度かかることが多いです。相続人が多数いる場合や、海外に居住している相続人がいる場合は、さらに時間がかかることがあります。
Q3. 検認期日に全ての相続人が出席する必要がありますか?
検認期日には、できるだけ全ての相続人が出席することが望ましいですが、必ずしも全員の出席が必要というわけではありません。欠席する場合は、裁判所に事前に連絡しておくとよいでしょう。なお、申立人(遺言書を提出した人)は必ず出席する必要があります。
Q4. 検認後に遺言書の内容に不服がある場合はどうすればよいですか?
検認は遺言書の形式的な確認にすぎず、内容の有効性を判断するものではありません。そのため、検認後に遺言書の内容に不服がある場合は、遺言無効確認の訴えを提起するなど、別途法的手続きを取る必要があります。このような場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
Q5. 法務局保管制度を利用した自筆証書遺言はなぜ検認が不要なのですか?
法務局保管制度を利用した自筆証書遺言は、法務局が遺言書の形式的な確認を行った上で保管するため、遺言書の偽造や変造のリスクがないからです。また、相続開始後は法務局から相続人等に遺言書の内容が正確に伝えられるため、検認の目的がすでに達成されているといえます。
まとめ
検認とは、遺言書の存在と内容を家庭裁判所が確認し、公的に証明する手続きです。自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合に必要となる手続きで、遺言書の偽造や変造を防ぐという重要な役割を果たしています。
検認が必要な遺言書を発見した場合は、速やかに家庭裁判所に申立てを行う必要があります。申立てには、遺言書原本や戸籍謄本などの書類が必要で、費用としては収入印紙代や郵便切手代などがかかります。
検認を行わないと、遺言に基づく相続手続きができなくなったり、相続人間のトラブルの原因となったりするリスクがあります。一方、公正証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言は、検認が不要となっています。
相続手続きを円滑に進めるためにも、遺言書の形式や検認の必要性について正しく理解し、適切に対応することが大切です。不安な点があれば、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。






