贈与税の配偶者控除(ぞうよぜいのはいぐうしゃこうじょ)とは?
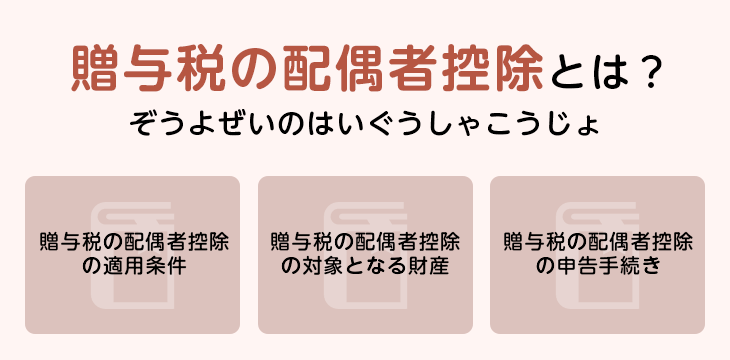
贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の配偶者から、居住用の不動産や居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合に、贈与税の基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できる特例制度です。
この特例により、夫婦間での自宅の名義変更や住宅取得資金の贈与に対する税負担を軽減することができます。
贈与税の配偶者控除とは
贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用の不動産またはその取得資金の贈与があった場合に適用される特例です。
通常の贈与では年間110万円を超える部分に贈与税がかかりますが、この特例を利用すると基礎控除110万円に加えて最高2,000万円まで控除することができます。
つまり、最大で2,110万円までの贈与について贈与税が非課税となる制度です。
| 控除額の上限 | 基礎控除110万円+配偶者控除2,000万円=最大2,110万円 |
|---|---|
| 適用回数 | 一生に一度のみ |
この表は贈与税の配偶者控除の控除額上限と適用回数を示しています。一生に一度しか使えない特例であることに注意が必要です。
贈与税の配偶者控除の適用条件
贈与税の配偶者控除を受けるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 贈与を受けた時点で婚姻期間が20年以上であること
- 居住用の不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告をすること
- 贈与を受けた不動産に贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住していること、または居住することが確実であると見込まれること
- 金銭の贈与の場合、その金銭で贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住用不動産を取得し、居住していること、または居住することが確実であると見込まれること
上記の条件は贈与税の配偶者控除を適用するための必須条件です。特に婚姻期間20年以上という条件と、居住用という目的限定が重要なポイントとなります。
贈与税の配偶者控除の対象となる財産
贈与税の配偶者控除の対象となる財産は、以下の2種類に限定されています。
| 居住用不動産 | 配偶者が居住するための家屋(敷地を含む) |
|---|---|
| 居住用不動産取得資金 |
|
この表は贈与税の配偶者控除の対象となる財産の種類を示しています。投資用不動産や別荘などは対象外となりますので注意が必要です。
対象外となる財産の例
- 賃貸用や事業用の不動産
- 別荘や二世帯住宅の親世帯部分
- 現金(居住用不動産の取得目的でない場合)
- 有価証券や預貯金
- 自動車などの動産
上記は贈与税の配偶者控除の対象とならない財産の例です。あくまで「居住用」という目的に合致する財産のみが対象となります。
贈与税の配偶者控除の申告手続き
贈与税の配偶者控除を受けるためには、必ず贈与税の申告が必要です。申告の流れは以下のとおりです。
- 贈与を受ける:配偶者から居住用不動産または資金の贈与を受けます
- 必要書類の準備:戸籍謄本(婚姻期間20年以上の証明)、不動産の登記事項証明書、贈与契約書などを準備します
- 申告書の作成:贈与税申告書と配偶者控除の特例適用に関する明細書を作成します
- 申告・納税:贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日までに税務署へ申告します
贈与税の配偶者控除の申告手続きでは、婚姻期間の証明や贈与の事実を証明する書類が重要です。期限内に適切な申告を行わないと特例が適用されないので注意が必要です。
| 必要書類 |
|
|---|
この表は贈与税の配偶者控除の申告に必要な書類をまとめたものです。事前に準備しておくことで、スムーズな申告が可能になります。
贈与税の配偶者控除の注意点
贈与税の配偶者控除を活用する際には、以下の注意点に気をつけましょう。
- 一生に一度しか利用できない特例です
- 住宅取得等資金の贈与税非課税制度との併用はできません
- 贈与を受けた不動産に居住していなければ、特例が適用されません
- 贈与を受けた後、3年以内に贈与者(配偶者)が亡くなった場合、相続時精算課税制度を選択していなければ、相続税の対象となる可能性があります
- 既に相続時精算課税制度を選択している場合、贈与税の配偶者控除との併用はできません
上記は贈与税の配偶者控除を利用する際の主な注意点です。他の税制優遇措置との併用可否や、申告漏れがないようにしましょう。
よくある質問
Q1. 婚姻期間はどのように計算するのですか?
婚姻期間は、婚姻の届出をした日から贈与を受けた日までの期間で計算します。
入籍日から贈与の日までが20年以上経過していることが必要です。
途中で離婚や再婚があった場合は、再婚後の期間のみが対象となります。
Q2. マンションの購入資金を贈与された場合も対象になりますか?
はい、マンションも居住用不動産に該当するため、対象となります。
ただし、実際にそのマンションに居住する必要があります。
投資用や賃貸用として購入する場合は、対象外となるのでご注意ください。
Q3. リフォーム費用の贈与も対象になりますか?
増改築のための費用は対象となりますが、単なる修繕や模様替えは対象外です。
対象となるのは、家屋の床面積が増加するような工事や、耐震性・バリアフリー性を高める工事などです。
リフォームの内容によって判断が異なるため、事前に税務署に確認することをおすすめします。
Q4. 控除額が2,000万円未満の場合、残りを後日利用できますか?
いいえ、控除額の残りを後日利用することはできません。
たとえば1,500万円の贈与に対して配偶者控除を適用した場合、残りの500万円分を次回の贈与で使うことはできません。
一生に一度の特例であり、控除限度額に満たない場合でも、その機会を使ったものとみなされます。
Q5. 相続時精算課税制度と贈与税の配偶者控除はどちらが有利ですか?
どちらが有利かは、資産状況や将来の相続の見通しによって異なります。
相続時精算課税制度は2,500万円までの贈与が非課税になりますが、将来相続が発生した際に相続財産に加算されます。
一方、贈与税の配偶者控除は最大2,000万円までですが、将来の相続財産には加算されません(3年以内の贈与を除く)。
総合的な税負担を考慮して、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産や居住用不動産取得資金の贈与に適用される特例です。
基礎控除110万円に加えて最大2,000万円まで控除できるため、最大で2,110万円までの贈与が非課税となります。
この特例を活用するためには、婚姻期間20年以上という条件や、実際に贈与された不動産に居住するという条件を満たす必要があります。
また、申告期限や必要書類の準備も重要です。贈与を受けた年の翌年3月15日までに必ず申告を行いましょう。
贈与税の配偶者控除は一生に一度しか利用できない特例であり、他の特例との併用制限もあります。自分の状況に最適な贈与方法を選ぶためには、税理士などの専門家への相談もおすすめします。
夫婦間の資産移転や住宅取得に関する税負担を軽減するこの制度を、ぜひ賢く活用してください。






