財産評価基本通達(ざいさんひょうかきほんつうたつ)とは?
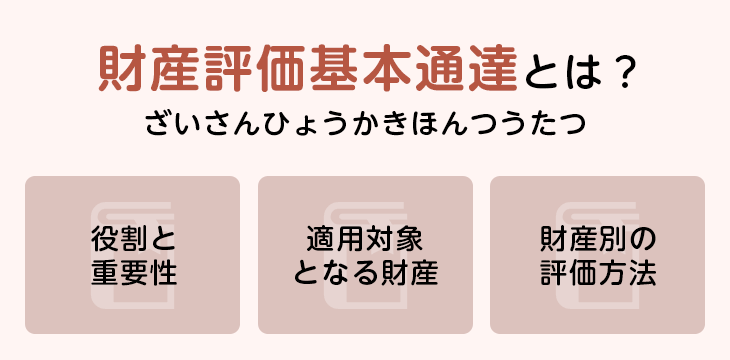
財産評価基本通達とは、相続税や贈与税の計算において、財産の評価方法を定めた国税庁の内部規則です。相続や贈与で取得した財産の価値を客観的に評価するための詳細なルールが記載されています。
この通達は法律そのものではありませんが、税務署や税務調査官が財産評価を行う際の統一的な基準として機能しています。相続税や贈与税の申告を正確に行うためには、この通達の内容を理解することが非常に重要です。
財産評価基本通達の役割と重要性
財産評価基本通達は、相続税や贈与税の課税対象となる財産の評価額を決定するための指針として極めて重要な役割を担っています。この通達に従って財産評価を行うことで、全国どこでも統一的な基準で財産価値が算定されます。
通達に基づく評価額は、相続税や贈与税の計算の基礎となるため、節税対策を考える上でも通達の内容を理解することは非常に有益です。また、税務調査の際にも評価額の妥当性が通達に基づいて判断されます。
| 財産評価基本通達の特徴 | 国税庁長官から各国税局長や税務署長に対して発せられる内部的な指示文書です |
|---|---|
| 法的位置づけ |
|
上記の表は財産評価基本通達の特徴と法的位置づけを示しています。法令ではありませんが、実務上は非常に重要な基準となっています。
財産評価基本通達の適用対象となる財産
財産評価基本通達は、相続税や贈与税の課税対象となるあらゆる種類の財産の評価方法を規定しています。土地や建物などの不動産から株式、預貯金、美術品、特許権など様々な財産が対象です。
- 土地(宅地、農地、山林など)
- 建物(居住用、事業用、賃貸用など)
- 有価証券(上場株式、非上場株式、国債、社債など)
- 現金・預貯金・生命保険金
- 事業用資産(機械設備、商品、のれんなど)
- 無形資産(特許権、著作権、商標権など)
- その他の財産(骨董品、美術品、宝飾品など)
上記のリストは財産評価基本通達が適用される主な財産の種類です。それぞれの財産について、詳細な評価方法が通達内で定められています。
財産評価の原則と基本的な考え方
財産評価基本通達では、財産評価に関する基本的な考え方として「時価主義」を採用しています。時価とは、その財産の取得の時における「客観的な交換価値」を意味します。
しかし、全ての財産について個別に時価を算定することは実務上困難なため、財産の種類ごとに合理的な評価方法が定められています。この評価方法に従って算出された価額は、特別な事情がない限り「時価」として取り扱われます。
| 時価の基本的な考え方 | 不特定多数の当事者間で自由な取引が行われた場合に通常成立すると認められる価額 |
|---|---|
| 評価の基本原則 |
|
上記の表は財産評価における時価の考え方と評価の基本原則を示しています。相続税・贈与税の財産評価は、これらの原則に基づいて行われます。
主な財産別の評価方法
土地の評価方法
土地は、相続財産の中でも大きな割合を占めることが多く、その評価方法は特に重要です。土地の用途や地域によって異なる評価方法が適用されます。
- 宅地:路線価方式または倍率方式で評価
- 農地:農地倍率や純農地価額等で評価
- 山林:山林の立木と林地を区分して評価
- 貸家建付地:貸家建付地補正により評価減
上記は土地の種類別の主な評価方法です。特に宅地については、路線価方式(路線価が定められている地域)と倍率方式(その他の地域)の2つの方法があります。
建物の評価方法
建物は原則として固定資産税評価額によって評価されます。ただし、建物の種類や用途によって評価方法に違いがあります。
| 一般の建物 | 固定資産税評価額 |
|---|---|
| 貸家 | 固定資産税評価額 × (1 – 借家権割合 × 賃貸割合) |
| 区分所有建物 | 専有部分の固定資産税評価額 + 共用部分の持分に対応する固定資産税評価額 |
上記の表は建物の種類別の評価方法を示しています。貸家の場合は借家権による評価減が認められています。
株式の評価方法
株式の評価方法は、上場株式と非上場株式で大きく異なります。特に非上場株式の評価は複雑で、会社の規模や種類によって異なる評価方法が適用されます。
- 上場株式:課税時期の終値または課税時期の月の毎日の終値の月平均額
- 非上場株式(大会社):類似業種比準方式と純資産価額方式の併用
- 非上場株式(中会社):類似業種比準価額と純資産価額の折衷方式
- 非上場株式(小会社):原則として純資産価額方式
上記のリストは株式の評価方法を示しています。非上場株式については会社の規模によって異なる評価方法が適用されます。
財産評価基本通達の改正と最新情報
財産評価基本通達は、社会経済情勢の変化や税制改正に伴って定期的に改正されています。土地や株式などの評価方法が見直されることもあるため、最新の通達内容を把握することが重要です。
特に、相続税や贈与税の税制改正があった場合には、通達の改正にも注意が必要です。税理士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
| 通達改正の主な情報源 |
|
|---|
上記の表は財産評価基本通達の改正情報を入手できる主な情報源です。定期的に最新情報を確認することが大切です。
よくある質問
Q1. 財産評価基本通達と法律との関係はどうなっていますか?
財産評価基本通達は法律ではなく、国税庁の内部規則です。しかし、税務実務においては法律と同様の効力を持つことが多く、税務署も通達に基づいて財産評価を行います。
ただし、通達による評価方法が著しく不合理な場合や特別な事情がある場合には、別の評価方法が認められることもあります。このような場合は税務署との協議や税務訴訟が必要になることもあります。
Q2. 相続財産の評価で通達と実際の市場価格に差がある場合はどうすればよいですか?
通達による評価額と実際の市場価格には差が生じることがあります。原則として税務署は通達に基づく評価を尊重しますが、特別な事情がある場合は個別評価が認められることもあります。
例えば、土地に特殊な形状や利用制限がある場合などは、通達の評価方法に補正を加えることが可能です。このような場合は専門家に相談することをおすすめします。
Q3. 非上場株式の評価方法はどのように決まりますか?
非上場株式の評価方法は、会社の規模や種類によって異なります。大会社は類似業種比準方式、小会社は純資産価額方式が原則とされ、中会社はその折衷方式となります。
会社の規模は、従業員数、総資産価額、年間取引金額の3つの指標に基づいて判定されます。また、同族株主かどうかによっても評価方法が異なる場合があります。
Q4. 路線価方式と倍率方式の違いは何ですか?
路線価方式は、国税庁が定めた路線価(道路に面した宅地の1平方メートル当たりの評価額)に基づいて土地を評価する方法です。主に市街地など路線価が設定されている地域で適用されます。
一方、倍率方式は、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価する方法です。路線価が設定されていない地域で適用されます。どちらの方式が適用されるかは地域によって決まります。
Q5. 財産評価に不服がある場合はどうすればよいですか?
相続税や贈与税の申告後に税務署から更正処分を受け、その財産評価に不服がある場合は、「異議申立て」や「審査請求」といった不服申立ての制度を利用できます。
財産評価に関する不服は、専門的な知識が必要なケースが多いため、税理士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。不服申立ては期限がありますので、早めの対応が大切です。
まとめ
財産評価基本通達は、相続税や贈与税の計算に必要な財産評価の方法を定めた国税庁の内部規則です。相続や贈与で取得した財産の「時価」を客観的に評価するための統一的な基準として、全国の税務署で適用されています。
土地、建物、株式などの財産ごとに異なる評価方法が定められており、特に土地の路線価方式や非上場株式の評価方法は複雑なルールとなっています。これらの評価方法を理解することは、相続税や贈与税の適正な申告や節税対策を考える上で非常に重要です。
財産評価基本通達は定期的に改正されるため、最新の内容を把握しておくことも大切です。相続や贈与の計画を立てる際には、専門家のアドバイスを受けながら、通達に基づく正確な財産評価を行うことをおすすめします。






