遺言書(ゆいごんしょ・いごんしょ)とは?
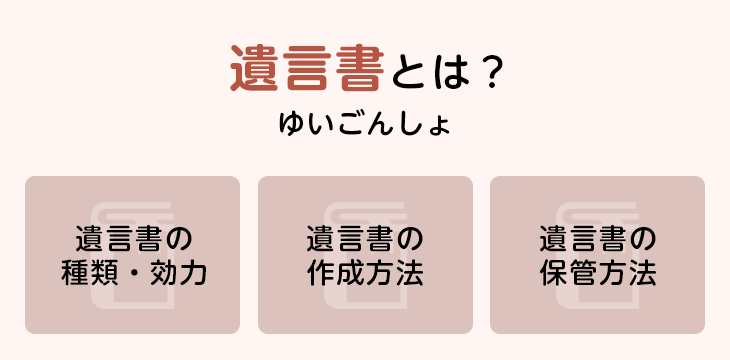
遺言書とは、人が亡くなった後に自分の財産をどのように分配するかなどの意思を示すために作成する文書です。「ゆいごんしょ」と「いごんしょ」という2つの読み方があり、それぞれ意味合いが異なります。
「ゆいごんしょ」は広い意味で死後のために生前に言い残したり書き残したりしたもの全般を指し、「いごんしょ」は法的効力を持つ文書として主に法律家が使う表現です。相続トラブルを事前に防ぎ、ご自身の最終的な意思を確実に実現するための重要な手段となります。
「ゆいごんしょ」と「いごんしょ」の違い
遺言書には「ゆいごんしょ」と「いごんしょ」という2つの読み方があります。どちらも正しい読み方ですが、その意味合いには違いがあります。
| ゆいごんしょ | 死後のために生前に言い残したり書き残したりしたもの全般を広く指します。法的効力の有無を問わず、感謝の手紙やビデオメッセージなども含まれます。 |
|---|---|
| いごんしょ | 生前に残す言葉の中でも、民法で定められた方式に従って作成された法的効力を持つ文書を指します。主に法律家が使う表現です。 |
上記の表は「ゆいごんしょ」と「いごんしょ」の違いを示しています。死後に備えた生前準備として残すメッセージはすべて「ゆいごんしょ」に含まれる広い概念です。
例えば、家族への感謝の手紙、お葬式の参列者へのビデオメッセージ、配偶者へのテープレコーダーなど、死後に残す様々なメッセージは「ゆいごんしょ」に含まれます。一方、「いごんしょ」は民法第967条から第975条までのルールに従って作成された法的効力のある文書のみを指します。
遺言書の種類
法的効力を持つ「いごんしょ」には主に以下の種類があります。それぞれ作成方法や有効要件が異なりますので、状況に応じて適切な形式を選ぶことが重要です。
| 自筆証書遺言 | 遺言者が全文を自筆で書き、日付と氏名を記載して押印する遺言書です。費用がかからず手軽に作成できますが、形式不備による無効リスクがあります。 |
|---|---|
| 公正証書遺言 | 公証人の関与のもと作成される遺言書です。公証人が証人の立会いのもとで遺言者の口述を筆記し、作成された遺言書は公証役場で保管されます。 |
| 秘密証書遺言 | 遺言内容を秘密にしたい場合に選ばれる方法です。遺言者が作成した遺言書を封筒に入れ、公証人と証人の前で封印手続きを行います。 |
| 特別方式の遺言 | 死が差し迫っている状況や伝染病で隔離されている場合など、通常の方式では遺言書作成が難しい人向けの特例です。証人の人数や署名・押印の要件が状況に応じて緩和されます。 |
| 法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言 | 2020年7月から始まった制度で、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえます。検認不要となり、紛失や改ざんのリスクを軽減できます。 |
上記の表は民法で定められている遺言書の主な種類です。それぞれメリット・デメリットがありますので、自分の状況に合った遺言書を選ぶことが大切です。
遺言書の効力
法的効力のある遺言書(いごんしょ)は遺言者の死亡時に効力を生じます。有効な遺言書があれば、法定相続分に優先して遺言内容が実現されます。ただし、遺留分を侵害する場合は、遺留分権利者から減殺請求される可能性があります。
遺言書に記載できる主な内容には以下のものがあります。
遺言書には民法で定められた要件を満たさなければ効力が生じない「要式性」があります。形式不備があると遺言自体が無効になる可能性がありますので注意が必要です。
一方、法的効力のない「ゆいごんしょ」(手紙やビデオメッセージなど)は、法律上の財産分配に直接影響しませんが、故人の想いを伝える大切な手段となります。
遺言書の作成方法
自筆証書遺言の作成方法
- 全文を自筆で書く:パソコンやワープロは使用できませんが、財産目録についてはパソコン等で作成可能です
- 日付を記入する:作成年月日を必ず記入します
- 署名・押印する:氏名を自署し、実印でなくても構いませんが押印が必要です
- 訂正がある場合:削除部分に二重線を引き、訂正箇所に押印します
上記の手順は自筆証書遺言を作成する基本的な流れです。形式不備を避けるためにも、専門家に相談することをおすすめします。
公正証書遺言の作成方法
- 公証役場に予約:事前に公証役場へ連絡し、予約を取ります
- 必要書類の準備:戸籍謄本、印鑑証明書、相続財産の資料などを用意します
- 証人の手配:証人2名が必要で、受遺者や相続人は証人になれません
- 公証人の前で口述:公証人に遺言内容を口述します
- 内容確認と署名押印:作成された遺言書の内容を確認し、署名押印します
公正証書遺言は手続きの複雑さがありますが、法的に最も安全な遺言方法です。公証人が関与するため形式不備が少なく、原本が公証役場で保管されるため紛失リスクも低減されます。
遺言書の保管方法
遺言書の保管方法は種類によって異なります。適切な保管が行われないと、せっかく作成した遺言書が見つからなかったり、改ざんされたりするリスクがあります。
| 自筆証書遺言 |
|
|---|---|
| 公正証書遺言 | 原本は公証役場で保管されます。謄本を自分で保管しておくとよいでしょう。 |
| 秘密証書遺言 | 封印された遺言書は公証役場ではなく、遺言者自身が保管します。安全な場所での保管が必要です。 |
どの方法を選んでも、遺言書の保管場所を家族や信頼できる人に伝えておくことが重要です。自筆証書遺言の場合は特に、2020年から始まった法務局保管制度の利用をおすすめします。
遺言書と相続手続き
遺言書が見つかった場合、相続手続きは遺言の内容に沿って進められます。ただし、遺言書の種類によって手続きが異なります。
自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言を見つけた場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。ただし、法務局保管制度を利用した自筆証書遺言は検認不要となります。
検認とは、遺言書の存在と内容を明確にし、改ざんを防止するための手続きです。検認後に相続手続きを進めることができます。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言は検認不要です。遺言書の内容に従って相続手続きを進めることができます。公証役場で原本が保管されているため、相続手続きの際は謄本を取得する必要があります。
遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者が遺言の内容を実現するための手続きを行います。指定がない場合は、相続人自身が手続きを行うことになります。
よくある質問
Q1. 「ゆいごんしょ」と「いごんしょ」は何が違うのですか?
「ゆいごんしょ」は死後に備えて生前に残す言葉や文書全般を広く指し、感謝の手紙やビデオメッセージなども含みます。「いごんしょ」は民法に定められた方式に従って作成された法的効力を持つ文書のみを指します。どちらも読み方としては正しいですが、法的な文脈では「いごんしょ」が使われることが多いです。
Q2. 遺言書は何歳から作成できますか?
遺言書は満15歳以上であれば作成することができます。ただし、未成年者の場合も親権者の同意は不要です。認知症など判断能力に問題がある場合は、遺言能力がないとみなされ、有効な遺言書を作成できません。
Q3. 遺言書は書き直すことができますか?
はい、遺言書は生前であれば何度でも書き直すことができます。新しい遺言書が有効となり、古い遺言書は自動的に無効となります。ただし、一部だけを変更したい場合は「遺言の変更」として新たに遺言書を作成する必要があります。
Q4. 特別方式の遺言とは何ですか?
特別方式の遺言は、死が差し迫っている人や伝染病で隔離されている人など、通常の方式では遺言書作成が難しい人向けの特例です。民法第967条から第984条において、証人の人数や本人の自署・押印の要件などが状況に応じて緩和されています。緊急時の例外的な制度として設けられています。
Q5. 遺言書がないとどうなりますか?
遺言書がない場合は、民法で定められた法定相続分に従って遺産が分配されます。法定相続人間で話し合い(遺産分割協議)により分割方法を決めることもできますが、トラブルになりやすいのが実情です。生前の想いを確実に実現するためにも、法的効力のある遺言書の作成をおすすめします。
まとめ
遺言書は「ゆいごんしょ」と「いごんしょ」の2つの読み方があり、それぞれ意味合いが異なります。「ゆいごんしょ」は広く死後のために残す言葉全般を指し、感謝の手紙やビデオメッセージなども含まれます。一方「いごんしょ」は民法に定められた方式に従って作成された法的効力を持つ文書を指します。
法的効力を持つ遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがあり、それぞれ作成方法や保管方法が異なります。また特別の方式として、死が差し迫っている場合など緊急時の特例も民法で定められています。
遺言書を作成することで、法定相続分による画一的な分配ではなく、ご自身の希望通りに財産を分配することが可能になります。また、相続争いを未然に防ぐ効果もあります。有効な遺言書を作成するためには、民法で定められた形式要件を満たす必要があります。
遺言書の保管も重要です。特に自筆証書遺言は法務局保管制度を利用するなど、適切な保管方法を選ぶことをおすすめします。相続に関するトラブルを避けるためにも、専門家に相談しながら遺言書を作成することが賢明です。






