特定遺贈(とくていいぞう)とは?
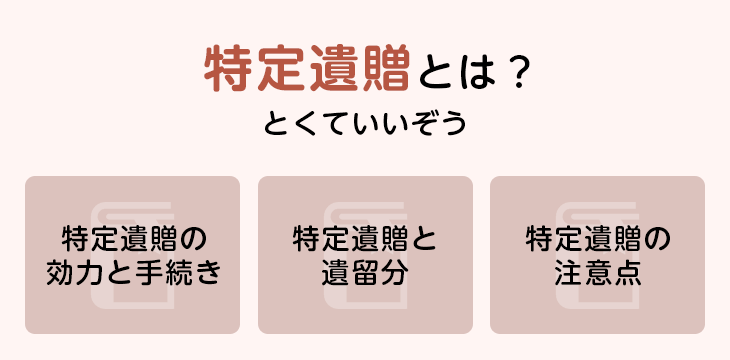
特定遺贈とは、遺言によって遺産の中から特定の財産を特定の人に与える方法です。
例えば「Aさんに自宅不動産を与える」「Bさんに預金1,000万円を与える」というように、具体的な財産を指定して相続人以外の人に遺す場合に用いられます。相続人に対しても特定遺贈をすることができ、法定相続分とは別に特定の財産を残すことが可能です。
特定遺贈の基本
特定遺贈は民法第964条に規定されている遺言の一つの内容です。遺言者が特定の財産を特定の受遺者(受取人)に与えると指定するものです。
特定遺贈の対象となる財産は、不動産や預貯金、有価証券、宝飾品など具体的に特定できるものであれば基本的に何でも構いません。「自宅の土地・建物」「○○銀行の預金口座」などのように明確に指定する必要があります。
受遺者には制限がなく、相続人はもちろん、相続人以外の第三者(友人・知人・団体など)にも遺贈することができます。これが特定遺贈の大きな特徴の一つです。
| 特定遺贈の対象例 |
|
|---|
上記の表は特定遺贈の対象となる代表的な財産例です。遺贈する財産は具体的に特定できるものであれば、基本的にどのような財産でも対象にすることができます。
特定遺贈と包括遺贈の違い
遺贈には「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類があります。両者の違いを理解することは、遺言作成において非常に重要です。
| 特定遺贈 | 特定の財産(例:「自宅不動産」「○○銀行の預金」など)を指定して遺贈します。受遺者は債権者的な立場になり、相続人から財産を受け取る権利を持ちます。 |
|---|---|
| 包括遺贈 | 遺産の全部または一定割合(例:「財産の3分の1」など)を指定して遺贈します。受遺者は相続人と同様の立場(包括受遺者)となり、遺産分割協議に参加します。 |
上記の表は特定遺贈と包括遺贈の主な違いを示しています。特定遺贈では財産を特定するため、受遺者は指定された特定の財産に対する権利のみを取得します。一方、包括遺贈では遺産の割合を指定するため、受遺者は相続人のような立場になります。
特定遺贈と相続の違い
- 相続:法律上当然に相続人が被相続人の権利義務を承継する
- 特定遺贈:遺言によって特定の財産を特定の人に与える
- 相続人の責任:原則として無限責任(限定承認の場合は例外)
- 受遺者の責任:対象財産の価値の範囲内に限定される
上記のリストは相続と特定遺贈の主な違いを示しています。相続人は被相続人の債務も承継しますが、特定遺贈の受遺者は指定された財産のみを受け取るため、債務は承継しません。
特定遺贈の効力発生と手続き
特定遺贈は遺言者の死亡と同時に効力が発生します。しかし、実際に財産を受け取るためには、いくつかの手続きが必要です。
- 遺言書の発見:遺言書が発見され、内容が明らかになる
- 遺言書の検認:自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認手続きが必要
- 遺贈の請求:受遺者は相続人に対して遺贈の履行を請求する
- 財産の移転登記等:不動産の場合は所有権移転登記、預金の場合は名義変更などの手続きを行う
上記は特定遺贈の財産を受け取るまでの一般的な流れです。不動産の場合は登記手続きが必要となり、相続人と受遺者が共同で申請するか、相続人が単独で申請することになります。
受遺者の権利と義務
特定遺贈の受遺者は、遺贈された特定の財産に対する権利を取得します。ただし、その権利の行使にはいくつかの制限や義務が伴います。
| 権利 |
|
|---|---|
| 義務・制限 |
上記の表は特定遺贈の受遺者が持つ権利と義務・制限をまとめたものです。受遺者は単に財産を受け取るだけでなく、税金の支払いや場合によっては特定の負担を負うことになります。
特定遺贈と遺留分
特定遺贈は遺言者の意思により自由に行うことができますが、法定相続人の遺留分を侵害する場合には、遺留分減殺請求(現在の法律では「遺留分侵害額請求」)の対象となります。
遺留分とは、一定の相続人(配偶者、子、直系尊属)に保障されている最低限の相続分のことです。特定遺贈によってこの遺留分が侵害されると、遺留分権利者は受遺者に対して遺留分侵害額請求をすることができます。
| 遺留分の割合 |
|
|---|---|
| 遺留分権利者 |
|
上記の表は遺留分の割合と遺留分権利者についてまとめたものです。兄弟姉妹には遺留分がないため、兄弟姉妹に対する特定遺贈は遺留分の問題は生じません。
遺留分侵害額請求の流れ
- 遺留分の計算:遺産総額から遺留分を算出する
- 侵害額の算定:遺留分から実際に取得した財産を差し引いて侵害額を算定
- 請求の実施:侵害額請求権者が受遺者に対して金銭での支払いを請求
- 支払い:原則として金銭で支払う(合意があれば現物返還も可能)
- 時効:相続開始と侵害を知ってから1年、または相続開始から10年で消滅
上記は遺留分侵害額請求の一般的な流れです。2019年の民法改正により、従来の「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」に変更され、原則として金銭での解決が基本となりました。
特定遺贈を行う際の注意点
特定遺贈を遺言に盛り込む際には、いくつかの重要な注意点があります。適切に準備しないと、遺言者の意思通りに財産が渡らない可能性があります。
- 財産の特定を明確に行う(「○○銀行△△支店の普通預金口座番号□□□□」など)
- 受遺者の特定を明確に行う(「長男A(住所:○○)」など)
- 遺言作成時点で所有していない財産は遺贈できない
- 遺言作成後に遺贈対象の財産を処分した場合、遺贈は効力を失う
- 預貯金の遺贈は、遺言執行者がいないと金融機関が応じないことがある
上記のリストは特定遺贈を行う際の主な注意点です。特に財産と受遺者の特定は明確に行う必要があり、あいまいな表現は後のトラブルの原因となります。
負担付遺贈について
特定遺贈には「負担付遺贈」という形態もあります。これは受遺者に対して、遺贈と引き換えに何らかの義務や条件を課すものです。
例えば「Aさんに自宅不動産を遺贈するが、毎年○○神社でお墓参りをすることを条件とする」「Bさんに預金1,000万円を遺贈するが、そのうち300万円を△△団体に寄付することを条件とする」などが負担付遺贈にあたります。
負担付遺贈の場合、負担の履行が困難になったり、受遺者が負担を履行しなかったりすると、遺贈が取り消される可能性があるため注意が必要です。
特定遺贈に関するよくある質問
Q1. 特定遺贈と遺産分割の関係はどうなりますか?
特定遺贈の対象となった財産は、遺産分割の対象から外れます。特定遺贈は遺言者の死亡と同時に効力が発生し、指定された財産について受遺者が権利を取得するためです。
ただし、実際の財産の引き渡しや名義変更などの手続きは必要となります。相続人は特定遺贈の履行義務を負うため、遺産分割協議では特定遺贈の内容を尊重して分割を行う必要があります。
Q2. 特定遺贈を受けた場合、相続税はかかりますか?
はい、特定遺贈を受けた場合でも相続税の対象となります。相続税法上、遺贈も相続と同様に扱われ、受遺者が取得した財産の価額に応じて相続税が課税されます。
ただし、受遺者が配偶者や法定相続人である場合は、相続税の配偶者控除や基礎控除などの適用を受けることができます。法定相続人以外の第三者が受遺者となる場合は、2割加算の対象となる点に注意が必要です。
Q3. 特定遺贈を拒否することはできますか?
はい、受遺者は特定遺贈を拒否(放棄)することができます。遺贈の放棄は、相続の放棄とは異なり、家庭裁判所での手続きは不要で、単に意思表示をするだけで効力が生じます。
遺贈の放棄をした場合、その財産は最初から遺贈がなかったものとして扱われ、相続財産に戻ります。遺贈が債務を伴う場合や、相続税の負担が大きい場合などに放棄を検討することがあります。
Q4. 遺言書がない場合でも特定遺贈はできますか?
いいえ、特定遺贈は必ず遺言によって行う必要があります。遺言書がなければ、法定相続分に従って相続財産が分配されることになります。
ただし、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議によって特定の財産を特定の人(相続人または第三者)に渡すことは可能です。この場合は「特定遺贈」ではなく「遺産分割」または「遺産分割後の譲渡」という扱いになります。
Q5. 特定遺贈の対象となった財産が遺言作成後になくなった場合はどうなりますか?
遺言作成後に特定遺贈の対象となった財産がなくなった場合(売却、滅失など)、原則としてその特定遺贈は効力を失います(民法第995条)。
例えば、「Aさんに○○銀行の定期預金1,000万円を遺贈する」という遺言があっても、遺言者が生前にその預金を解約していた場合、特定遺贈は効力を失います。代わりの財産を受遺者に渡す義務は発生しません。
まとめ
特定遺贈は、遺言によって特定の財産を特定の人に与える方法です。相続人はもちろん、法定相続人以外の第三者にも財産を残したい場合に有効な手段となります。
特定遺贈を行う際は、財産と受遺者を明確に特定することが重要です。あいまいな表現は後のトラブルの原因となります。また、法定相続人の遺留分を侵害する場合は遺留分侵害額請求の対象となる可能性がある点にも注意が必要です。
特定遺贈の受遺者は、遺贈された財産に対する権利を取得しますが、実際に財産を受け取るためには相続人からの引き渡しが必要です。場合によっては遺言執行者の選任も検討すべきでしょう。
遺贈を受けた財産には相続税が課税されるため、税金面での対策も重要です。特に法定相続人以外が受遺者となる場合は、2割加算の対象となる点に留意が必要です。
特定遺贈は財産を指定した人に確実に残すための有効な方法ですが、適切な知識と準備がなければ意図した通りの結果にならないこともあります。専門家のアドバイスを受けながら、遺言の作成を検討することをおすすめします。






