消極財産(しょうきょくざいさん)とは?
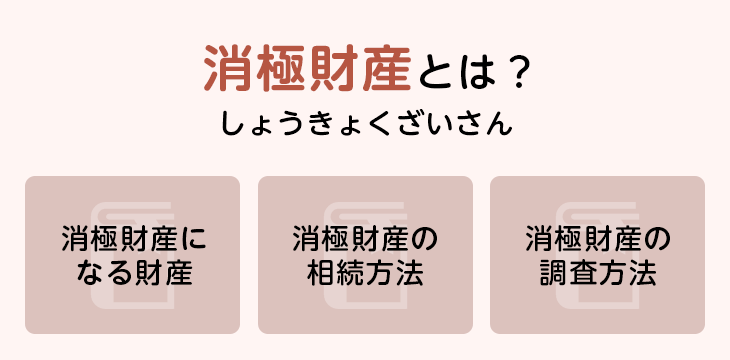
消極財産とは、被相続人(亡くなった方)が残した借金や債務などのマイナスの財産のことです。
相続では、プラスの財産(積極財産)だけでなく、このマイナスの財産も引き継ぐことになります。住宅ローンや事業資金の借入金、未払いの税金などが消極財産の代表的な例です。
消極財産とはどのような財産か
消極財産とは、簡単に言えば「借金」や「債務」など、マイナスの財産のことを指します。相続が発生すると、被相続人の財産はプラスとマイナスの両方が相続人に引き継がれます。プラスの財産を「積極財産」、マイナスの財産を「消極財産」と呼びます。
相続財産の総額を計算する際は、積極財産の合計から消極財産の合計を差し引いた金額が、実際に相続される純資産となります。消極財産が積極財産を上回る場合、相続財産はマイナスとなり、相続人にとって負担となる可能性があります。
| 相続財産の計算式 | 相続財産の純額 = 積極財産(プラスの財産)- 消極財産(マイナスの財産) |
|---|
この表は相続財産の純額の計算方法を示しています。積極財産から消極財産を差し引くことで、実際に相続される財産の総額が算出されます。
消極財産の具体例
消極財産には様々な種類があります。一般的な例として、以下のようなものが挙げられます。
- 住宅ローンの残債
- 事業資金の借入金
- カードローンやキャッシングの借入金
- 未払いの税金(所得税、固定資産税など)
- 未払いの公共料金や家賃
- 保証人としての保証債務
- 損害賠償責任
- 葬儀費用
上記のリストは代表的な消極財産の例です。被相続人の生前の借入状況や契約内容によって、相続する消極財産は異なります。特に事業を営んでいた方の場合、事業関連の負債が多額になることがあるため注意が必要です。
特に注意すべき消極財産
消極財産の中でも、特に注意が必要なものがあります。例えば、保証人になっていた場合の保証債務は、主債務者が返済不能になると突然発生する可能性があります。また、被相続人が経営者だった場合、会社の負債に個人保証をしていることもあります。
さらに、相続開始後に発覚する債務もあります。例えば、被相続人の隠れた借金や、生前に知られていなかった損害賠償責任などが後から判明するケースもあるため、慎重な調査が必要です。
| 隠れた消極財産の例 |
|
|---|
この表は、相続開始後に発覚する可能性のある「隠れた消極財産」の例を示しています。これらは公的な記録に残っていないことが多く、発見が困難な場合があります。
消極財産の相続方法
消極財産は、原則として相続人が法定相続分に応じて引き継ぎます。例えば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ずつ消極財産を相続することになります。
ただし、消極財産のみを相続放棄<することはできません。相続放棄をする場合は、積極財産と消極財産の両方を放棄することになります。また、相続人全員で遺産分割協議を行い、特定の相続人が消極財産を多く引き継ぐという取り決めをすることも可能です。
- 法定相続分による相続:法律で定められた割合に従って消極財産を分担
- 遺産分割協議による相続:相続人全員の合意によって消極財産の分担割合を決定
- 相続放棄:消極財産も積極財産もすべて放棄
- 限定承認:相続財産の範囲内でのみ債務を弁済
このリストは消極財産を相続する4つの方法を示しています。状況に応じて最適な選択をすることが重要です。特に消極財産が多い場合は、相続放棄や限定承認を検討する必要があります。
債権者への対応
消極財産を相続した場合、債権者(お金を貸している側)から返済を求められることになります。相続したことで返済義務が発生するため、債権者からの請求に対して適切に対応する必要があります。
債権者との交渉により、分割払いや減額の合意を得られる可能性もあります。特に多額の債務がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
消極財産と相続放棄
消極財産が積極財産を上回る場合、相続放棄を検討する価値があります。相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄する手続きです。
相続放棄をするためには、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。この期間を経過すると、原則として相続放棄はできなくなるため、注意が必要です。
相続放棄をした場合、その相続人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。そのため、消極財産に関する責任を負わなくなりますが、同時に積極財産も一切相続できなくなります。
| 相続放棄の流れ |
|
|---|
この表は相続放棄の一般的な手続きの流れを示しています。手続きには期限があるため、消極財産が多いと判明した場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
限定承認という選択肢
相続放棄のほかに、「限定承認」という選択肢もあります。限定承認とは、相続財産の範囲内でのみ債務を弁済する制度です。つまり、積極財産の総額を超える消極財産については、支払い義務を負わないというものです。
限定承認も相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。また、相続人全員が共同で申述しなければならないという制約があります。一人でも限定承認に同意しない相続人がいると、手続きを進めることができません。
消極財産の調査方法
相続が発生した際、消極財産の存在と金額を正確に把握することが重要です。以下に、消極財産を調査する主な方法を紹介します。
- 被相続人の通帳や契約書類の確認:生前の借入に関する書類を探し、確認する
- 債権者からの請求書の確認:相続開始後に届く請求書から債務を把握する
- 金融機関への照会:被相続人が取引していた銀行やカード会社に問い合わせる
- 信用情報機関への照会:個人信用情報に記録されている借入情報を確認する
- 税務署や市区町村への照会:未払いの税金がないか確認する
このリストは消極財産を調査する主な方法を示しています。調査は早めに行い、相続放棄や限定承認の検討に必要な情報を集めることが大切です。
特に事業を営んでいた方の場合、取引先や従業員からも情報を得ることが重要です。また、借金が見つかった場合は、その内容(借入日、金額、返済状況など)を詳細に確認しましょう。
よくある質問
Q1: 消極財産だけを相続放棄することはできますか?
いいえ、消極財産だけを選択的に相続放棄することはできません。相続放棄は、積極財産と消極財産の両方を放棄する手続きです。プラスの財産は欲しいけれどマイナスの財産は引き継ぎたくないという場合でも、法律上は選択的な放棄はできないとされています。
Q2: 相続後に新たな消極財産が見つかった場合はどうすればよいですか?
相続承認後に新たな消極財産が発見された場合でも、原則として債務の返済義務があります。ただし、相続開始を知った時点では債務の存在を知らず、その後に発覚した場合は、家庭裁判所に「特別縁故者の相続放棄」を申し立てることができる場合があります。早急に専門家に相談することをおすすめします。
Q3: 連帯保証人になっていた債務も消極財産として相続されますか?
はい、被相続人が連帯保証人になっていた債務も消極財産として相続されます。連帯保証債務は被相続人の死亡によって消滅せず、相続人に引き継がれます。主債務者が返済できない場合、相続人が保証債務の履行を求められる可能性があります。
Q4: 消極財産が多い場合、相続税は発生しますか?
消極財産が積極財産を上回る場合、相続税は発生しません。相続税は、積極財産から消極財産を差し引いた正味の遺産額に対して課税されます。マイナスになる場合は課税対象となる財産がないため、相続税は発生しません。
Q5: 相続放棄の期限を過ぎてしまった場合、どうすればよいですか?
原則として、相続開始を知った日から3ヶ月を過ぎると相続放棄はできません。ただし、「相続財産の全部または一部を処分した」「相続財産を隠匿した」などの事実がない場合で、かつ「相続放棄できることを知らなかった」「債務の存在を知らなかった」などの正当な理由があれば、期限を経過した後でも家庭裁判所に申立てができる場合があります。専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
消極財産とは、被相続人が残した借金や債務などのマイナスの財産のことです。住宅ローン、事業資金の借入金、未払いの税金などが代表的な例として挙げられます。相続では、積極財産(プラスの財産)だけでなく、消極財産も引き継ぐことになります。
消極財産の相続方法には、法定相続分による相続、遺産分割協議による相続、相続放棄、限定承認があります。特に消極財産が積極財産を上回る場合は、相続放棄や限定承認を検討する価値があります。
相続放棄や限定承認には期限があり、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。期限を過ぎると原則として手続きができなくなるため、消極財産の存在が疑われる場合は、早めに調査を行い、専門家に相談することが重要です。
消極財産の調査は、被相続人の通帳や契約書類の確認、債権者からの請求書の確認、金融機関への照会などの方法で行います。調査は徹底的に行い、隠れた債務がないか確認することが大切です。
相続は複雑な手続きであり、特に消極財産が絡む場合は専門的な知識が必要になります。不安や疑問がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。






