相続放棄(そうぞくほうき)とは?
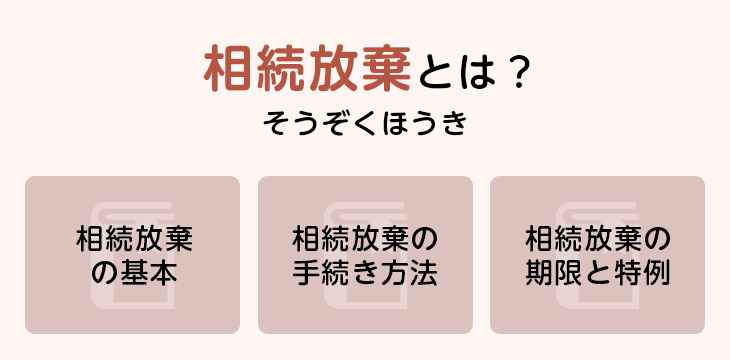
相続放棄とは、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述をすることで、初めから相続人ではなかったことになる制度です。被相続人の借金や債務が多く、プラスの財産より負債が多い場合に選択されることが多いです。
相続放棄をすると、プラスの財産(積極財産)もマイナスの財産(消極財産)も一切相続せず、初めから相続人ではなかったものとみなされます。これにより借金などの負債を引き継ぐことがなくなります。
相続放棄の基本
相続放棄は民法上の制度で、被相続人(亡くなった方)の財産を相続したくない場合に行う手続きです。被相続人に多額の借金がある場合や、相続財産の状況が不明確な場合に選択されることが多いです。
相続放棄をすると「初めから相続人ではなかった」という法的効果が生じ、相続人としての権利も義務も一切発生しなくなります。そのため、プラスの財産(不動産や預貯金など)もマイナスの財産(借金や債務など)も一切引き継がないことになります。
| 相続放棄の特徴 | 相続開始後、3か月以内に家庭裁判所への申述が必要 |
|---|---|
| 効果 |
|
相続放棄の判断は、被相続人の財産状況を十分に把握した上で行うことが重要です。特に借金や債務が多い場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄の効果
相続放棄をすると、法律上「初めから相続人ではなかった」とみなされます。これにより、相続人としての権利と義務の両方が消滅します。
- プラスの財産(不動産、預貯金、有価証券など)を相続できなくなる
- マイナスの財産(借金、未払い税金など)を引き継がなくてよくなる
- 被相続人の葬儀費用や埋葬費用の支払い義務がなくなる
- 相続人としての地位が完全に失われる
上記のリストは相続放棄の主な効果を示しています。相続放棄は一部の財産だけを選択して放棄することはできず、すべての相続財産について効果が及ぶ点に注意が必要です。
また、相続放棄をした人の子どもにも相続権が移らないため、代襲相続も発生しません。相続放棄者が亡くなった場合でも、その子どもが代わりに相続人になることはありません。
相続放棄と次順位相続人への影響
相続放棄をすると、次順位の相続人が繰り上がって相続人となります。例えば、子どもが相続放棄をした場合、その子どもの子(被相続人の孫)ではなく、被相続人の他の子どもや配偶者が相続することになります。
すべての第一順位相続人が相続放棄をした場合は、第二順位相続人(被相続人の親)に相続権が移ります。第二順位までの相続人全員が放棄した場合は、第三順位相続人(被相続人の兄弟姉妹)に相続権が移ります。
相続放棄の手続き方法
相続放棄の手続きは、家庭裁判所への申述によって行います。手続きの流れは以下のとおりです。
- 相続放棄申述書の作成:必要事項を記入した申述書を準備する
- 必要書類の収集:戸籍謄本、住民票、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍などを用意する
- 家庭裁判所への申述:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書と必要書類を提出する
- 申述手数料の納付:収入印紙(800円)を納付する
- 審査:裁判所が申述内容を審査する
- 相続放棄申述受理通知書の受領:審査の結果、問題がなければ受理通知書が発行される
上記の手続きの流れは一般的なものであり、実際の手続きは各家庭裁判所によって若干異なる場合があります。また、必要書類も状況によって異なることがあるため、事前に管轄の家庭裁判所に確認することをおすすめします。
| 必要書類 |
|
|---|---|
| 申述先 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 費用 | 申述手数料800円(収入印紙)、郵送料等の実費 |
この表は相続放棄の手続きに必要な書類と申述先、費用についてまとめたものです。書類の取得には別途費用がかかりますので、あらかじめ予算を確保しておくことをおすすめします。
相続放棄の期限と特例
相続放棄の期限は原則として、相続の開始(被相続人の死亡)があったことを知った時から3か月以内とされています。この期間を熟慮期間といいます。
ただし、相続財産の状況が不明確で判断が難しい場合には、家庭裁判所に申立てをすることで熟慮期間を伸長(延長)することが可能です。これにより、より慎重に相続放棄の判断をすることができます。
相続放棄の特例(民法915条の特則)
熟慮期間(3か月)を過ぎた場合でも、以下の条件を満たせば例外的に相続放棄が認められることがあります。
- 相続人が相続財産の全部または一部を処分していないこと
- 相続財産の存在を知らなかったこと
- 債務の存在を知らなかったこと
- 相続財産が存在しないと信じていたこと
上記の条件に該当する場合、家庭裁判所による「特別な事情」の認定を受けることで、期限後でも相続放棄が認められる可能性があります。ただし、この特例の適用は裁判所の判断によるため、確実ではありません。
期限を過ぎている場合は、早急に弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄と限定承認の違い
相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの選択肢があります。特に「限定承認」と「相続放棄」は債務への対応という点で似ていますが、大きな違いがあります。
| 相続放棄 | 限定承認 | |
|---|---|---|
| 効果 | 初めから相続人ではなかったものとみなされる | プラスの財産の範囲内で債務を返済する義務を負う |
| 財産の取得 | 一切の財産(プラス・マイナス)を相続しない | 債務返済後に残ったプラス財産を取得できる |
| 手続き | 家庭裁判所への申述(個人でも可能) | 家庭裁判所への申述(共同相続人全員で行う必要あり) |
| 期限 | 相続を知ってから3か月以内 | 相続を知ってから3か月以内 |
この表は相続放棄と限定承認の主な違いを比較したものです。限定承認は、プラスの財産と債務の額が不明確な場合や、プラスの財産の方が多いと思われる場合に選択することが有利です。
一方、相続放棄は債務が多い、または財産状況が全く分からない場合に選択されることが多いです。また、限定承認は共同相続人全員で行う必要があるのに対し、相続放棄は個人単位で行えるという違いもあります。
よくある質問
Q1. 相続放棄をした後に撤回はできますか?
原則として、相続放棄が家庭裁判所に受理された後は撤回することはできません。相続放棄は「初めから相続人ではなかった」という強い法的効果を生じるため、一度手続きが完了すると変更できません。
ただし、相続放棄の申述が詐欺や強迫によって行われた場合など、特殊な事情がある場合には取り消しが認められることがあります。これは非常に例外的なケースです。
Q2. 相続放棄をするといつからその効果が発生しますか?
相続放棄の効果は、家庭裁判所に申述が受理された時点ではなく、被相続人が亡くなった時点(相続開始時)にさかのぼって発生します。これにより、初めから相続人ではなかったという法的効果が生じます。
そのため、相続放棄の申述が受理される前に相続財産を処分したり、債務の支払いをしたりした場合でも、原則としてそれらの行為は無効となる可能性があります。
Q3. 相続放棄をした場合、誰が相続人になりますか?
相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったものとみなされるため、その人の子どもが代わりに相続人になるわけではありません。相続放棄者以外の同順位の相続人が相続することになります。
同順位の相続人全員が相続放棄をした場合は、次順位の相続人(第一順位が全員放棄なら第二順位、第二順位も全員放棄なら第三順位)に相続権が移ります。
Q4. 相続放棄の手続きは自分でできますか?
相続放棄の手続きは自分で行うことも可能です。必要書類を揃えて家庭裁判所に申述をすれば、専門家に依頼しなくても手続きを完了させることができます。
ただし、相続関係が複雑な場合や、必要書類の収集が難しい場合には、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。また、相続放棄の判断自体についても専門家のアドバイスを受けると安心です。
Q5. 相続放棄をすると葬儀費用も支払わなくてよいですか?
相続放棄をすると、法律上は初めから相続人ではなかったことになるため、葬儀費用や埋葬費用の支払い義務もなくなります。ただし、実際には葬儀を執り行った後に相続放棄の手続きをするケースが多いです。
葬儀費用を立て替えた後に相続放棄をした場合、その費用を相続財産から回収することが難しくなる可能性がありますので注意が必要です。このような場合は、他の相続人との話し合いで解決を図ることが一般的です。
相続放棄のまとめ
相続放棄は、被相続人の財産を一切相続したくない場合に選択できる重要な制度です。被相続人の借金や債務が多い場合に、相続人が自己の財産で返済義務を負わないようにするための有効な手段となります。
相続放棄の手続きは、相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述することで行います。この期間を過ぎると原則として相続放棄はできなくなりますので、早めの判断と行動が重要です。
相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続せず、初めから相続人ではなかったものとみなされます。一度相続放棄の手続きが完了すると、原則として撤回はできません。
相続放棄を検討する際には、被相続人の財産状況を可能な限り調査し、プラスの財産とマイナスの財産のバランスを見極めることが大切です。不明な点がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
また、相続放棄と限定承認の違いを理解し、自分の状況に合った選択をすることも重要です。限定承認はプラスの財産の範囲内で債務を返済する制度であり、相続放棄とは異なる効果を持ちます。






