成年後見人制度(せいねんこうけんにんせいど)とは?
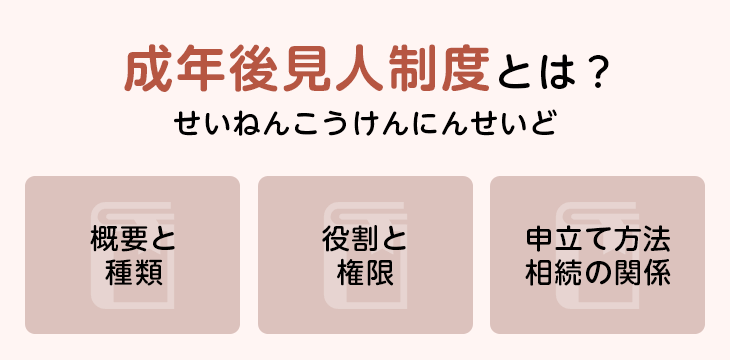
成年後見人制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な方を法律的に保護し、支援するための制度です。
本人の財産管理や契約行為などをサポートする後見人等が選任され、本人の権利や財産を守ります。
成年後見人制度の概要
成年後見人制度は、2000年4月に施行された民法の改正によって導入された制度です。従来の禁治産・準禁治産制度に代わるものとして、ノーマライゼーションや自己決定権の尊重という理念に基づいて創設されました。
この制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な方々の権利を守るために、家庭裁判所が選任した成年後見人等が、本人に代わって財産管理や契約などの法律行為を行います。
| 制度の対象者 | 認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が不十分な成年者 |
|---|---|
| 制度の目的 |
|
上記の表は成年後見人制度の対象者と主な目的をまとめたものです。判断能力が不十分な方の権利を守りながら、できる限り本人の意思を尊重することを目指しています。
成年後見人制度の種類
成年後見人制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの種類があります。さらに法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて3つの類型に分かれています。
法定後見制度
法定後見制度は、すでに判断能力が不十分になった方を対象とした制度で、家庭裁判所が成年後見人等を選任します。本人の判断能力の程度によって、以下の3つの類型に分かれています。
- 後見:判断能力が常に欠けている状態の方
- 保佐:判断能力が著しく不十分な方
- 補助:判断能力が不十分な方
上記のリストは、法定後見制度の3つの類型とその対象となる方の判断能力の状態を示しています。判断能力の程度に応じて適切な支援が受けられるように設計されています。
任意後見制度
任意後見制度は、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ自分で後見人となる人(任意後見人)と、支援してもらう内容について契約(任意後見契約)を結んでおく制度です。
この契約は公正証書で作成する必要があり、本人の判断能力が低下した際に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで効力が生じます。
| 法定後見制度 | すでに判断能力が不十分になった方が対象。家庭裁判所が後見人等を選任 |
|---|---|
| 任意後見制度 | 判断能力があるうちに、将来に備えて自分で後見人と契約を結んでおく制度 |
上記の表は、法定後見制度と任意後見制度の主な違いを示しています。自分の将来について準備をしておきたい方は、任意後見制度の活用を検討するとよいでしょう。
成年後見人の役割と権限
成年後見人には、本人の生活や財産を守るために様々な役割と権限が与えられています。主な役割と権限は以下のとおりです。
財産管理
成年後見人は、本人の預貯金や不動産などの財産を管理し、適切に運用する役割があります。定期的な収支の管理や、税金・公共料金などの支払いも行います。
また、本人の財産目録を作成し、家庭裁判所に報告する義務もあります。財産管理は透明性を持って行われる必要があります。
身上監護(契約等の法律行為)
成年後見人は、本人の生活に関わる契約を行う権限があります。介護サービスの利用契約、施設入所の契約、医療契約などが含まれます。
ただし、身上監護は法律行為に限られており、直接的な介護行為や看護行為などは含まれません。あくまでも契約などの法律行為を通じて本人の生活をサポートします。
- 財産管理:預貯金・不動産などの管理、収支の管理、税金や公共料金の支払い
- 身上監護:介護サービス・施設入所・医療などの契約
- 取消権:本人が不利益な契約を結んだ場合の取消し
- 代理権:本人に代わって契約などの法律行為を行う
上記のリストは成年後見人の主な役割と権限を示しています。成年後見人は、常に本人の意思を尊重し、本人の利益を第一に考えて職務を遂行する必要があります。
成年後見人制度の申立て方法
成年後見人制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。申立ての流れは以下のとおりです。
申立て可能な人
法定後見制度の申立ては、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市区町村長などが行うことができます。任意後見制度の場合は、任意後見契約が結ばれた後、本人の判断能力が低下した時点で、本人、配偶者、親族、任意後見受任者などが家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。
申立て手続きの流れ
- 申立て準備:必要書類の収集(診断書、戸籍謄本など)
- 申立て書類の作成:申立書、財産目録などの作成
- 家庭裁判所への申立て:書類提出と申立て手数料の納付
- 家庭裁判所による調査:本人の判断能力の鑑定、親族への照会など
- 審判:後見人等の選任
上記は成年後見人制度の申立て手続きの基本的な流れです。地域や状況によって必要書類や手続きが異なる場合があるため、事前に最寄りの家庭裁判所に確認することをおすすめします。
| 必要書類 |
|
|---|---|
| 申立て費用 |
|
上記の表は、成年後見人制度の申立てに必要な主な書類と費用の目安です。実際の費用は地域や事案によって異なるため、事前に確認が必要です。
成年後見人制度と相続の関係
成年後見人制度は相続とも密接な関係があります。特に、被後見人(成年後見制度を利用している本人)が相続人となる場合や、被後見人が亡くなった場合の対応について理解しておくことが重要です。
被後見人が相続人となる場合
被後見人が他の方の相続人となった場合、成年後見人は被後見人に代わって相続の手続きを行います。相続の承認・放棄の判断、遺産分割協議への参加などを行います。
ただし、相続放棄や特定の遺産分割案に同意する場合などには、家庭裁判所の許可が必要になることがあります。成年後見人は被後見人の利益を最優先に考えて判断する必要があります。
被後見人が亡くなった場合
被後見人が亡くなると、成年後見人の職務は当然に終了します。成年後見人は、被後見人の死亡後2ヶ月以内に、家庭裁判所に対して終了報告書を提出する必要があります。
また、被後見人の相続人に対して、管理していた財産を引き継ぐ必要があります。この際、成年後見人は自分が行った財産管理の内容について、相続人に対して報告する義務があります。
| 被後見人が相続人となる場合 |
|
|---|---|
| 被後見人が亡くなった場合 |
|
上記の表は、成年後見人制度と相続が関わる主なケースとその対応についてまとめたものです。成年後見人は、相続に関連する手続きも適切に行う必要があります。
よくある質問
Q1. 成年後見人になれる人の条件はありますか?
成年後見人になれる人に特別な資格は必要ありませんが、本人の利益を考えて適切な判断ができる人が選ばれます。親族が選ばれることもありますが、専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士など)が選任されることも増えています。
ただし、本人と利害関係がある人や、破産者、未成年者などは成年後見人になれません。最終的には家庭裁判所が本人にとって最適な人を選任します。
Q2. 成年後見人制度を利用するとどのくらい費用がかかりますか?
成年後見人制度を利用する際の費用は、申立て費用と後見人への報酬に分かれます。申立て費用は、収入印紙代(800円〜4,000円)、郵便切手代(数千円程度)、鑑定費用(必要な場合は5万円〜10万円程度)などです。
後見人への報酬は、家庭裁判所が決定します。一般的に月額2万円〜3万円程度ですが、本人の財産状況や後見事務の難易度によって変動します。専門職が後見人になる場合は、報酬が高くなる傾向があります。
Q3. 任意後見制度と法定後見制度はどちらを選ぶべきですか?
判断能力があるうちに将来に備えたい場合は、任意後見制度がおすすめです。任意後見制度では、自分で後見人を選び、支援してもらう内容を決めることができるため、自分の意思をより反映させることができます。
一方、すでに判断能力が低下している場合は法定後見制度を利用することになります。どちらが良いかは個人の状況によって異なるため、専門家に相談することをおすすめします。
Q4. 成年後見人は被後見人の借金を返済する義務がありますか?
成年後見人は、被後見人の財産から被後見人の債務を支払う義務はありますが、自分自身の財産から被後見人の債務を支払う義務はありません。成年後見人は、被後見人の財産を適切に管理し、借金がある場合はその財産から返済する役割があります。
ただし、被後見人の財産が不足している場合、成年後見人は債権者と交渉したり、必要に応じて債務整理を検討したりする必要があります。
Q5. 成年後見人制度を終了させることはできますか?
法定後見制度は、原則として被後見人が亡くなるか、判断能力が回復しない限り継続します。判断能力が回復した場合は、本人や親族などが家庭裁判所に後見開始の審判の取消しを申し立てることができます。
任意後見制度の場合は、本人の判断能力があれば、任意後見契約を解除することができます。ただし、任意後見監督人が選任された後は、家庭裁判所の許可なしに契約を解除することはできません。
まとめ
成年後見人制度は、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な方の権利や財産を守るための重要な制度です。法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、本人の状況に応じて適切な制度を選択することができます。
成年後見人は、本人の財産管理や契約などの法律行為を代行し、本人の生活を法律面からサポートします。成年後見人になるには特別な資格は必要ありませんが、家庭裁判所が本人にとって最適な人を選任します。
成年後見人制度は相続とも密接に関連しており、被後見人が相続人となる場合や被後見人が亡くなった場合には、特定の手続きが必要になります。制度の利用には一定の費用がかかりますが、本人の権利を守るための重要な投資と考えることができます。
判断能力があるうちに任意後見契約を結んでおくことで、将来に備えることができます。自分や家族の将来に不安がある方は、成年後見人制度の活用を検討し、専門家に相談することをおすすめします。






