二次相続(にじそうぞく)とは?
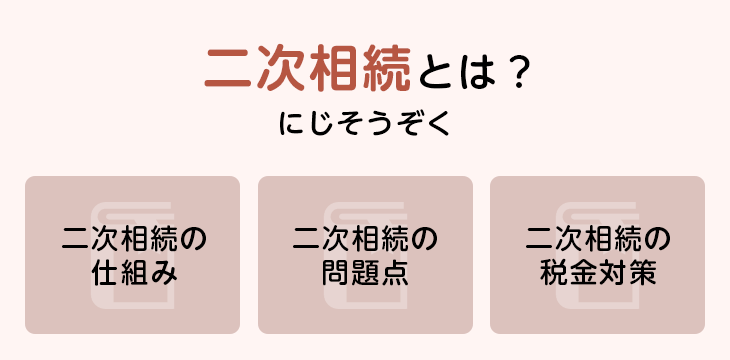
二次相続とは、一次相続後に相続人となった方がさらに亡くなり、その財産が次の相続人に引き継がれることを指します。例えば、夫が亡くなり妻が相続した後(一次相続)、妻が亡くなって子どもが相続する(二次相続)というケースが代表的です。
二次相続は相続税の負担が大きくなりやすく、事前の対策が重要となります。特に相続税の基礎控除が一次相続と二次相続でそれぞれ適用されるため、全体としての相続税負担を考慮した計画が必要です。
二次相続の基本的な仕組み
一般的な二次相続の流れは、まず配偶者(多くの場合は妻)が夫の財産を相続し、その後妻が亡くなった際に子どもたちがその財産を相続するというものです。この二段階の相続が「二次相続」と呼ばれています。
- 一次相続:夫が亡くなり、妻が夫の財産を相続
- 二次相続:妻が亡くなり、子どもたちが母親の財産(一次相続で取得した財産を含む)を相続
上記のような二段階の相続プロセスにおいて、それぞれの段階で相続税が計算され、課税されることになります。
| 相続税の基礎控除 | 一次相続と二次相続でそれぞれ「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数」の基礎控除が適用されます。 |
|---|---|
| 配偶者の税額軽減特例 |
|
上記の表は相続税計算における重要な点を示しています。二次相続では配偶者の税額軽減を利用できないため、相続税の負担が一次相続よりも大きくなることが多いです。
二次相続で起こりやすい問題点
二次相続では以下のような問題が発生しやすく、事前の対策が必要となります。
- 相続税負担の増大:配偶者の税額軽減が使えなくなるため税負担が増加
- 流動性の問題:不動産などの換金しにくい財産が多いと相続税の納付が困難になる
- 相続人間の争い:財産分割で子どもたち間の争いが発生するリスク
- 評価額の上昇:長期間経過により不動産などの評価額が上昇し、税負担が増える可能性
二次相続における最大の問題は、一次相続で適用された配偶者の税額軽減措置が二次相続では適用されないことです。このため、実質的な相続税負担が大きくなりやすくなります。
相続税負担の具体例
| 一次相続時の状況 | 夫の財産2億円を妻が全額相続した場合、配偶者の税額軽減により相続税はゼロになることも |
|---|---|
| 二次相続時の状況 | 妻の財産2億円を子ども2人で相続する場合、約2,000万円程度の相続税が発生する可能性 |
上記の例は、二次相続で相続税負担が大きくなる典型的なケースを示しています。一次相続では相続税がゼロでも、二次相続では高額な相続税が発生する可能性があります。
二次相続の税金対策
二次相続による相続税負担を軽減するための主な対策には、以下のようなものがあります。
- 一次相続時の財産分散:配偶者だけでなく子どもにも一部財産を相続させる
- 生前贈与の活用:毎年の贈与税の基礎控除(110万円)を活用した計画的な贈与
- 相続時精算課税制度の利用:子や孫への生前贈与で2,500万円までの特別控除を利用
- 不動産の評価減対策:小規模宅地等の特例などを活用した不動産評価額の圧縮
- 生命保険の活用:死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)を活用
上記の対策は、二次相続における相続税負担を軽減するための代表的な方法です。特に一次相続の段階から計画的に財産を分散させることが重要となります。
一次相続での財産分散の効果
| 配偶者に全額相続 | 二次相続時に相続財産がまとまって相続税の累進課税で税率が高くなりやすい |
|---|---|
| 配偶者と子に分散 |
|
上記の表は、一次相続での財産分散の効果を示しています。配偶者に全額相続させるのではなく、配偶者の税額軽減の範囲内で最大限活用しつつ、子にも財産を分散させることで、二次相続時の相続税負担を軽減できます。
二次相続対策の具体例
二次相続対策を具体的な事例でみていきましょう。
事例:総資産3億円の場合の二次相続対策
| 対策なしの場合 | 一次相続で妻が3億円全額相続→二次相続で子2人が相続→約4,000万円の相続税 |
|---|---|
| 対策ありの場合 |
|
上記の事例は、一次相続で適切に財産分散を行うことで、総相続税額を大幅に軽減できることを示しています。配偶者の税額軽減を最大限活用しつつ、子にも財産を分散させることが効果的です。
生前贈与を活用した対策
二次相続対策として生前贈与を活用する方法もあります。
- 暦年贈与:毎年110万円の基礎控除を活用して子や孫に贈与
- 相続時精算課税制度:子や孫に対して2,500万円まで贈与税がかからない特別控除を利用
- 教育資金贈与:孫などへの教育資金として1,500万円まで非課税で贈与可能
- 結婚・子育て資金贈与:子や孫への結婚・子育て資金として1,000万円まで非課税で贈与可能
上記の生前贈与の方法を計画的に活用することで、二次相続時の相続財産を減らし、相続税負担を軽減することができます。特に長期間にわたって計画的に行うことが効果的です。
よくある質問
Q1: 二次相続とは具体的にどのような状況を指しますか?
二次相続とは、一次相続(例えば夫が亡くなり妻が相続した場合)の後に、その相続人(妻)も亡くなり、さらに次の相続人(子どもなど)に財産が引き継がれる状況を指します。特に夫婦間での相続の後、子どもへの相続という流れが一般的です。
Q2: 二次相続で税金負担が大きくなるのはなぜですか?
二次相続で税金負担が大きくなる主な理由は、一次相続で適用された「配偶者の税額軽減」が二次相続では適用されないためです。また、相続財産が一人(配偶者)に集中することで、相続税の累進課税の影響で税率が高くなりやすくなります。
Q3: 二次相続対策はいつから始めるべきですか?
二次相続対策は、できるだけ早く、理想的には夫婦ともに健在なうちから始めるべきです。特に生前贈与や財産分散などの対策は、長期間にわたって計画的に行うことで効果が大きくなります。一次相続が発生してからでも遅くはありませんが、選択肢は限られます。
Q4: 二次相続対策で最も効果的な方法は何ですか?
二次相続対策で最も効果的な方法は、一次相続の段階で配偶者に財産を集中させすぎないことです。配偶者の税額軽減は最大限活用しつつも、子どもにも適切に財産を分散させることで、二次相続時の相続税負担を軽減できます。また、計画的な生前贈与も効果的です。
Q5: 相続税の申告は二次相続でも必要ですか?
はい、二次相続でも相続税の申告は必要です。相続開始(被相続人の死亡)から10ヶ月以内に申告・納付する必要があります。一次相続と二次相続はそれぞれ別の相続として扱われ、それぞれで相続税の計算と申告が必要となります。
まとめ
二次相続とは、一次相続(例えば夫から妻への相続)の後に、さらに次の相続(妻から子どもへの相続)が発生することを指します。二次相続では配偶者の税額軽減が適用されないため、相続税負担が大きくなりやすいという特徴があります。
二次相続対策の基本は、一次相続の段階から計画的に財産を分散させることです。配偶者の税額軽減を最大限活用しつつも、子どもにも適切に財産を相続させることで、二次相続時の相続税負担を軽減できます。
また、生前贈与の活用も効果的な対策となります。暦年贈与や相続時精算課税制度、教育資金贈与などの制度を活用し、計画的に財産を移転していくことで、二次相続時の相続財産を減らし、相続税負担を軽減することができます。
相続対策は早めに始めることが重要です。特に二次相続を見据えた対策は、夫婦ともに健在なうちから始めることで、より効果的な対策が可能となります。専門家に相談しながら、ご家族の状況に合った最適な対策を検討することをおすすめします。






