寄与分(きよぶん)とは?
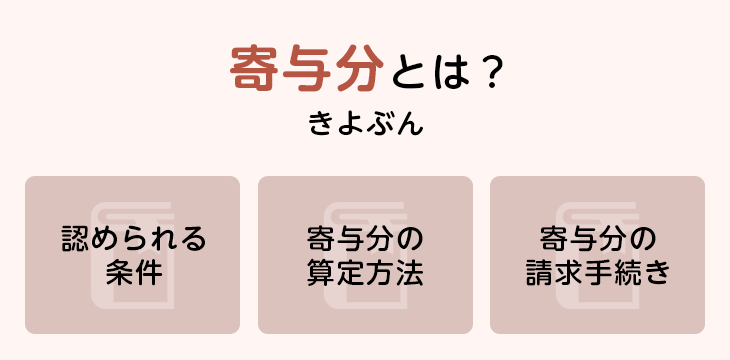
寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別に貢献した相続人が、法定相続分に加えて受け取ることができる追加の相続分のことです。民法第904条の2に規定されており、相続人の特別な貢献に対する公平な評価を目的としています。
たとえば、長年にわたり被相続人の介護をした相続人や、被相続人の事業を手伝って財産形成に貢献した相続人などが、寄与分を主張できる可能性があります。
寄与分の基本的な考え方
相続では原則として、法定相続分に従って遺産を分配します。しかし、被相続人の財産形成や維持に特別に貢献した相続人がいる場合、その貢献度に応じて追加の相続分(寄与分)を与えることで、公平な遺産分割を実現するという考え方です。
寄与分は、昭和55年の民法改正によって導入された制度です。それまでは、たとえ大きな貢献をした相続人がいても、法定相続分通りに分割するのが原則でした。
この制度により、特に被相続人の介護や事業の手伝いなどで貢献した相続人の努力が正当に評価されるようになりました。
| 寄与分制度の目的 | 相続人間の実質的公平を図り、被相続人の財産維持・増加に特別に寄与した相続人の貢献を適切に評価すること |
|---|---|
| 法的根拠 | 民法第904条の2(特別の寄与) |
この表は寄与分制度の基本的な目的と法的根拠を示しています。実質的な公平性を確保するための重要な制度であることがわかります。
寄与分が認められる条件
寄与分が認められるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。単に被相続人の面倒を見ていただけでは、寄与分として認められない場合が多いです。
- 相続人であること(相続人以外は特別寄与料の制度で対応)
- 被相続人の財産の維持・増加に特別な寄与があること
- 無償または著しく低い対価での貢献であること
- 一般的な親族間の助け合いの範囲を超えること
- 被相続人の生前における意思に反しないこと
上記のリストは寄与分が認められるための主な条件です。特に「特別な寄与」と「一般的な親族間の助け合いの範囲を超える」という点が重要なポイントになります。
「特別な寄与」とは
「特別な寄与」とは、単なる日常的な手伝いや世話ではなく、長期間にわたる献身的な介護や、事業への積極的な参加など、通常の親族間の援助の範囲を超える貢献を指します。
たとえば、自分の生活や仕事を犠牲にして、何年もの間、要介護状態の被相続人を献身的に介護したケースなどが該当します。
また、被相続人の事業に無償または低賃金で従事し、その事業の発展に大きく寄与したようなケースも特別な寄与として認められる可能性があります。
寄与分の具体的な事例
寄与分が認められるかどうかは、その貢献の内容や程度によって個別に判断されます。以下に、寄与分が認められやすい典型的な事例と、認められにくい事例を紹介します。
| 認められやすい事例 |
|
|---|
| 認められにくい事例 |
|
|---|
この表は寄与分が認められやすい事例と認められにくい事例を比較しています。寄与の程度や期間、無償性などが重要な判断基準となることがわかります。
裁判例からみる寄与分
実際の裁判例では、10年以上の長期介護で寄与分として遺産の10〜20%程度が認められたケースや、家業の農業を手伝い収益増加に貢献したことで15%程度の寄与分が認められたケースなどがあります。
ただし、寄与分の評価は事例ごとに異なり、貢献の内容や期間、被相続人の財産状況などを総合的に考慮して判断されます。
寄与分の算定方法
寄与分の具体的な金額や割合は、法律で明確に定められていません。相続人間の話し合いや家庭裁判所の審判によって個別に決定されます。
一般的には、以下のような要素を考慮して総合的に判断されます。
- 寄与の内容:どのような貢献をしたか(介護、事業参加、金銭的援助など)
- 寄与の期間:どれくらいの期間続いたか(長期間ほど評価が高い)
- 寄与の程度:どれだけ献身的に行ったか(自己犠牲の度合いなど)
- 財産への影響:被相続人の財産維持・増加にどれだけ貢献したか
- 他の相続人との比較:他の相続人も同様の貢献をしていないか
このリストは寄与分を算定する際に考慮される主な要素です。これらの要素を総合的に評価して、寄与分の金額や割合が決定されます。
寄与分の算定例
たとえば、遺産総額が5,000万円で、長男が10年間にわたり被相続人を献身的に介護したケースを考えてみましょう。
| 相続人構成 | 長男、次男、長女の3人(法定相続分は各1/3) |
|---|---|
| 寄与の内容 | 長男が10年間、仕事を調整しながら被相続人を献身的に介護 |
| 寄与分の評価 | 遺産総額の15%(750万円)を寄与分として認定 |
| 最終的な分配 |
|
この表は寄与分を考慮した相続分の算定例です。長男の介護という特別な寄与が評価され、法定相続分に加えて寄与分が認められています。
寄与分の請求手続き
寄与分を主張するためには、以下の手続きを踏む必要があります。寄与分は自動的に認められるものではなく、相続人自身が積極的に主張する必要があります。
- 遺産分割協議の場で寄与分を主張:まずは相続人間の話し合いで解決を試みます
- 寄与の事実と内容を証明する資料の準備:介護記録、医療費の領収書、事業への貢献を示す資料など
- 合意が得られない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て
- 調停でも解決しない場合は、遺産分割審判へ移行
- 審判でも寄与分の主張・立証を行う
このリストは寄与分を請求するための一般的な手続きの流れです。早い段階から証拠資料を収集・保管しておくことが重要です。
証拠の重要性
寄与分の主張において、その寄与の事実を証明することが非常に重要です。特に家庭裁判所での手続きでは、客観的な証拠が求められます。
- 介護日誌や医療機関の記録
- 介護サービスの利用状況がわかる資料
- 医療費や介護費用の領収書
- 被相続人の事業に関わっていたことを示す資料
- 金銭的支援を行った場合の振込記録や領収書
- 第三者(医師、ヘルパー、近隣住民など)の証言
このリストは寄与分を証明するために役立つ証拠の例です。日頃から記録をつけておくなど、事前の準備が大切です。
よくある質問
Q1. 親の介護をしていましたが、どのくらいの期間や内容であれば寄与分として認められますか?
一般的には、数年以上の長期間にわたる献身的な介護が必要です。特に、自分の仕事や生活を犠牲にして行った場合や、介護の負担が重い場合(認知症や寝たきりの介護など)は認められやすいでしょう。
ただし、週末だけの訪問介護や、介護サービスを十分に利用していた場合などは、通常の親族間の援助の範囲内とみなされ、寄与分として認められにくい傾向があります。
Q2. 相続人ではない嫁(息子の妻)が介護していた場合、寄与分は認められますか?
寄与分は相続人のみが主張できる制度です。嫁(息子の妻)は相続人ではないため、直接寄与分を主張することはできません。
ただし、平成30年の民法改正により「特別寄与料」の制度が創設され、相続人以外の親族(嫁や婿など)が被相続人に特別な貢献をした場合に、相続人に対して金銭の支払いを請求できるようになりました。
Q3. 親の事業を手伝っていましたが、給料をもらっていました。この場合も寄与分は認められますか?
相応の給料をもらっていた場合は、すでに労働の対価を受け取っているとみなされ、寄与分は認められにくくなります。
ただし、市場相場よりも著しく低い給料で長期間働き、事業の発展に大きく貢献した場合などは、その差額分について寄与分が認められる可能性があります。
Q4. 寄与分は遺言で否定することができますか?
遺言で「寄与分を認めない」と明記することはできますが、その効力については議論があります。裁判所は個別の事案に応じて、遺言の内容と寄与の事実を総合的に判断します。
特に著しく不公平な結果となる場合には、遺言の記載にかかわらず寄与分が認められるケースもあります。
Q5. 寄与分の請求には期限がありますか?
寄与分の請求に明確な期限はありませんが、遺産分割協議または遺産分割調停・審判の中で主張する必要があります。
遺産分割が終了した後に寄与分を主張することは困難です。また、相続開始から長期間が経過すると、証拠の収集も難しくなるため、早めに手続きを進めることをおすすめします。
まとめ
寄与分は、被相続人の財産の維持や増加に特別に貢献した相続人が、法定相続分に加えて受け取ることができる追加の相続分です。公平な遺産分割を実現するための重要な制度といえます。
寄与分が認められるためには、単なる日常的な世話ではなく、長期間にわたる献身的な介護や、事業への積極的な参加など、通常の親族間の援助の範囲を超える「特別な貢献」が必要です。
寄与分の具体的な金額や割合は法律で明確に定められておらず、相続人間の話し合いや家庭裁判所の審判によって個別に決定されます。一般的に、寄与の内容、期間、程度、財産への影響などを総合的に考慮して判断されます。
寄与分を主張するためには、遺産分割協議の場で積極的に主張し、寄与の事実を証明する資料を準備することが重要です。合意が得られない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
相続において自分の貢献が正当に評価されるよう、日頃から介護記録や支出の証拠を残しておくなど、事前の準備が大切です。弁護士、司法書士などの専門家に相談しながら手続きを進めることもおすすめします。






