自筆証書遺言書保管制度(じひつしょうしょゆいごんしょほかんせいど)とは?
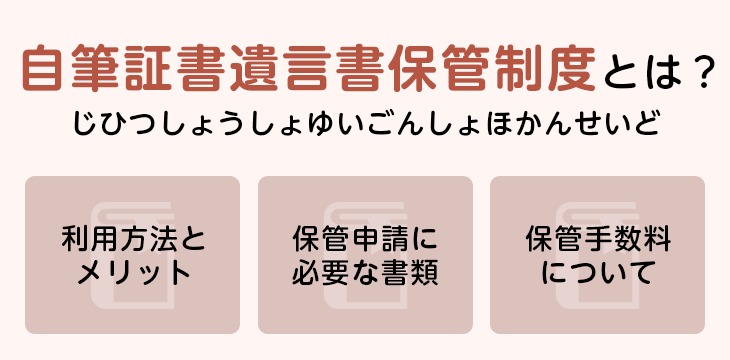
自筆証書遺言書保管制度とは、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度です。2020年7月10日からスタートした比較的新しい制度で、自筆証書遺言の紛失や改ざんなどのリスクを軽減し、相続手続きをスムーズに進めることができます。
従来の自筆証書遺言は自宅で保管することが多く、紛失や相続人による破棄、偽造などのリスクがありました。この制度を利用することで、そうしたリスクを回避し、遺言の内容を確実に実現することができるようになりました。
自筆証書遺言書保管制度のメリット
自筆証書遺言書保管制度には、遺言を残す方にとっても相続人にとっても多くのメリットがあります。この制度を利用することで、相続トラブルを未然に防ぎ、スムーズな財産承継が可能になります。
- 遺言書の紛失や盗難、破棄のリスクがなくなる
- 家庭裁判所での検認手続きが不要になる
- 遺言書の偽造や変造を防止できる
- 法務局が遺言者の死亡情報を把握した場合、相続人等に遺言書の保管の有無を通知する仕組みがある
- 財産目録を添付する場合、全文自筆でなくてもよい(パソコン作成可)
上記のメリットにより、遺言者の最終意思が確実に実現でき、相続人間のトラブル防止にもつながります。特に検認手続きが不要になることで、相続手続きの期間短縮と費用削減が期待できます。
自筆証書遺言書保管制度の利用方法
自筆証書遺言書保管制度を利用するためには、一定の手続きが必要です。利用できるのは遺言者本人のみで、代理人による申請はできません。
- 遺言書の作成:民法の方式に従って自筆証書遺言を作成する
- 管轄法務局の確認:遺言者の住所地か本籍地を管轄する法務局を選択
- 必要書類の準備:遺言書原本、本人確認書類など
- 法務局での申請:予約が必要な場合もあるので事前確認を
- 遺言書の保管:申請が受理されると遺言書保管証が発行される
上記の流れに沿って手続きを進めますが、法務局によって予約制を採用している場合もあります。事前に電話やインターネットで確認することをおすすめします。
保管申請に必要な書類
自筆証書遺言書の保管申請には、いくつかの書類が必要です。事前に準備しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。
| 必須書類 |
|
|---|---|
| 場合により必要な書類 |
|
本人確認書類は写真付きのものが望ましいですが、健康保険証などでも受け付けられる場合があります。また、財産目録はパソコンで作成したものでも構いませんが、各ページに署名と押印が必要です。
保管手数料について
自筆証書遺言書の保管には所定の手数料がかかります。手数料は保管申請時に納付する必要があります。
| 保管手数料 | 3,900円(収入印紙で納付) |
|---|---|
| その他の手数料 |
|
保管手数料は一度の納付で遺言書が保管されている限り有効です。追加の年間管理費などは発生しません。ただし、遺言書の内容を変更したい場合は、新たな遺言書を作成して再度保管申請を行い、手数料を納付する必要があります。
保管後の手続き
自筆証書遺言書が法務局で保管された後も、いくつかの手続きが可能です。遺言者の死亡後は、相続人などが一定の手続きを行うことになります。
遺言者が生存中にできること
- 遺言書の閲覧(遺言者本人のみ)
- 遺言書の返還請求(保管の終了)
- 遺言書保管事実証明書の交付請求
- 死亡時の通知の申出
遺言者本人であれば、いつでも保管されている遺言書の閲覧や返還を請求できます。また、特定の人に対して、自分の死亡後に遺言書が保管されていることを通知するよう法務局に申し出ることもできます。
遺言者死亡後にできること
- 遺言書情報証明書の交付請求
- 遺言書保管事実証明書の交付請求
- 遺言書の閲覧
遺言者が死亡した後は、相続人や受遺者などの利害関係人が、遺言書情報証明書の交付を請求できます。この証明書は遺言の内容を証明するもので、相続手続きに必要な書類として利用できます。
よくある質問
Q1. 一度保管した遺言書を変更することはできますか?
一度保管した遺言書自体を変更することはできません。内容を変更したい場合は、新たな遺言書を作成して再度保管申請を行う必要があります。この場合、以前の遺言書は自動的に無効になるわけではなく、遺言の内容によっては撤回などの対応が必要です。
Q2. 法務局での保管中に遺言者が亡くなった場合、相続人はどのように遺言書の存在を知ることができますか?
法務局が遺言者の死亡情報を把握した場合、遺言者があらかじめ指定した人に通知が行われます。また、相続人などの利害関係人は、遺言者の死亡後に法務局で遺言書の有無を確認することができます。ただし、法務局が必ず死亡を把握できるわけではないため、遺言者が信頼できる人に遺言書保管証を預けておくことも検討すべきです。
Q3. 自筆証書遺言書保管制度を利用する場合でも、遺言書は全文自筆で作成する必要がありますか?
遺言書本文は従来通り全文自筆で作成する必要がありますが、財産目録についてはパソコンなどで作成することが可能です。ただし、財産目録の各ページに遺言者の署名と押印が必要です。また、遺言書本文と財産目録が一体となっていることが明確になるよう、適切な記載が求められます。
Q4. 保管されている遺言書を他の法務局に移すことはできますか?
遺言書を他の法務局に移すことはできません。引っ越しなどで住所が変わった場合でも、当初申請した法務局での保管が継続されます。住所変更の届出は不要ですが、連絡先が変わった場合は届け出ることをおすすめします。
Q5. 公正証書遺言と自筆証書遺言書保管制度はどちらがよいですか?
どちらが良いかは個人の状況によって異なります。公正証書遺言は公証人の関与があり法的安全性が高いですが、手数料が高額になる場合があります。自筆証書遺言書保管制度は比較的低コストで利用でき検認不要というメリットがありますが、内容面での法的チェックはありません。遺言の内容や予算に応じて選択するとよいでしょう。
まとめ
自筆証書遺言書保管制度は、従来の自筆証書遺言の欠点を補い、安全に遺言を残すことができる画期的な制度です。遺言書の紛失や改ざんのリスクを防ぎ、家庭裁判所での検認手続きも不要になるため、相続手続きの負担を大きく軽減することができます。
この制度を利用するには、法務局への申請が必要で、3,900円の手数料がかかります。遺言者本人が手続きを行う必要があり、代理人による申請はできない点に注意が必要です。
遺言書の内容については従来の自筆証書遺言と同様のルールが適用されますが、財産目録についてはパソコン作成が認められるなど、一部緩和されています。ただし、遺言の内容自体の法的チェックは行われないため、内容に不安がある場合は専門家に相談することをおすすめします。
自筆証書遺言書保管制度と公正証書遺言にはそれぞれメリット・デメリットがあります。ご自身の状況に合わせて、どちらの方法が適しているかを検討するとよいでしょう。いずれにしても、遺言を残すことで、大切な人たちに財産を円滑に引き継ぎ、相続トラブルを防ぐことができます。






