自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)とは?
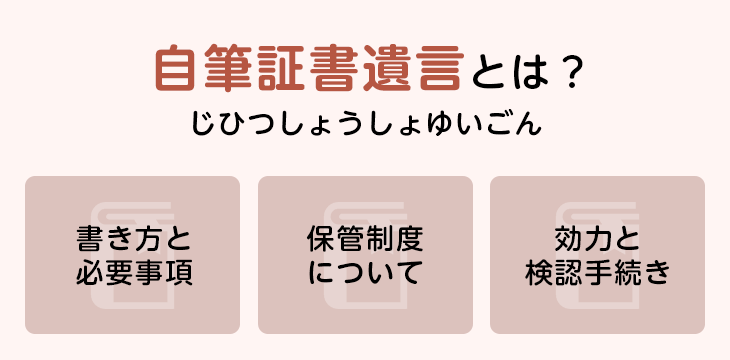
自筆証書遺言とは、遺言者本人が全文を自筆で書き、日付を記載し、署名・押印することで効力を持つ遺言方式です。
2019年の法改正により、財産目録についてはパソコンでの作成が可能になり、さらに法務局で自筆証書遺言書の保管制度が創設されるなど、より利用しやすくなりました。
自筆証書遺言の基本と特徴
自筆証書遺言は、遺言の方式の中で最も手軽に作成できる方法です。証人の立会いが不要で、費用もほとんどかからないため、多くの方に選ばれています。
ただし、法律で定められた形式を満たさないと無効になる可能性があるため、作成時には注意が必要です。自筆証書遺言は原則として全文自筆である必要があり、タイプやワープロでの作成は認められていません。
| 自筆証書遺言のメリット |
|
|---|---|
| 自筆証書遺言のデメリット |
|
上記の表は自筆証書遺言のメリットとデメリットをまとめたものです。法的な効力を持たせるためには、形式要件を満たすことが重要になります。
自筆証書遺言の書き方と必要事項
自筆証書遺言が有効であるためには、民法に定められた要件を満たす必要があります。以下の点に注意して作成しましょう。
- 全文自筆:遺言本文はすべて遺言者本人が自分で書く必要があります
- 日付記入:作成年月日を明記します(西暦・和暦どちらでも可)
- 署名:遺言者の氏名を自署します(フルネームで記載)
- 押印:実印でなくても有効ですが、印鑑登録されているものが望ましいです
上記は自筆証書遺言作成の基本的な流れです。財産目録については2019年の法改正によりパソコン等で作成することが可能になりましたが、その場合も各ページに署名・押印が必要です。
自筆証書遺言の記載例
| 遺言書の基本構成 |
|
|---|
遺言書の文面に決まった書式はありませんが、明確で誤解のない表現を心がけましょう。特に不動産や預貯金などは正確に特定できる情報(所在地、口座番号など)を記載することが重要です。
自筆証書遺言保管制度について
2020年7月から開始された自筆証書遺言保管制度は、法務局で遺言書を保管してもらえる制度です。これにより、遺言書の紛失や隠匿、偽造などのリスクを防ぐことができます。
法務局で保管された遺言書は、遺言者の死亡後に家庭裁判所での検認手続きが不要となり、相続手続きがスムーズに進められるというメリットもあります。
| 保管制度の利用方法 |
|
|---|
保管制度を利用する際は事前予約が必要です。また、いったん保管した遺言書は引き出して書き直すことができないため、新たに遺言書を作成して保管申請する必要があります。
自筆証書遺言の効力と検認手続き
自筆証書遺言は、作成の時点で効力を持ちますが、遺言者が亡くなった後、遺言書を発見した人は原則として1か月以内に家庭裁判所に提出し、検認手続きを行う必要があります。
検認とは、遺言書の形状・加除訂正の状態などを確認し、相続人に遺言の存在と内容を知らせる手続きです。遺言の有効性を判断するものではありません。
- 検認手続きは遺言書の存在と内容を相続人全員に知らせるための手続き
- 検認を受けていない遺言書に基づく登記などの手続きはできない
- 法務局保管の自筆証書遺言は検認が不要
- 公正証書遺言も検認は不要
上記は遺言書の検認に関する重要なポイントです。検認を経ない自筆証書遺言に基づいて不動産の名義変更などの手続きを行うことはできませんので注意が必要です。
他の遺言方式との比較
遺言書には自筆証書遺言のほかに、公正証書遺言と秘密証書遺言があります。それぞれの特徴を理解し、自分に適した方式を選びましょう。
| 遺言方式 | 特徴 | おすすめのケース |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 |
|
|
| 公正証書遺言 |
|
|
| 秘密証書遺言 |
|
|
この表は主な遺言方式の比較です。一般的には公正証書遺言が最も安全で確実な方法とされていますが、状況に応じて適切な方式を選ぶことが大切です。
自筆証書遺言に関するよくある質問
Q1. パソコンで作成した遺言書は有効ですか?
原則として、遺言本文はすべて自筆で書く必要があります。パソコンやワープロで作成された遺言書は無効です。ただし、2019年の法改正により、財産目録についてはパソコン等で作成することが可能になりました。
Q2. 自筆証書遺言に証人は必要ですか?
自筆証書遺言には証人は不要です。これが公正証書遺言や秘密証書遺言との大きな違いです。ただし、遺言者本人の署名と押印は必須となります。
Q3. 自筆証書遺言を書き直したい場合はどうすればよいですか?
新たに遺言書を作成し、以前の遺言書を撤回する旨を明記します。日付の新しい遺言書が優先されるため、必ず作成日を記入してください。古い遺言書は破棄するか、法務局保管の場合は保管事実証明書を請求して撤回することができます。
Q4. 自筆証書遺言保管制度を利用する際の費用はいくらですか?
自筆証書遺言保管制度の利用手数料は3,900円です。遺言書の保管期間に制限はなく、撤回して新しい遺言書を保管する場合にも同額の手数料がかかります。
Q5. 法務局に保管された遺言書はどのように確認できますか?
遺言者本人は「遺言書情報証明書」を請求することで内容を確認できます。相続人などは遺言者の死亡後に「遺言書情報証明書」を請求することができ、死亡の事実を証明する戸籍謄本等が必要になります。
まとめ
自筆証書遺言は、誰でも手軽に作成できる遺言方式として多くの方に利用されています。費用がほとんどかからず、秘密性も高いというメリットがある一方で、形式不備による無効リスクや紛失のリスクもあります。
2019年の法改正により財産目録のパソコン作成が認められ、2020年からは法務局での保管制度も始まったことで、以前よりも利用しやすくなりました。特に保管制度を利用することで、遺言書の紛失や偽造のリスクを防ぎ、検認手続きも不要になるため、相続手続きがスムーズになります。
ただし、内容が複雑な場合や確実な効力を求める場合は、公正証書遺言の利用も検討すべきでしょう。自分の財産や家族の状況に合わせて、最適な遺言方式を選ぶことが大切です。専門家のアドバイスを受けながら、有効な遺言を残しましょう。






