遺留分放棄(いりょうぶんほうき)とは?
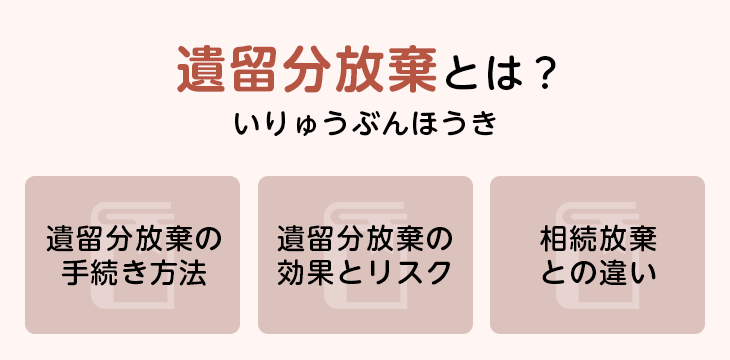
遺留分放棄とは、相続人が法律で保障されている「遺留分」と呼ばれる最低限の相続分を事前に放棄する手続きのことです。被相続人の生前に家庭裁判所の許可を得て行う特別な手続きであり、一度放棄すると取り消すことができません。
遺留分放棄を行うことで、相続人間のトラブルを防いだり、スムーズな事業承継を実現したりすることが可能になります。ただし、慎重に検討すべき重要な選択です。
遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人に法律で保障されている最低限の相続分のことです。被相続人が遺言で財産の分配方法を自由に決められますが、それでも特定の相続人には最低限の取り分が確保されています。
遺留分が認められている相続人は「兄弟姉妹を除く法定相続人」です。つまり、配偶者、子、直系尊属(親や祖父母)には遺留分が保障されていますが、兄弟姉妹には遺留分はありません。
| 遺留分の割合 | 法定相続分の2分の1(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1) |
|---|---|
| 遺留分権利者 |
|
この表は遺留分の基本的な割合と権利者を示しています。法定相続分の半分が基本的な遺留分の割合となり、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1になります。
遺留分放棄の目的
遺留分放棄をする主な目的には以下のようなものがあります。
- 事業承継をスムーズに行うため
- 特定の相続人に財産を集中させるため
- 相続争いを未然に防ぐため
- 生前贈与や遺言の効力を確実にするため
このリストは遺留分放棄を検討する主な理由です。特に家業や事業を継ぐ場合、分散を避けるために行われることが多いでしょう。
例えば、家業を継ぐ長男に会社の株式を集中させたい場合、他の相続人が遺留分放棄をすることで、遺言や生前贈与による財産移転が確実になります。また、相続時の争いを避けるために、生前に話し合って他の財産での補償と引き換えに遺留分放棄を行うケースもあります。
遺留分放棄の手続き
遺留分放棄は、以下の流れで行います。
- 家庭裁判所への申立書類の準備:必要書類を揃えます
- 家庭裁判所への申立て:被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います
- 家庭裁判所での審問:必要に応じて家庭裁判所で審問があります
- 家庭裁判所の許可:審査の結果、許可されると決定書が交付されます
- 効力の発生:許可が下りた時点で遺留分放棄の効力が生じます
このリストは遺留分放棄手続きの基本的な流れを示しています。実際の手続きでは、家庭裁判所に「遺留分放棄申述書」や戸籍謄本などの書類を提出することが必要です。
申立ては被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に行い、家庭裁判所は申立人の意思確認や判断能力、経済的な不利益の有無などを審査します。特に、遺留分放棄が申立人にとって不当に不利益にならないかを重視して判断されます。
必要書類
| 申立人関係 |
|
|---|---|
| 被相続人関係 |
|
| その他 |
|
この表は遺留分放棄の申立てに必要な主な書類をまとめたものです。各家庭裁判所によって若干異なる場合がありますので、事前に確認することをおすすめします。
遺留分放棄の効果とリスク
遺留分放棄をすると、以下のような効果とリスクがあります。
| 効果 |
|
|---|---|
| リスク |
|
この表は遺留分放棄の主な効果とリスクを対比して示しています。特に、放棄は取り消せないため、将来の資産価値の変動や家族関係の変化があっても覆すことができません。
遺留分放棄は法的に強い効力を持つため、慎重な判断が必要です。放棄後に被相続人の財産が予想以上に増えた場合でも、一度放棄した遺留分の権利は戻りません。また、遺留分放棄は相続放棄とは異なり、相続自体は放棄していないため、遺言などで指定された相続分については受け取ることができます。
遺留分放棄と相続放棄の違い
遺留分放棄と相続放棄は似て非なるものです。その違いを以下に示します。
| 項目 | 遺留分放棄 | 相続放棄 |
|---|---|---|
| 時期 | 被相続人の生前 | 被相続人の死亡後(相続開始を知った日から3ヶ月以内) |
| 手続き先 | 家庭裁判所(許可制) | 家庭裁判所(申述制) |
| 放棄する権利 | 遺留分のみ | 相続権全て(プラスの財産もマイナスの財産も) |
| 効力 | 最低限保障される相続分を放棄する | 初めから相続人ではなかったものとみなされる |
この表は遺留分放棄と相続放棄の主要な違いを比較したものです。両者は目的も手続きも大きく異なります。
遺留分放棄は被相続人が生きている間に行う手続きで、最低限保障される相続分のみを放棄します。一方、相続放棄は被相続人の死後に行い、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も含めた相続権全体を放棄します。
よくある質問
遺留分放棄は後から取り消すことはできますか?
いいえ、家庭裁判所の許可を得て行った遺留分放棄は、原則として取り消すことができません。そのため、放棄を検討する際は将来の資産状況の変動も考慮して、慎重に判断する必要があります。
遺留分放棄をしても、相続はできますか?
はい、遺留分放棄は遺留分の権利だけを放棄するものであり、相続自体は放棄していません。そのため、遺言や法定相続分に基づいて相続することは可能です。遺留分放棄をしても、被相続人の意思(遺言など)に従って財産を相続できます。
未成年者でも遺留分放棄はできますか?
未成年者が遺留分放棄をする場合、親権者が代理人として申立てをすることになります。ただし、親権者と未成年者の間で利益相反がある場合は、特別代理人の選任が必要です。家庭裁判所は未成年者の利益を特に慎重に判断します。
遺留分放棄の費用はどのくらいかかりますか?
遺留分放棄の申立てには、収入印紙800円、連絡用の郵便切手代(裁判所によって異なる)などがかかります。司法書士などの専門家に依頼する場合は、別途報酬が発生します。一般的には5万円〜10万円程度が相場ですが、案件の複雑さによって変動します。
遺留分放棄を代理人に依頼できますか?
はい、遺留分放棄の手続きは本人だけでなく、代理人に依頼することも可能です。司法書士などの専門家に依頼することで、適切な書類作成や手続きを行うことができます。ただし、家庭裁判所での審問には本人の出席が求められることもあります。
まとめ
遺留分放棄とは、被相続人の生前に、相続人が法律で保障されている最低限の相続分(遺留分)を放棄する手続きです。この手続きは家庭裁判所の許可を得て行い、一度許可されると取り消すことができません。
遺留分放棄の主な目的は、事業承継をスムーズに行うことや、特定の相続人に財産を集中させること、また将来の相続争いを未然に防ぐことなどが挙げられます。手続きには家庭裁判所への申立てと審査が必要で、申立人の意思確認や経済的不利益の有無などが慎重に判断されます。
遺留分放棄と相続放棄は異なる制度であり、遺留分放棄は最低限保障される相続分のみを放棄するもので、相続自体は放棄しません。一方、相続放棄は相続権全体を放棄し、プラスもマイナスも含めた全ての相続財産との関係を断ち切るものです。
遺留分放棄は一度行うと取り消せないため、将来の資産状況の変化も考慮して慎重に判断すべき重要な選択です。特に家業や事業の承継を円滑に進めたい場合などに有効な手段となりますが、専門家への相談をおすすめします。






