遺留分(いりゅうぶん)とは?
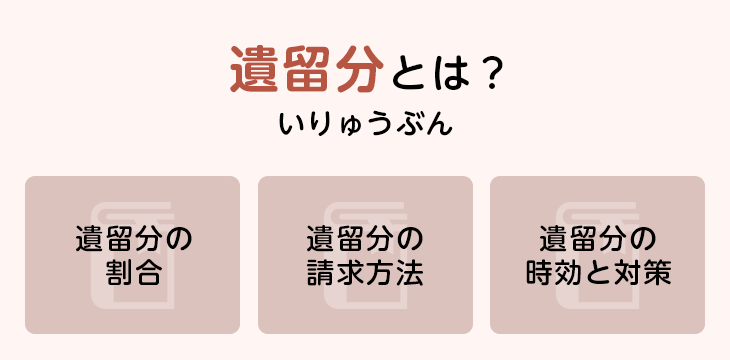
遺留分とは、相続人の最低限の取り分を法律で保障する制度です。
被相続人がすべての財産を自由に処分できるわけではなく、一定の相続人には最低限の相続分が保障されています。これにより、特定の相続人が著しく不利益を被ることを防ぎ、相続における公平性を確保する仕組みとなっています。
遺留分の基本知識
遺留分は民法で定められた法定相続人の権利であり、被相続人の意思に関わらず保障されています。遺言や生前贈与によって遺留分が侵害された場合、該当する相続人は「遺留分侵害額請求」という手続きを行うことができます。
2019年7月1日の民法改正により、それまでの「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」に名称が変更されました。この改正によって、原則として金銭での請求となり、より実務的な対応が可能になりました。
| 改正前 | 遺留分減殺請求(現物返還が原則) |
|---|---|
| 改正後(現行) | 遺留分侵害額請求(金銭請求が原則) |
上記の表は民法改正による遺留分請求の変更点をまとめたものです。改正前は現物での返還が原則でしたが、現在は金銭での支払いが原則となっています。
遺留分の請求権者と割合
遺留分が認められる相続人は限定されており、すべての法定相続人に認められるわけではありません。遺留分を請求できる権利者と、その割合について理解しましょう。
遺留分を持つ相続人
- 配偶者(夫または妻)
- 子(養子を含む)
- 直系尊属(親、祖父母など)
上記のリストは遺留分が認められる相続人です。兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺言によって相続から除外されても請求することはできません。
遺留分の割合
遺留分の割合は、通常の法定相続分の2分の1とされています。ただし、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1となります。
| 相続人の構成 | 遺留分の割合 |
|---|---|
| 配偶者のみ | 財産の1/2(法定相続分)× 1/2 = 1/4 |
| 子のみ | 財産の全部(法定相続分)× 1/2 = 1/2 |
| 配偶者と子 | 配偶者:財産の1/2(法定相続分)× 1/2 = 1/4 子:財産の1/2(法定相続分)× 1/2 = 1/4 |
| 直系尊属のみ | 財産の全部(法定相続分)× 1/3 = 1/3 |
| 配偶者と直系尊属 | 配偶者:財産の2/3(法定相続分)× 1/2 = 1/3 直系尊属:財産の1/3(法定相続分)× 1/3 = 1/9 |
この表は相続人の構成によって変わる遺留分の割合を示しています。例えば、配偶者と子が相続人の場合、それぞれが財産の1/4ずつの遺留分を持ちます。
遺留分侵害額請求の方法
遺留分が侵害されたと感じた場合、相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことができます。その手続きの流れを理解しましょう。
- 遺留分侵害の確認:相続財産の総額と自分の遺留分を計算し、侵害額を把握します
- 受遺者や受贈者への通知:内容証明郵便などで請求の意思を通知します
- 協議:当事者間で話し合いを行います
- 合意形成または調停・裁判:協議がまとまらない場合は法的手続きに進みます
- 金銭の支払いまたは代物弁済:遺留分侵害額の清算を行います
上記のリストは遺留分侵害額請求の一般的な流れです。できるだけ当事者間の話し合いで解決することが望ましいですが、合意に至らない場合は家庭裁判所での調停や訴訟に進むこともあります。
遺留分算定の基礎となる財産
遺留分の計算には、相続開始時の財産に加えて、一定期間内の生前贈与も含まれることがあります。これを「遺留分算定の基礎となる財産」といいます。
| 対象となる財産 |
|
|---|---|
| 対象とならない財産 |
この表は遺留分算定の際に基礎となる財産と対象とならない財産を示しています。生前贈与も一定条件下では計算に含まれる点に注意が必要です。
遺留分の時効と対策
遺留分侵害額請求権には時効があります。権利を行使する期限を正しく理解し、適切な対応を取ることが重要です。
| 時効期間 |
|
|---|
上記の表は遺留分侵害額請求権の時効期間を示しています。「知った時」とは、遺留分を侵害する遺言や贈与の存在、および侵害額を知った時点を指します。
遺留分対策の方法
被相続人の立場からは、遺言作成時に遺留分を考慮した財産分配を計画することが重要です。また、相続人の立場からは権利を適切に保護するための知識を持つことが大切です。
- 生命保険の活用(受取人を指定することで遺留分算定の基礎財産から除外)
- 生前贈与の計画的実施(相続開始1年超前の贈与は原則として算入されない)
- 遺留分放棄の手続き(家庭裁判所の許可が必要)
- 相続人との事前合意(公正証書など文書化することで後のトラブル防止)
- 代償財産の準備(現金や換金しやすい資産を用意)
このリストは主な遺留分対策の方法です。特に事業承継など特定の相続人に事業用資産を集中させたい場合などに有効です。ただし、これらの対策には専門的な知識が必要なため、専門家への相談をおすすめします。
遺留分に関する特殊なケース
遺留分に関しては、特殊なケースや注意すべき点もあります。代表的なものをいくつか確認しておきましょう。
代襲相続と遺留分
相続人が被相続人より先に死亡している場合、その子(被相続人の孫)が代襲相続人となります。代襲相続人にも遺留分が認められますが、その割合は本来の相続人が受け取るはずだった遺留分の範囲内となります。
特別受益と遺留分
被相続人から生前に特別な利益(特別受益)を受けていた相続人については、その価額を考慮して遺留分が調整されることがあります。例えば、教育費や結婚資金などの援助を受けていた場合です。
遺留分の放棄
相続人は家庭裁判所の許可を得ることで、相続開始前に遺留分を放棄することができます。これは被相続人の生前に行う手続きで、相続放棄とは異なる点に注意が必要です。
| 遺留分放棄 | 被相続人の生前に家庭裁判所の許可を得て行う。遺留分のみを放棄し、相続自体は放棄しない |
|---|---|
| 相続放棄 | 相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する。相続権全体を放棄する |
この表は遺留分放棄と相続放棄の違いを示しています。両者は手続きのタイミングや効果が大きく異なるため、混同しないよう注意が必要です。
遺留分に関するよくある質問
Q1. 兄弟姉妹に遺留分はありますか?
いいえ、兄弟姉妹には遺留分はありません。遺留分が認められているのは、配偶者、子、および直系尊属(親や祖父母)のみです。そのため、兄弟姉妹は遺言によって相続から除外されても、遺留分侵害額請求をすることはできません。
Q2. 養子にも遺留分はありますか?
はい、法的に有効な養子縁組が成立している場合、養子にも実子と同様の遺留分が認められます。ただし、特別養子縁組の場合は実親との関係が終了するため、実親からの遺留分は認められなくなります。
Q3. 遺留分を侵害しないようにするには、どのように遺言を書けばよいですか?
遺言を作成する際は、各相続人の遺留分を計算し、それを下回らないように財産を分配することが基本です。特定の相続人に多くの財産を残したい場合は、遺留分に相当する財産を現金などの分割しやすい形で準備しておくとよいでしょう。専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
Q4. 遺留分侵害額請求をした場合、家族関係が悪化しませんか?
遺留分侵害額請求は法的権利ですが、家族間の問題であるため感情的な対立を招くことがあります。できれば当事者間の話し合いで解決することが望ましいですが、難しい場合は弁護士などの専門家に間に入ってもらうことで、冷静な解決を図ることができるでしょう。
Q5. 遺留分の計算に生命保険金は含まれますか?
原則として、死亡保険金は受取人が指定されている場合、遺留分算定の基礎財産には含まれません。これは、保険金が被相続人の財産ではなく、保険契約に基づき受取人に直接支払われるものだからです。ただし、著しく高額な保険料を支払っていた場合など、特殊なケースでは判断が異なることもあります。
まとめ
遺留分は、一定の相続人に対して最低限の財産取得を保障する制度です。配偶者、子、直系尊属に認められ、兄弟姉妹には認められていません。遺留分の割合は法定相続分の2分の1(直系尊属のみの場合は3分の1)となります。
2019年の民法改正により、遺留分侵害に対する請求は「遺留分侵害額請求」となり、原則として金銭での解決が基本となりました。請求権は「知った時から1年」または「相続開始から10年」という時効があるため、権利行使の時期に注意が必要です。
遺言を作成する際は遺留分を考慮した財産分配を計画し、相続人は自分の権利を適切に保護するための知識を持つことが重要です。特に事業承継や不動産など分割しにくい財産が多い場合は、生命保険の活用や生前贈与など、計画的な対策が有効です。
遺留分に関する問題は家族間の深刻な対立を招くことがあるため、できるだけ当事者間の話し合いでの解決を目指すべきですが、必要に応じて専門家のサポートを受けることをおすすめします。適切な知識と準備によって、円滑な相続を実現しましょう。






