法定相続人(ほうていそうぞくにん)とは?
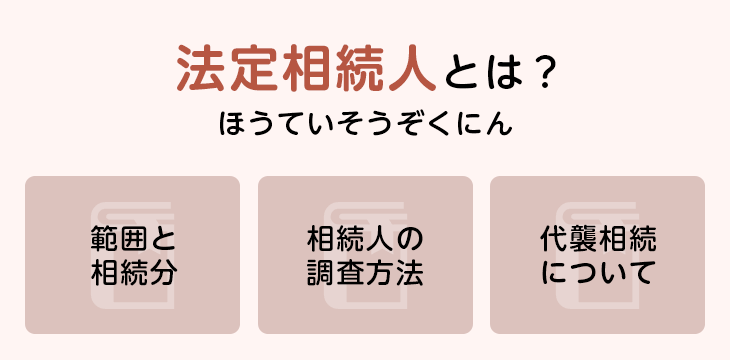
法定相続人とは、民法で定められた相続権を持つ人のことです。亡くなった方(被相続人)の配偶者と、一定範囲の血族(子、直系尊属、兄弟姉妹)が該当します。
法定相続人の範囲や相続分は民法で明確に規定されており、遺言がない場合の財産分配の基準となります。誰が法定相続人になるかを知ることは、相続手続きの第一歩といえるでしょう。
法定相続人とは
法定相続人とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続する権利を法律上与えられている人のことです。民法で定められた一定の親族が該当し、遺言書がない場合は法定相続人と法定相続分に従って遺産が分配されます。
遺言書があっても、遺留分(法定相続人に保障された最低限の相続分)は保護されるため、法定相続人かどうかの確認は重要な意味を持ちます。相続手続きを進める際は、まず法定相続人を確定させることから始めましょう。
法定相続人の範囲
法定相続人になる人は民法で明確に定められています。相続の際には、次の順位に従って法定相続人が決まります。
| 第1順位 | 被相続人の子(養子も含む) |
|---|---|
| 第2順位 | 被相続人の直系尊属(父母、祖父母など) |
| 第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 |
| 常に相続人 | 被相続人の配偶者(婚姻関係にある夫または妻) |
この表は相続人の順位を示しています。血族については、上位の順位に該当する人がいる場合、下位の順位の人は相続人になりません。例えば、子がいる場合、父母や兄弟姉妹は相続人にはなりません。
なお、配偶者は常に相続人となり、他の相続人と共同で相続することになります。内縁関係の場合は、法律上の配偶者とはみなされないため注意が必要です。
第1順位:子
子とは、被相続人の実子(婚姻中の子、婚姻外の子を問わない)および養子をいいます。認知された子も含まれます。
子が複数いる場合は、全員が平等に相続権を持ちます。また、子が既に死亡している場合は、その子の子(被相続人から見て孫)が代襲相続します。
第2順位:直系尊属
直系尊属とは、被相続人の父母、祖父母などの直系の尊属親族をいいます。子がいない場合に初めて相続人となります。
直系尊属が複数いる場合は、親等の近い者を優先します。例えば、父母と祖父母がいる場合は、父母のみが相続人となります。
第3順位:兄弟姉妹
兄弟姉妹は、子も直系尊属もいない場合に初めて相続人となります。兄弟姉妹が既に死亡している場合は、その子(被相続人から見て甥・姪)が代襲相続します。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は、甥・姪の代までとなり、さらにその先の子(被相続人から見て大甥・大姪)には及びません。
配偶者
配偶者は、被相続人と法律上の婚姻関係にあった人をいいます。血族相続人の有無にかかわらず、常に相続人となります。
事実婚(内縁関係)のパートナーは、法定相続人とはならないため注意が必要です。また、離婚が成立している場合も相続権はありません。
法定相続分について
法定相続分とは、遺言がない場合に法定相続人が相続できる財産の割合のことです。民法で以下のように定められています。
| 相続人の組み合わせ | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者と子 |
|
| 配偶者と直系尊属 |
|
| 配偶者と兄弟姉妹 |
|
| 配偶者のみ | 配偶者:全部(相続財産の100%) |
| 子のみ | 子:全部(子が複数いる場合は均等に分ける) |
| 直系尊属のみ | 直系尊属:全部(直系尊属が複数いる場合は均等に分ける) |
| 兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹:全部(兄弟姉妹が複数いる場合は均等に分ける) |
この表は相続人の組み合わせ別の法定相続分を示しています。兄弟姉妹については、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)で相続分が異なり、半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の1/2となります。
代襲相続について
代襲相続とは、本来相続人となるべき人が被相続人より先に死亡している場合などに、その人の子(被相続人から見て孫や甥・姪)が「代わって」相続人となる制度です。
代襲相続が発生するのは、次のような場合です。
この代襲相続の範囲は、相続人の順位によって異なります。子の場合は無制限に代襲し、兄弟姉妹の場合は甥・姪までとなります。直系尊属については代襲相続の制度はありません。
相続人の調査方法
相続手続きを進めるためには、法定相続人を正確に把握する必要があります。調査方法としては、主に戸籍謄本を収集して確認します。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得する
- 被相続人の配偶者の戸籍謄本を取得する
- 被相続人の子の戸籍謄本を取得する(子が既に死亡している場合はその子の戸籍謄本も)
- 子がいない場合は、被相続人の直系尊属の戸籍謄本を取得する
- 子も直系尊属もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹の戸籍謄本を取得する
この流れは相続人調査の基本的な手順です。戸籍謄本の収集は、市区町村役場で請求することができますが、被相続人との関係を証明する書類が必要になる場合があります。
相続人調査は専門的な知識が必要な場合もあるため、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することもおすすめです。
よくある質問
内縁関係のパートナーは法定相続人になれますか?
内縁関係のパートナーは、法律上の婚姻関係にないため、法定相続人にはなれません。パートナーに財産を残したい場合は、遺言書を作成するか、生前贈与を行うなどの対策が必要です。
養子は法定相続人になれますか?
養子は、実子と同様に法定相続人となります。法律上の養子縁組が成立していれば、実子と同じ相続分を持ちます。ただし、特別養子縁組の場合は、実親との間の相続関係は終了します。
相続放棄をすると、その人の子は代襲相続できますか?
基本的に、相続放棄をした人の子は代襲相続できません。ただし、兄弟姉妹が相続放棄をした場合に限り、その子(甥・姪)は代襲相続することができます。子や直系尊属が相続放棄した場合は、代襲相続は発生しません。
戸籍上の親子関係がない場合でも法定相続人になれますか?
婚姻外の子(非嫡出子)でも、認知されていれば法定相続人となります。認知されていない場合は、家庭裁判所で親子関係の確認の訴えを起こし、親子関係が認められれば相続人となることができます。
相続人がいない場合はどうなりますか?
法定相続人が全くいない場合(相続人不存在)、相続財産は最終的に国庫に帰属します。ただし、その前に特別縁故者(被相続人と特別な関係があった人)が家庭裁判所に請求することで、財産の全部または一部を取得できる可能性があります。
まとめ
法定相続人とは、民法で定められた相続権を持つ人のことで、被相続人の配偶者と、一定範囲の血族(子、直系尊属、兄弟姉妹)が該当します。配偶者は常に相続人となり、血族は第1順位(子)、第2順位(直系尊属)、第3順位(兄弟姉妹)の順で相続権を持ちます。
法定相続分は、配偶者と子の場合は1/2ずつ、配偶者と直系尊属の場合は2/3と1/3、配偶者と兄弟姉妹の場合は3/4と1/4となっています。また、相続人となるべき人が既に死亡している場合などには、代襲相続の制度があります。
相続手続きを正確に進めるためには、まず法定相続人を正確に把握することが重要です。戸籍謄本の収集などによる調査が必要となりますが、複雑なケースでは専門家に相談することもおすすめします。法定相続人を確定させることが、円滑な相続手続きの第一歩です。






