配偶者(はいぐうしゃ)とは?
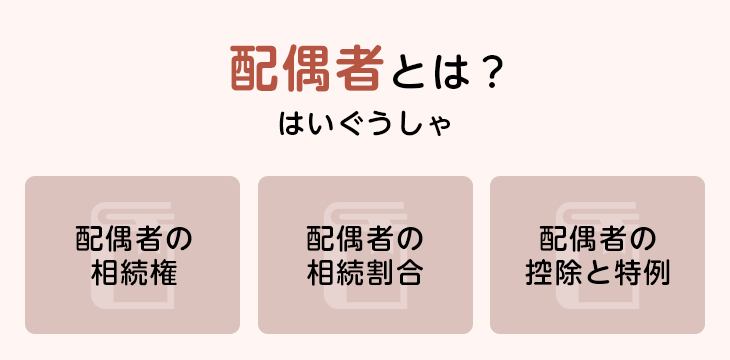
配偶者とは、戸籍上の婚姻関係にある夫または妻のことを指します。相続法上、配偶者は最も重要な法定相続人の一人であり、被相続人亡くなった場合には、他の相続人がいるかどうかにかかわらず、常に相続権を持ちます。
相続における配偶者の権利は民法で特別に保護されており、配偶者控除や配偶者居住権など、さまざまな優遇措置が設けられています。
配偶者の相続権
配偶者は、被相続人(亡くなった方)の財産を相続する権利を持つ法定相続人の一人です。民法では、配偶者は常に相続権を持つと定められています。
つまり、子供や親、兄弟姉妹などの他の相続人がいるかどうかにかかわらず、配偶者は必ず相続人となります。このことから、配偶者は相続において特別な地位を持っていることがわかります。
| 配偶者の特徴 | 常に第一順位の法定相続人となる |
|---|---|
| 必要な条件 |
|
上記の表は配偶者が相続権を持つための条件を示しています。特に注意すべき点は、内縁関係にある方は法律上の配偶者とは認められず、相続権を持たないことです。
配偶者の相続割合
配偶者の法定相続分(相続割合)は、他にどのような相続人がいるかによって変わります。民法では、配偶者と共に相続する人によって、以下のように相続分が定められています。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者と子 | 1/2(残りの1/2を子が均等に分ける) |
| 配偶者と被相続人の親 | 2/3(残りの1/3を親が均等に分ける) |
| 配偶者と被相続人の兄弟姉妹 | 3/4(残りの1/4を兄弟姉妹が均等に分ける) |
| 配偶者のみ | 全部(相続財産の100%) |
この表は、配偶者と他の相続人との関係によって、配偶者が受け取れる相続分がどのように変わるかを示しています。子供がいる場合は財産の半分、親のみの場合は3分の2、兄弟姉妹のみの場合は4分の3が配偶者の取り分となります。
配偶者居住権
配偶者居住権とは、2020年の民法改正で新たに創設された制度で、被相続人の所有していた居住用不動産に住み続ける権利を配偶者に保障するものです。配偶者が亡くなった後も、残された配偶者がこれまで通りその家に住み続けられるよう配慮された制度です。
配偶者居住権の特徴
- 被相続人所有の建物に相続開始時に居住していた配偶者に認められる
- 配偶者が亡くなるまで、または決められた期間、住み続けることができる
- 物権として登記することができる
- 居住権と建物の所有権を分けることができるため、相続資産の分配がしやすくなる
上記のリストは配偶者居住権の主な特徴です。この制度により、配偶者は自宅に住み続けながらも、建物の評価額を下げて相続税の負担を軽減することが可能になりました。
配偶者居住権の評価
相続税における配偶者居住権の評価額は、建物の時価から算出され、配偶者の年齢や居住権の存続期間によって変わります。一般的に、配偶者の年齢が高いほど、また存続期間が短いほど評価額は低くなります。
配偶者控除
相続税の配偶者控除(正式には「配偶者に対する相続税額の軽減」)とは、被相続人の配偶者が相続や遺贈によって財産を取得した場合、一定の金額まで相続税が課税されない特例です。
| 控除の上限額 | 1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか大きい金額 |
|---|---|
| 適用条件 |
|
この表は配偶者控除の概要を示しています。例えば、相続財産が3億円で配偶者と子2人が相続する場合、配偶者の法定相続分は1億5,000万円ですが、配偶者控除の上限額である1億6,000万円まで税金がかからないことになります。
配偶者と贈与税の特例
配偶者間の贈与には、通常の贈与とは異なる特例が設けられています。特に注目すべきは「配偶者控除(結婚20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与)」です。
結婚20年以上の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用の不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円に加えて最高2,000万円まで控除される特例があります。
- 婚姻期間が20年以上であること:婚姻届の提出日から贈与の日まで20年以上経過していることが必要です
- 居住用不動産または資金であること:贈与の対象は、夫婦が住むための不動産または住宅購入資金に限られます
- 贈与税の申告が必要:特例を受けるためには、贈与税の申告期限内に申告する必要があります
- 一生に一度限り:この特例は一生に一度しか利用できません
上記は結婚20年以上の配偶者控除を受けるための条件と流れです。この特例を利用することで、夫婦間での資産移転が税制上有利になることがあります。
よくある質問
Q1. 内縁関係の場合、相続権はありますか?
内縁関係(婚姻届を提出していない事実婚の関係)にある方は、法律上の配偶者とは認められないため、相続権はありません。ただし、遺言書で相続人として指定することは可能です。
また、内縁関係にあった方が亡くなった場合、生活保障の観点から「死亡退職金」などの受取人になれる場合もあります。
Q2. 配偶者居住権は必ず取得できますか?
配偶者居住権は、遺産分割協議や遺言、家庭裁判所の審判によって取得するものであり、自動的に与えられるものではありません。取得するためには、相続開始時に被相続人の所有していた建物に居住していることが前提条件となります。
Q3. 海外で結婚した場合、日本の法律で配偶者として認められますか?
海外で結婚した場合でも、その結婚が日本の法律で有効と認められれば、相続に関しても配偶者として扱われます。ただし、重婚や近親婚など日本の公序良俗に反する場合は認められないことがあります。
相続手続きの際には、外国の婚姻証明書などの翻訳文を準備する必要があります。
Q4. 配偶者控除は自動的に適用されますか?
配偶者控除は自動的には適用されません。相続税の申告期限内(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内)に税務署へ申告することが必要です。
また、配偶者が実際に財産を取得していることが条件となるため、相続放棄をした場合には適用されません。
Q5. 離婚協議中に配偶者が亡くなった場合、相続権はありますか?
離婚協議中であっても、正式に離婚が成立していない場合は、法律上はまだ配偶者であるため相続権があります。ただし、別居中や調停中という事情が遺産分割の際に考慮されることはあります。
相続権が発生するかどうかは、被相続人の死亡時点で法律上の婚姻関係が存続しているかどうかで判断されます。
まとめ
配偶者は相続において特別な地位を持つ法定相続人です。常に相続権を持ち、子供がいる場合は財産の1/2、親のみの場合は2/3、兄弟姉妹のみの場合は3/4、他に相続人がいない場合は全ての財産を相続します。
2020年の民法改正では配偶者居住権が新設され、配偶者が亡くなった後も残された配偶者が自宅に住み続けられる権利が保障されるようになりました。この制度は相続税の負担軽減にも役立ちます。
また、相続税における配偶者控除では、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか大きい金額まで相続税が課税されません。贈与税においても、婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与には最高2,000万円の控除が認められています。
配偶者の権利を十分に活用するためには、正確な知識と適切な手続きが必要です。特に配偶者控除や配偶者居住権などの特例を利用する場合は、期限内の申告や必要書類の準備が重要になります。専門家に相談しながら、適切な相続対策を行うことをおすすめします。






