代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)とは?
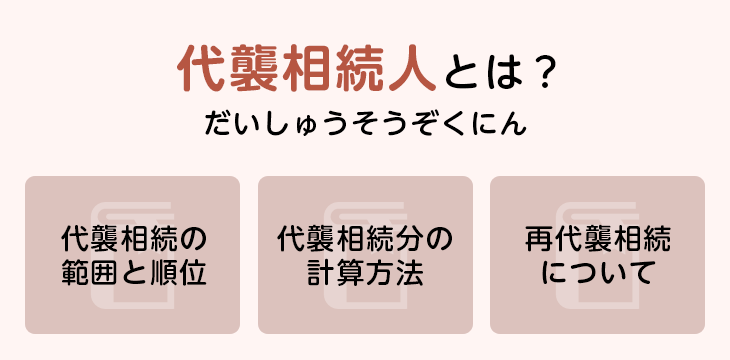
代襲相続人とは、本来相続人となるべき人が被相続人よりも先に死亡したり、相続欠格や廃除によって相続権を失った場合に、その人に代わって相続権を取得する人のことです。
主に子や兄弟姉妹の直系卑属(子や孫など)が代襲相続人となり、被相続人の財産を受け継ぐ権利を持ちます。
代襲相続人の基本
代襲相続人制度は、本来相続人となるはずだった人(子や兄弟姉妹など)が何らかの理由で相続できなくなった場合に、その子(被相続人から見れば孫や甥・姪)が代わりに相続権を得る制度です。
この制度は「血のつながった家族の財産を守る」という相続の基本理念に基づいています。突然の不幸で親が先に亡くなっても、子や孫の相続権を保護する重要な仕組みです。
| 代襲相続人の定義 | 本来相続人となるべき人が相続開始前に死亡などした場合に、その人に代わって相続権を取得する人 |
|---|---|
| 法的根拠 | 民法第887条(代襲相続)、第889条(代襲相続人の相続分) |
上記の表は代襲相続人の基本的な定義と法的根拠を示しています。民法に明確に規定された制度であり、相続において重要な役割を果たします。
代襲相続が発生する条件
代襲相続が発生するのは、以下の3つの条件のいずれかに該当する場合です。
- 本来の相続人が被相続人より先に死亡している場合
- 本来の相続人が相続欠格事由に該当し、相続権を失った場合
- 本来の相続人が廃除によって相続権を失った場合
上記のリストは代襲相続が発生する主な条件を示しています。最も一般的なのは本来の相続人が先に死亡しているケースですが、相続欠格や廃除のような法的な事由でも代襲相続は発生します。
相続欠格と廃除の違い
| 相続欠格 | 故意に被相続人や他の相続人を殺害したり、遺言書を偽造・隠匿したりするなどの著しい非行があった場合に、法律上当然に相続権を失うこと |
|---|---|
| 廃除 | 被相続人に対する虐待や重大な侮辱など、著しい非行があった場合に、被相続人の請求により家庭裁判所の審判を経て相続権を失うこと |
上記の表は相続欠格と廃除の違いを説明しています。どちらの場合も代襲相続が発生しますが、成立要件や手続きが異なります。
代襲相続の範囲と順位
代襲相続は相続人の種類によって範囲が異なります。法定相続人の種類と代襲相続の可否は以下のとおりです。
| 法定相続人 | 代襲相続の可否 | 代襲の範囲 |
|---|---|---|
| 第1順位:子 | 可能 | 無制限(何世代でも代襲可能) |
| 第2順位:直系尊属(親、祖父母) | 不可 | – |
| 第3順位:兄弟姉妹 | 可能 | 1世代のみ(甥・姪まで) |
| 配偶者 | 不可 | – |
上記の表は各法定相続人における代襲相続の可否と範囲を示しています。子の代襲相続は無制限に認められますが、兄弟姉妹の代襲は1世代のみに限定されます。
代襲相続分の計算方法
代襲相続人が相続できる財産の割合(相続分)は、本来の相続人が受け取るはずだった相続分になります。また、同一の本来相続人に複数の代襲相続人がいる場合は、その相続分を人数で等分します。
代襲相続分の計算例
例えば、被相続人に子A、子B、子C(死亡)がいて、子Cには子C-1、子C-2の2人の子(被相続人から見て孫)がいる場合の相続分は以下のようになります。
| 相続人 | 相続分 |
|---|---|
| 子A | 1/3 |
| 子B | 1/3 |
| 子C-1(孫) | 1/6(子Cの相続分1/3の半分) |
| 子C-2(孫) | 1/6(子Cの相続分1/3の半分) |
上記の表は代襲相続における相続分の具体的な計算例を示しています。代襲相続人は本来の相続人(親)の取り分を等分して相続します。
再代襲相続について
再代襲相続とは、代襲相続人となるべき人もまた被相続人より先に死亡している場合に、さらにその子が代襲相続する状況を指します。
子の場合は何世代でも代襲が認められるため、子→孫→ひ孫という具合に連続して代襲相続が発生することがあります。これを再代襲相続といいます。
- 本来の相続人(子)が死亡:子に代わって孫が代襲相続
- 代襲相続人(孫)も死亡:孫に代わってひ孫が再代襲相続
- 再代襲相続人(ひ孫)も死亡:さらにその子が代襲相続(子の場合は無制限に続く)
上記のリストは子の場合の再代襲相続の流れを示しています。子の場合は何世代でも代襲が認められますが、兄弟姉妹の場合は甥・姪までの1世代のみとなります。
養子と代襲相続
養子も実子と同様に相続権を持ち、養子が被相続人より先に死亡した場合、その実子(被相続人からみれば養孫)にも代襲相続権が発生します。
ただし、特別養子縁組の場合は実親との法的関係が終了するため、実親の相続において代襲相続権は発生しません。
| 普通養子縁組 |
|
|---|---|
| 特別養子縁組 |
|
上記の表は養子と代襲相続の関係を示しています。養子制度の種類によって相続関係に違いがありますが、いずれの場合も養親との関係では代襲相続が発生します。
よくある質問
Q1. 代襲相続人が相続放棄した場合、さらにその子に代襲相続権は移りますか?
いいえ、代襲相続人が相続放棄した場合、その効果はその人の子には及びません。相続放棄は本人の意思による選択であり、相続権自体は存在していたためです。
代襲相続が発生するのは「本来の相続人が被相続人より先に死亡した場合」など、相続権を取得する前に相続権が失われた場合に限られます。
Q2. 代襲相続人も遺留分を請求できますか?
はい、代襲相続人も本来の相続人と同様に遺留分を請求することができます。代襲相続人は本来の相続人と同じ法的地位を引き継ぐからです。
ただし、遺留分の割合については本来相続人が取得するはずだった相続分に応じて計算されます。
Q3. 兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲相続する場合、相続税の2割加算はありますか?
はい、兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲相続する場合も、被相続人からみて「一親等の血族及び配偶者以外の者」に該当するため、相続税の2割加算の対象となります。
代襲相続人は本来の相続人の地位を相続法上は引き継ぎますが、税法上の血族関係は実際の関係に基づいて判断されるためです。
Q4. 代襲相続と遺言はどちらが優先されますか?
原則として遺言が優先されます。被相続人が遺言で特定の相続人に財産を指定した場合、その指定は代襲相続よりも優先されます。
ただし、遺言で「子Aに相続させる」と指定した場合で、子Aが先に死亡していた場合は、解釈によって代襲相続が認められる場合もあります。
Q5. 代襲相続人も相続手続きに参加する必要がありますか?
はい、代襲相続人も他の相続人と同様に相続手続きに参加する必要があります。遺産分割協議では代襲相続人も含めた全相続人の合意が必要です。
また、相続税の申告・納付、預貯金の解約手続き、不動産の名義変更など、すべての相続手続きにおいて代襲相続人も相続人としての権利と義務を持ちます。
代襲相続人についてのまとめ
代襲相続人とは、本来相続人となるべき人が被相続人より先に死亡したり、相続欠格や廃除によって相続権を失った場合に、その人に代わって相続権を取得する人のことです。主に子や兄弟姉妹の直系卑属(子や孫など)が該当します。
代襲相続の範囲は相続人の種類によって異なり、子の場合は無制限に代襲が認められますが、兄弟姉妹の場合は1世代(甥・姪まで)に限られます。また、直系尊属や配偶者には代襲相続は認められていません。
代襲相続人の相続分は、本来の相続人が受け取るはずだった相続分となります。複数の代襲相続人がいる場合は、その相続分を人数で等分します。
代襲相続制度は、突然の不幸で親が先に亡くなった場合でも、その子や孫の相続権を保護するという重要な役割を果たしています。相続手続きを進める際には、代襲相続人の有無を確認し、適切に権利を保護することが大切です。






