生前贈与(せいぜんぞうよ)とは?
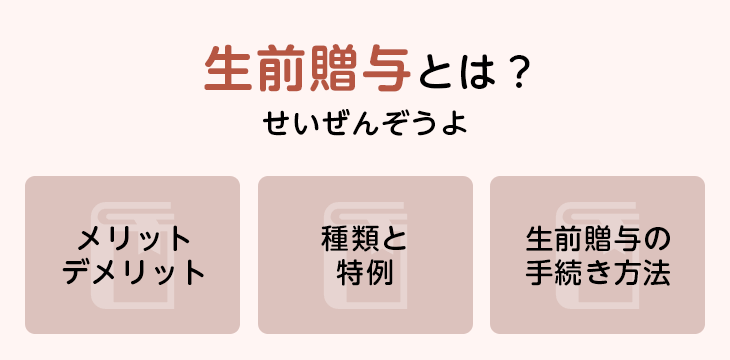
生前贈与とは、生きている間に自分の財産を他の人に無償で譲り渡すことを指します。相続対策として活用されることが多く、計画的に行うことで相続税の負担軽減が可能になります。
贈与税の基礎控除額(年間110万円)を活用しながら、少しずつ財産を移転することで、将来の相続税対策として効果的な方法です。
生前贈与の基本的な仕組み
生前贈与は、贈与者(財産を譲る人)から受贈者(財産を受け取る人)へ財産を移転する行為です。贈与が成立するためには、贈与者の「贈与する意思」と受贈者の「受け取る意思」が必要となります。
贈与税は暦年(1月1日から12月31日まで)ごとに計算され、毎年基礎控除額110万円が適用されます。この控除額を超えた部分に対して、贈与税が課税されます。
| 贈与税の基礎控除 | 年間110万円まで非課税 |
|---|---|
| 課税対象 | 基礎控除額を超える部分 |
| 申告期限 | 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで |
贈与税は相続税に比べて税率が高く設定されています。これは短期間での大量の財産移転による相続税回避を防ぐためです。
生前贈与のメリット
生前贈与を活用することには、いくつかの重要なメリットがあります。計画的に行うことで、相続対策として効果的に機能します。
- 相続財産の減少による相続税の軽減が可能
- 毎年の基礎控除(110万円)を活用できる
- 財産を早期に移転することで受贈者の生活基盤確立に役立つ
- 生前に財産分配の意思を明確にできる
- 相続争いの予防につながる
上記のメリットを活かすためには、計画的かつ継続的な贈与が重要です。特に相続税対策として行う場合は、長期的な視点での取り組みが効果的です。
生前贈与のデメリット
生前贈与にはメリットだけでなく、注意すべきデメリットもあります。贈与を検討する際には、これらのデメリットも十分に理解しておくことが大切です。
- 一度贈与すると原則として取り消しができない
- 相続税よりも贈与税の税率が高い場合がある
- 贈与から3年以内に贈与者が亡くなった場合、相続財産に加算される(相続時精算課税制度を除く)
- 受贈者の浪費や破産リスクがある
- 不動産など分割しにくい財産の場合、共有名義になるリスクがある
これらのデメリットを考慮し、専門家のアドバイスを受けながら、自分の状況に合った贈与計画を立てることが重要です。
生前贈与の種類と特例
生前贈与には通常の暦年贈与のほかに、いくつかの特例制度があります。それぞれの制度には特徴があり、状況に応じて選択することが重要です。
暦年贈与
暦年贈与は、毎年1月1日から12月31日までの間に、基礎控除額110万円までの贈与を非課税で行える一般的な贈与方法です。長期間にわたって計画的に行うことで、多額の財産移転が可能になります。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、60歳以上の親から18歳以上の子(または孫)への贈与に適用できる制度です。2,500万円までの特別控除があり、将来の相続時に相続財産と合算して相続税を計算します。
| 対象者 | 60歳以上の贈与者と18歳以上の子・孫 |
|---|---|
| 特別控除額 | 2,500万円(累計) |
| メリット |
|
この表は相続時精算課税制度の基本的な仕組みを示しています。この制度を選択すると、その後は暦年贈与に戻ることができないため、慎重な検討が必要です。
住宅取得資金贈与の非課税特例
親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受ける場合、一定条件を満たせば最大1,000万円(特定の省エネ住宅等では最大1,500万円)まで非課税となる特例です。
教育資金贈与の非課税特例
30歳未満の子や孫に対する教育資金の一括贈与について、1,500万円まで非課税とする特例です。金融機関に専用口座を開設し、教育費の支払いに充てる必要があります。
結婚・子育て資金贈与の非課税特例
20歳以上50歳未満の子や孫に対する結婚・子育て資金の一括贈与について、1,000万円まで非課税とする特例です。こちらも専用口座での管理が必要です。
生前贈与の手続き方法
生前贈与を行う際の基本的な手続きの流れを理解しておくことが重要です。特に贈与税の申告が必要な場合は、期限に注意が必要です。
- 贈与契約の締結:口頭でも成立しますが、トラブル防止のため書面での契約書作成がおすすめです
- 財産の移転:現金なら振込、不動産なら名義変更登記などの実質的な財産移転が必要です
- 贈与税の申告と納付:基礎控除額を超える場合、翌年の2月1日から3月15日までに申告・納税します
- 記録の保管:贈与契約書や振込記録、登記関係書類など証拠となる書類は大切に保管しましょう
上記は生前贈与の基本的な手続きの流れです。特に不動産や高額な贈与の場合は、専門家(税理士・司法書士など)に相談することをおすすめします。
よくある質問
Q1. 生前贈与は毎年いくらまで非課税ですか?
暦年贈与の場合、1月1日から12月31日までの1年間で、受贈者1人あたり110万円までが非課税となります。この基礎控除額を超えた部分に対して贈与税が課税されます。
Q2. 生前贈与をした財産は将来の相続財産に含まれますか?
暦年贈与の場合、贈与者が亡くなる前3年以内の贈与財産は「相続開始前3年以内の贈与」として相続財産に加算されます。相続時精算課税制度を選択した場合は、贈与時期に関わらず相続財産に加算されます。
Q3. 生前贈与は現金以外でもできますか?
はい、現金以外にも不動産、有価証券、美術品、宝飾品など様々な財産で贈与が可能です。ただし、現金以外の財産は時価評価が必要となり、贈与税の計算が複雑になる場合があります。
Q4. 生前贈与は取り消すことができますか?
原則として、一度成立した贈与は取り消すことができません。ただし、贈与者が贈与後に生活に困窮した場合や、受贈者が贈与者に対して著しい忘恩行為(恩を忘れた行為)を行った場合など、限られた状況では取り消しが認められることがあります。
Q5. 配偶者への贈与に特例はありますか?
配偶者控除として、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与について、最大2,000万円まで非課税となる特例があります。この特例は一生に一度しか利用できません。
まとめ
生前贈与は、生きている間に計画的に財産を移転することで、相続税対策や財産の早期移転による受贈者の生活基盤確立などのメリットがあります。毎年の基礎控除額110万円を活用した暦年贈与や、2,500万円の特別控除がある相続時精算課税制度など、状況に応じた選択が可能です。
ただし、一度贈与すると原則として取り消しができないことや、贈与税率が相続税率より高い場合があるなどのデメリットも理解しておく必要があります。特に高額な贈与や不動産など複雑な財産の贈与を検討する場合は、税理士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
生前贈与を効果的に活用するためには、贈与の目的を明確にし、長期的な視点で計画的に行うことが重要です。また、贈与契約書の作成や贈与税の申告など、適切な手続きを行うことで、将来のトラブルを防ぐことができます。






