贈与税(ぞうよぜい)とは?
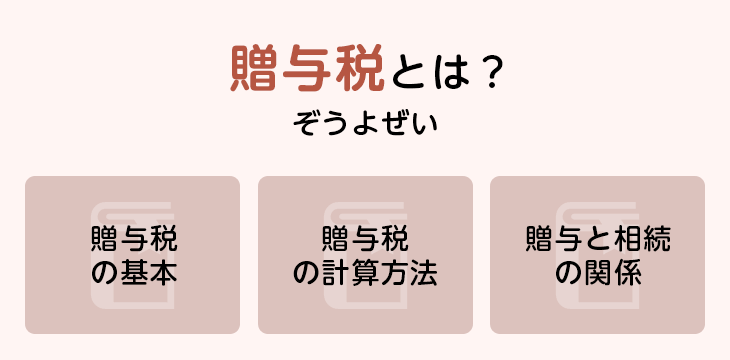
贈与税とは、個人から財産をもらった場合にかかる税金です。生前に財産を受け取った人(受贈者)に課税される税金で、相続税の補完税としての役割を持っています。
贈与税は相続税に比べて税率が高く設定されており、生前贈与による相続税の回避を防止する目的があります。毎年110万円までの基礎控除があり、この金額を超えた部分に対して課税されます。
贈与税の基本
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた金額に対して課税されます。贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに申告・納付する必要があります。
贈与とは、財産を無償で(対価を支払わずに)与えることをいいます。現金だけでなく、不動産や有価証券、美術品なども贈与税の対象となります。
| 贈与税の対象となるもの |
|
|---|---|
| 贈与税の対象とならないもの |
|
上記の表は贈与税の課税対象となる財産と対象とならない財産の例です。日常生活で必要な費用については贈与税はかかりませんが、それ以外の財産贈与には注意が必要です。
贈与税の計算方法
贈与税の計算方法は、贈与の種類によって異なります。一般的な贈与と特例贈与(特例税率が適用される贈与)の2種類があります。
一般贈与の税率
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 200万円超〜300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 300万円超〜400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 400万円超〜600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 600万円超〜1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超〜1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 1,500万円超〜3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
この表は一般贈与の税率表です。基礎控除額(110万円)を差し引いた後の課税価格に応じて、税率と控除額が定められています。課税価格が高くなるほど税率も上がる累進課税方式となっています。
特例贈与(直系尊属からの贈与)の税率
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 200万円超〜400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円超〜600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 600万円超〜1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,000万円超〜1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 1,500万円超〜3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 3,000万円超〜4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
この表は特例贈与(20歳以上の方が直系尊属から受ける贈与)の税率表です。一般贈与より税率が若干優遇されており、若年層の資産形成を支援する目的があります。
贈与税の計算方法は以下の通りです。
- その年に受けた贈与財産の価額を合計する
- 合計額から基礎控除額110万円を差し引く
- 残った金額(課税価格)に応じた税率を適用し、控除額を差し引く
- 計算式:贈与税額 = 課税価格 × 税率 - 控除額
上記の計算手順に従って贈与税額を算出します。贈与者と受贈者の関係によって適用される税率表が異なるため注意が必要です。
贈与税の特例制度
贈与税には様々な特例制度があり、条件を満たすことで税負担を軽減できます。主な特例制度は以下の通りです。
暦年贈与の特例
毎年110万円までの贈与は非課税になる制度です。複数年にわたって計画的に贈与することで、税負担を抑えながら財産を移転できます。
住宅取得等資金の贈与税の非課税特例
父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税になる特例です。住宅の質や消費税率によって非課税限度額が変わります。
| 区分 | 良質な住宅用家屋 | 左記以外の住宅用家屋 |
|---|---|---|
| 消費税率10%の住宅 | 1,000万円 | 500万円 |
| 消費税率8%の住宅 | 700万円 | 300万円 |
この表は令和5年の住宅取得等資金の贈与税非課税限度額を示しています。良質な住宅(省エネ性や耐震性に優れた住宅)ほど非課税限度額が大きくなっています。
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税特例
30歳未満の子や孫への教育資金の贈与について、1,500万円まで贈与税が非課税になる制度です。教育資金管理契約に基づき、金融機関に資金を預け入れる必要があります。
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税特例
20歳以上50歳未満の子や孫への結婚・子育て資金の贈与について、1,000万円まで贈与税が非課税になる制度です。専用口座を通じて資金を管理する必要があります。
配偶者控除(贈与税)
婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産や居住用不動産の購入資金の贈与があった場合、最高2,000万円まで贈与税が控除される制度です。
- 婚姻期間が20年以上であること
- 居住用不動産または居住用不動産の購入資金であること
- 贈与を受けた配偶者が贈与を受けた年の翌年3月15日までにその不動産に住んでいること
- 過去にこの特例の適用を受けていないこと
上記は贈与税の配偶者控除の適用条件です。夫婦間での住宅資金の移転をサポートする制度として活用されています。
贈与税の申告と納付
贈与税の申告と納付は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行う必要があります。申告が必要なのは、1年間の贈与財産の合計額が基礎控除額110万円を超える場合です。
申告手続きの流れ
- 贈与財産の価額を評価する:不動産や株式などは時価で評価します
- 贈与税申告書を作成する:必要事項を記入し、添付書類を準備します
- 納税地を管轄する税務署に申告書を提出する:郵送または電子申告も可能です
- 納税する:現金納付のほか、口座振替や電子納税も利用できます
上記の手順に従って、贈与税の申告と納付を行います。不動産などの評価額に不安がある場合は、税理士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
申告に必要な書類
| 主な必要書類 |
|
|---|
この表は贈与税申告時に必要な主な書類をまとめたものです。贈与財産の種類や適用する特例によって、必要書類が異なる場合があります。
贈与と相続の関係
贈与と相続には密接な関係があり、相続税対策として生前贈与が活用されることがあります。ただし、相続開始前の一定期間内の贈与については、相続財産に加算される制度があります。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、2,500万円までの特別控除を受けられる制度です。特別控除を超える部分には一律20%の税率で課税されます。
この制度を選択すると、贈与財産は将来の相続財産に加算されて相続税が計算されます。すでに納付した贈与税は相続税から控除されるため、二重課税は生じません。
死亡前3年以内の贈与
被相続人の死亡前3年以内に行われた贈与は、相続財産に加算して相続税を計算します。これは、相続税回避目的の生前贈与を防止するための制度です。
ただし、暦年課税の基礎控除(年間110万円)の範囲内の贈与については、この加算の対象外となります。
生前贈与と相続税対策
計画的な生前贈与は、相続税の負担を軽減する効果があります。毎年の基礎控除や各種特例を活用することで、資産を徐々に移転することができます。
ただし、贈与税と相続税の税率構造や各種特例を考慮した上で、総合的な判断が必要です。家族構成や資産状況に応じた適切な対策を立てるためには、専門家への相談が有効です。
よくある質問
Q1. 親から毎月お小遣いをもらっていますが、贈与税はかかりますか?
生活費や教育費として通常必要と認められる金額については、贈与税はかかりません。ただし、金額が高額で明らかに生活費を超える場合は、贈与税の対象となる可能性があります。
Q2. 贈与税の申告を忘れていた場合はどうなりますか?
申告期限後に自主的に申告・納付する場合は、無申告加算税(15%または20%)と延滞税がかかります。税務署の調査により発覚した場合は、無申告加算税が25%に引き上げられることがあります。早めに専門家に相談することをおすすめします。
Q3. 夫婦間の贈与も課税対象になりますか?
はい、夫婦間の贈与も贈与税の対象です。ただし、婚姻期間が20年以上の場合は、居住用不動産等の贈与について最高2,000万円まで控除される配偶者控除の特例があります。
Q4. 相続時精算課税制度と暦年課税はどちらが有利ですか?
資産の額や種類、将来の相続税率などによって異なります。一般的に、将来値上がりが見込まれる資産や高額な資産の贈与には相続時精算課税制度が有利な場合があります。一方、少額の贈与を長期間にわたって行う場合は暦年課税が有利なことが多いです。
Q5. 海外在住の親族からの贈与も課税対象になりますか?
日本に住所がある人(居住者)が、国内外の親族から受けた贈与は、すべて日本の贈与税の対象となります。また、日本国籍を持つ非居住者が日本国内の財産を贈与された場合も課税対象です。国際的な贈与には複雑なルールがあるため、専門家への相談が必要です。
まとめ
贈与税は、個人から財産をもらった場合にかかる税金で、相続税の補完税としての役割を持っています。基礎控除額は年間110万円で、これを超える部分に10%〜55%の累進税率で課税されます。
贈与税には様々な特例制度があり、住宅取得資金や教育資金の贈与、配偶者間の居住用不動産の贈与などについては、一定の条件を満たせば税負担が軽減されます。
また、相続時精算課税制度を選択すると、2,500万円までの特別控除が受けられますが、将来の相続財産に加算されて相続税が計算されます。
贈与税の申告と納付は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行う必要があります。贈与契約書の作成や財産評価など、適切な手続きを踏むことが大切です。
生前贈与は相続税対策として有効ですが、贈与税と相続税のバランスを考慮した総合的な計画が必要です。家族構成や資産状況に応じた最適な対策を立てるためには、税理士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。






