相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)とは?
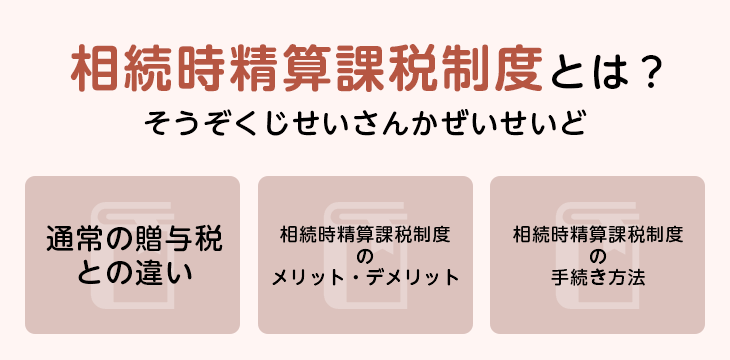
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子や孫への生前贈与に対して特別な税制優遇を受けられる制度です。贈与時に一定額までは非課税となり、相続発生時に贈与財産と相続財産を合算して相続税を計算する仕組みとなっています。
この制度を利用すると、2,500万円までの贈与については贈与税が非課税となり、それを超える部分には一律20%の贈与税が課税されます。相続時には、これまでの贈与財産と相続財産を合計して相続税を計算するため、計画的な資産移転が可能になります。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度は、2003年(平成15年)に導入された、生前贈与と相続を一体化して課税する制度です。この制度を選択すると、贈与時に特別控除額2,500万円までの贈与については贈与税が非課税となります。
特別控除額を超える部分については、一律20%の税率で贈与税が課されます。これは通常の贈与税の累進税率(最高55%)と比較すると、高額な贈与の場合に税負担が軽減される可能性があります。
この制度の最大の特徴は、贈与者(親や祖父母)が亡くなった際に、それまでの贈与財産と相続財産を合算して相続税を計算する点です。贈与時に支払った贈与税は相続税から控除されるため、二重課税を防ぐ仕組みになっています。
| 相続時精算課税制度の特徴 |
|
|---|
上記の特徴から、将来的に相続税の課税対象となる可能性が高い方や、計画的な資産移転を考えている方にとって有効な制度といえます。
相続時精算課税制度の適用条件
相続時精算課税制度を利用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。贈与者と受贈者の両方に条件があるため、事前に確認しておきましょう。
贈与者(親・祖父母)の条件
- 60歳以上の父母または祖父母であること
- 贈与の年の1月1日現在の年齢で判断
- 日本国内に住所を有する者(または過去10年以内に日本国内に住所を有していた者)
贈与者の条件としては、60歳以上の父母または祖父母である必要があります。また、基本的には日本国内に住所を有している必要がありますが、過去10年以内に日本国内に住所を有していた場合も対象となります。
受贈者(子・孫)の条件
- 20歳以上の子または孫であること
- 贈与の年の1月1日現在の年齢で判断
- 日本国内に住所を有する者
受贈者の条件としては、20歳以上の子または孫である必要があります。また、日本国内に住所を有している必要があります。養子も対象となりますが、特別養子縁組による養子以外の養子は1人までとされています。
その他の条件
相続時精算課税制度を選択するには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の申告とともに「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
また、一度この制度を選択すると、その贈与者からの贈与については、以後すべてこの制度が適用され、通常の贈与税制度(暦年課税)に戻すことはできません。
通常の贈与税との違い
相続時精算課税制度と通常の贈与税(暦年課税)には大きな違いがあります。どちらが有利かは家族の状況や資産状況によって異なるため、比較して検討することが重要です。
| 比較項目 | 暦年課税(通常の贈与税) | 相続時精算課税制度 |
|---|---|---|
| 非課税枠 | 年間110万円まで | 2,500万円まで(一生涯の累計) |
| 税率 | 10%~55%の累進税率 | 2,500万円超の部分は一律20% |
| 相続との関係 | 相続開始前3年以内の贈与のみ相続財産に加算 | すべての贈与財産を相続財産に加算 |
| 制度選択 | 毎年選択可能 | 一度選択すると変更不可 |
| 適用対象者 | 制限なし | 60歳以上の親・祖父母から20歳以上の子・孫へ |
上記の表は、相続時精算課税制度と暦年課税(通常の贈与税)の主な違いを比較したものです。非課税枠や税率、相続との関係など、多くの点で異なります。
相続時精算課税制度のメリット・デメリット
相続時精算課税制度には、様々なメリットとデメリットがあります。自分の状況に合わせて検討することが大切です。
メリット
- 2,500万円までの贈与が非課税:一度に多額の財産を移転する場合に有利です。
- 計画的な財産移転が可能:生前に財産を移転することで、相続手続きの負担軽減につながります。
- 不動産など高額資産の贈与に有効:一度に大きな財産を贈与する場合に税負担を抑えられます。
- 将来値上がりが見込める資産の早期移転:値上がりする前に移転することで、将来の税負担を軽減できます。
上記のように、まとまった資産を計画的に移転したい場合や、将来値上がりが見込める資産を早期に移転したい場合などに大きなメリットがあります。
デメリット
- 一度選択すると撤回不可:制度選択後は、同じ贈与者からの贈与はすべてこの制度が適用されます。
- 贈与時の評価額で相続税計算:贈与後に資産価値が下落しても、贈与時の評価額で相続税が計算されます。
- 相続時に贈与財産が加算される:相続税の課税対象が増えるため、相続税の総額が増加する可能性があります。
- 基礎控除や配偶者控除などが適用できない:暦年課税で利用できる控除が使えない場合があります。
特に注意すべき点として、一度この制度を選択すると撤回できないことや、贈与時の評価額で相続税が計算されることが挙げられます。資産価値が下落するリスクがある場合は慎重に検討する必要があります。
相続時精算課税制度の手続き方法
相続時精算課税制度を利用するためには、適切な手続きを行う必要があります。基本的な流れは以下の通りです。
- 贈与の実行:贈与契約を締結し、実際に財産を移転します。
- 必要書類の準備:戸籍謄本、住民票、贈与財産の評価資料などを準備します。
- 申告書の作成:贈与税申告書と相続時精算課税選択届出書を作成します。
- 税務署への提出:贈与を受けた年の翌年の3月15日までに提出します。
- 贈与税の納付:2,500万円を超える部分については、一律20%の贈与税を納付します。
上記の手続きを正確に行うことが重要です。特に初めて相続時精算課税制度を選択する場合は、「相続時精算課税選択届出書」の提出を忘れないようにしましょう。
必要書類一覧
| 必要書類 | 内容・注意点 |
|---|---|
| 贈与税申告書 | 相続時精算課税用の申告書を使用 |
| 相続時精算課税選択届出書 | 初回のみ提出が必要(同じ贈与者からの2回目以降は不要) |
| 戸籍謄本 | 贈与者と受贈者の続柄を証明するもの |
| 贈与者の住民票 | 贈与者が60歳以上であることを証明 |
| 受贈者の住民票 | 受贈者が20歳以上であることを証明 |
| 贈与財産の評価資料 | 不動産の場合は固定資産評価証明書など |
上記の書類を準備して税務署に提出することで、相続時精算課税制度を利用することができます。不明点がある場合は、税理士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
よくある質問
Q1. 相続時精算課税制度と暦年課税は併用できますか?
同一の贈与者からの贈与については併用できません。一度相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者からの贈与はすべてこの制度が適用されます。
ただし、異なる贈与者からの贈与については、別々の制度を選択することが可能です。例えば、父からの贈与には相続時精算課税制度を選択し、母からの贈与には暦年課税を選択するといったことができます。
Q2. 2,500万円の特別控除は夫婦でそれぞれ利用できますか?
はい、夫婦それぞれが贈与者となる場合、それぞれに2,500万円の特別控除を利用することができます。つまり、夫婦合わせて最大5,000万円までの贈与が非課税となる可能性があります。
ただし、贈与を受ける側(子や孫)ごとに控除額が設定されるわけではないので注意が必要です。一人の贈与者からの贈与について、複数の受贈者で2,500万円を分け合うことになります。
Q3. 相続時精算課税制度を選択した場合、毎年の贈与税申告は必要ですか?
贈与を受けた年の合計額が特別控除額(2,500万円)以下であっても、毎年贈与税の申告を行う必要があります。これは、将来の相続税計算の基礎となる贈与財産の記録を残すためです。
贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行いましょう。ただし、特別控除額以下の場合は贈与税の納付は不要です。
Q4. 相続時精算課税制度を利用した場合、相続税はどのように計算されますか?
相続時精算課税制度を利用した場合、相続時には以下の手順で相続税が計算されます。
- 相続財産に贈与財産を加算して課税価格を算出
- 通常の相続税の計算方法で税額を算出
- 既に納付した贈与税額を控除
- 最終的な納付税額を確定
この計算方法により、贈与時と相続時の二重課税を防ぐ仕組みとなっています。ただし、贈与時の財産評価額が相続時の計算に使用されるため、資産価値の変動には注意が必要です。
Q5. 相続時精算課税制度を選択した後、贈与者が亡くなるまでに制度が変更された場合はどうなりますか?
原則として、贈与時の制度が適用されます。ただし、税制改正により明確に経過措置が設けられた場合は、その内容に従うことになります。
将来の税制改正によるリスクは完全に排除できないため、長期的な視点で検討する必要があります。不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子・孫への贈与に適用できる特別な税制です。2,500万円までの贈与が非課税となり、それを超える部分には一律20%の贈与税が課されます。
この制度の最大の特徴は、贈与財産と相続財産を合算して相続税を計算する点です。一度選択すると撤回できないため、家族の状況や資産状況を考慮して慎重に検討する必要があります。
制度のメリットとしては、まとまった資産を一度に移転できること、将来値上がりが見込める資産の早期移転に有効なことなどが挙げられます。一方、デメリットとしては、撤回できないこと、贈与時の評価額で相続税が計算されることなどがあります。
相続時精算課税制度を利用する場合は、贈与税の申告と「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。不明点がある場合は、税理士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
将来の相続に備えて計画的な資産移転を考えている方は、この制度の活用を検討してみてはいかがでしょうか。ただし、家族構成や資産状況によって最適な選択は異なるため、自分の状況に合わせた判断が重要です。






