積極財産(せっきょくざいさん)とは?
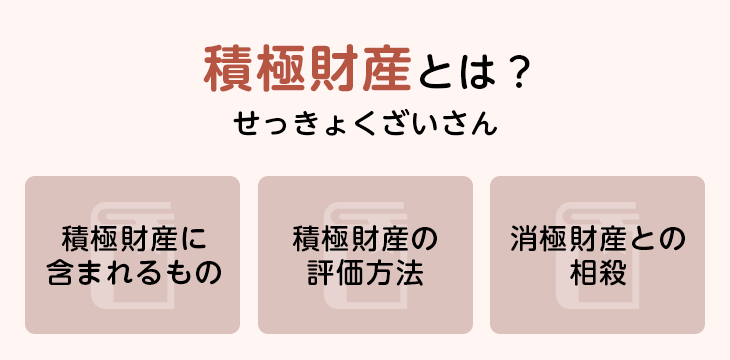
積極財産とは、相続の際に被相続人(亡くなった方)から相続人に引き継がれる「プラスの財産」のことです。
現金や預貯金、不動産、有価証券などの資産がこれに該当します。相続財産は積極財産と消極財産(借金などのマイナスの財産)に分けられ、その差額が実際の相続対象となります。
積極財産の基本的な概念
相続が発生すると、被相続人の財産は相続人に引き継がれます。この時、財産は「積極財産」と「消極財産」の2種類に分類されます。積極財産は、プラスの価値を持つ資産を指します。
相続の際には、積極財産から消極財産を差し引いた「正味の遺産」が実際の相続対象となります。例えば、積極財産が5,000万円、消極財産が1,000万円の場合、正味の遺産は4,000万円となります。
積極財産は、相続税の計算基礎となるため、正確に把握することが重要です。相続開始時(被相続人の死亡時点)の時価で評価されるのが原則です。
積極財産に含まれるもの
積極財産には様々な種類があります。主なものを以下にまとめました。
| 現金・預貯金 | 現金、普通預金、定期預金、外貨預金など |
|---|---|
| 不動産 | 土地、建物、マンション、賃貸アパートなど |
| 有価証券 | 株式、投資信託、国債、社債など |
| 事業用資産 | 自営業や経営者が所有する事業用の機械設備、商品、営業権など |
| 生命保険金 | 契約者が被相続人で、受取人が相続人の場合の死亡保険金(みなし相続財産) |
| 退職金・功労金 | 被相続人に支給される退職金や功労金(みなし相続財産) |
| 動産 | 自動車、貴金属、美術品、骨董品、家財道具など |
| 知的財産権 | 特許権、著作権、商標権など |
上記の表は主な積極財産の種類を示しています。実際の相続では、これらの財産を漏れなく把握することが重要です。
みなし相続財産について
生命保険金や退職金などは、法律上は相続財産ではありませんが、相続税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。これらも積極財産として取り扱われます。
例えば、生命保険金は契約によって受取人に直接支払われるため、相続財産ではありませんが、相続税の計算では積極財産に含まれます。ただし、一定金額までは非課税となる特例があります。
積極財産の評価方法
相続税の計算において、積極財産は原則として相続開始時の「時価」で評価します。ただし、財産の種類によって評価方法が異なります。
- 現金・預貯金:額面金額(外貨の場合は相続開始時のレートで換算)
- 不動産:路線価方式または倍率方式で評価
- 上場株式:相続開始前後の一定期間の平均価格
- 非上場株式:純資産価額方式や類似業種比準方式など
- 美術品・骨董品:鑑定評価額や購入価格
上記のリストは主な積極財産の評価方法です。特に不動産や非上場株式の評価は複雑なため、専門家への相談がおすすめです。
不動産の評価方法について
不動産は相続財産の中でも大きな割合を占めることが多く、その評価方法は重要です。土地は主に「路線価方式」または「倍率方式」で評価されます。
| 路線価方式 | 国税庁が毎年発表する路線価に基づいて評価する方法。主に市街地で用いられます。 |
|---|---|
| 倍率方式 | 固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価する方法。路線価が設定されていない地域で用いられます。 |
| 建物の評価 | 固定資産税評価額が基本となりますが、築年数による減価償却も考慮されます。 |
不動産の評価額は、実際の市場価格より低くなることが多いですが、適正な評価を行うことが重要です。評価が低すぎると、後に税務調査で指摘される可能性があります。
相続税の計算と積極財産
相続税は、積極財産の合計額から基礎控除額を差し引いた金額に対して課税されます。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
- 積極財産の合計額を算出:すべての積極財産を評価し合計する
- 債務控除を適用:積極財産から消極財産(債務・葬式費用)を差し引く
- 非課税財産を除外:墓地や仏壇など非課税となる財産を除外する
- 生前贈与加算:相続開始前3年以内の贈与財産を加算する
- 基礎控除額を差し引く:「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
- 課税遺産総額に税率を適用:税率は10%〜55%の累進税率
上記のリストは相続税計算の基本的な流れです。積極財産の把握が不十分だと、相続税の計算も正確にできないため、専門家のサポートを受けることがおすすめです。
積極財産と消極財産の相殺
相続では、積極財産から消極財産を差し引いた「正味の遺産」が実際の相続対象となります。消極財産には、被相続人の借金、未払い税金、葬式費用などが含まれます。
例えば、被相続人に住宅ローンが残っている場合、不動産という積極財産と住宅ローンという消極財産が相殺されます。消極財産が積極財産を上回る場合は「債務超過」となり、相続放棄を検討する必要があるかもしれません。
| 消極財産の例 |
|
|---|
上記の表は主な消極財産の例です。これらは積極財産から差し引くことができますが、適切な証拠書類が必要です。
よくある質問
Q1. 生前贈与した財産も積極財産に含まれますか?
原則として、生前贈与された財産は相続財産には含まれません。ただし、相続開始前3年以内に贈与された財産は「相続時精算課税制度」を選択していなくても、相続税の計算上は積極財産に加算されます。また、「相続時精算課税制度」を選択していた場合は、いつ贈与されたものでも相続財産に加算されます。
Q2. 海外にある財産も積極財産に含まれますか?
はい、被相続人が日本国籍を持ち日本に住所がある場合、海外にある財産も含めて全世界の財産が相続税の対象となります。海外の預金や不動産なども積極財産として申告する必要があります。ただし、外国にも相続税がある場合は、二重課税を調整する外国税額控除の制度があります。
Q3. 生命保険金はすべて積極財産になりますか?
生命保険金は「みなし相続財産」として積極財産に含まれますが、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。例えば、法定相続人が3人の場合、1,500万円までの生命保険金は相続税がかかりません。この非課税枠を超えた分が積極財産として相続税の対象となります。
Q4. 家財道具も積極財産として評価されますか?
日常的に使用する家財道具は、通常は少額なものとして相続税の申告では省略されることが多いです。ただし、美術品や骨董品、貴金属など高額なものは積極財産として評価・申告する必要があります。一般的には、1点あたり30万円を超えるものは申告対象と考えられています。
Q5. 積極財産の評価を下げる方法はありますか?
法律の範囲内で積極財産の評価を適正に行うことは重要です。例えば、不動産の場合、建物の老朽化や欠陥を証明できれば評価額が下がることがあります。また、小規模宅地等の特例など各種の特例措置を活用することで、相続税の負担を軽減できる場合があります。ただし、不当に評価を下げることは税務調査の対象となる可能性があるため、専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
積極財産とは、相続において被相続人から相続人に引き継がれるプラスの価値を持つ財産のことです。現金や預貯金、不動産、有価証券などがこれに該当します。相続税の計算において、積極財産は正確に把握し、適正に評価することが重要です。
積極財産から消極財産(借金など)を差し引いた「正味の遺産」が実際の相続対象となります。財産の種類によって評価方法が異なり、特に不動産や非上場株式の評価は複雑なため、専門家のアドバイスを受けることがおすすめです。
また、生命保険金や退職金などの「みなし相続財産」や、相続開始前3年以内の生前贈与も積極財産に含まれる点にも注意が必要です。相続税の計算では、積極財産の合計額から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた金額に対して課税されます。
相続に関する知識を深め、適切な相続対策を行うことで、相続税の負担を軽減し、円滑な財産承継を実現することができます。複雑な相続手続きや税金の計算については、税理士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。






