指定相続分(していそうぞくぶん)とは?
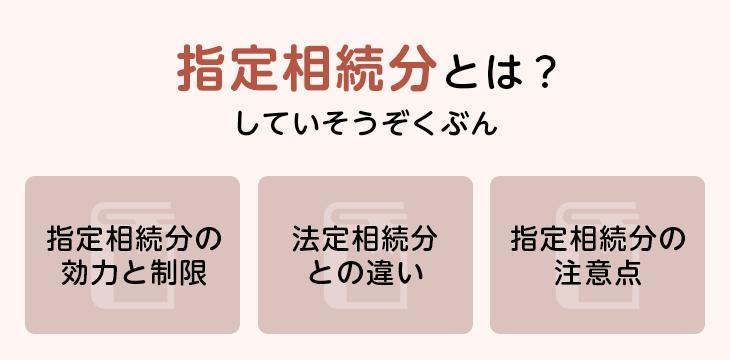
指定相続分とは、被相続人が遺言によって法定相続分と異なる割合で財産を分割するよう指定することをいいます。民法第902条に規定されており、被相続人の意思を尊重するための制度です。
法定相続分では相続人それぞれの取り分が法律で決められていますが、指定相続分では被相続人の意思によって自由に割合を決めることができます。
指定相続分の基本
指定相続分とは、被相続人(亡くなった方)が遺言によって、法律で定められた相続分とは異なる割合で相続財産を分けることができる制度です。この制度により、被相続人は自分の財産をどのように分配したいかという意思を実現することができます。
例えば、子供が3人いる場合の法定相続分は各3分の1ずつですが、指定相続分を使えば「長男に2分の1、次男に4分の1、長女に4分の1」というように、被相続人の意思で自由に割合を変えることが可能です。
| 根拠法 | 民法第902条(相続分の指定) |
|---|---|
| 指定方法 |
|
指定相続分は必ず遺言書によって行わなければならず、口頭での約束や遺言以外の文書では法的効力は認められません。遺言書の形式は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれでも可能です。
法定相続分との違い
法定相続分と指定相続分の大きな違いは、相続分を決める主体にあります。法定相続分は法律によって一律に定められた割合であるのに対し、指定相続分は被相続人の意思によって自由に決めることができます。
| 法定相続分 |
|
|---|---|
| 指定相続分 |
|
上記の表は法定相続分と指定相続分の違いを示しています。法定相続分は民法によって定められた固定の割合ですが、指定相続分では被相続人の意思によって柔軟に割合を決めることができます。
指定相続分の効力と制限
指定相続分は被相続人の意思を尊重する制度ですが、完全に自由というわけではなく、いくつかの制限があります。最も重要な制限は「遺留分」です。
遺留分による制限
遺留分とは、一定の相続人(配偶者、子、直系尊属)に保障された最低限の相続分のことです。遺留分権利者は、指定相続分によって遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
| 遺留分の割合 |
|
|---|---|
| 遺留分権利者 |
|
上記の表は遺留分の割合と遺留分権利者を示しています。指定相続分によって遺留分を下回る相続分を指定された相続人は、遺留分侵害額請求によって最低限の相続分を確保する権利があります。
指定相続分の効力範囲
指定相続分の効力は、特に指定がない限り、相続財産全体に及びます。ただし、特定の財産についてのみ指定することや、相続人の一部についてのみ指定することも可能です。
- 一部の相続人だけに指定した場合、指定のない相続人は法定相続分に従って相続
- 一部の財産だけに指定した場合、指定のない財産は法定相続分に従って相続
- 相続分の合計が1(100%)を超える場合、各相続人の指定相続分は比例的に減少
- 相続分の合計が1(100%)に満たない場合、残りは法定相続分に従って分配
上記のリストは指定相続分の効力範囲についての重要なポイントを示しています。指定相続分は柔軟に設定できますが、指定がない部分については法定相続分が適用されます。
指定相続分の遺言書の書き方
指定相続分を有効に指定するためには、適切な遺言書の作成が必要です。遺言書は法律で定められた形式に従って作成しなければ無効となります。
指定相続分の記載例
| 割合による指定例 | 「私の相続財産について、妻○○に2分の1、長男△△に4分の1、次男□□に4分の1の割合で相続させる。」 |
|---|---|
| 具体的な財産による指定例 | 「私の所有する○○市△△町□□番地の土地および同所の建物は、長男○○に相続させる。預貯金は妻△△と次男□□で均等に分けて相続させる。」 |
上記の表は指定相続分を遺言書に記載する際の例文を示しています。割合による指定と具体的な財産による指定のどちらの方法も有効です。
- 遺言書の形式を選ぶ:自筆証書遺言か公正証書遺言か秘密証書遺言かを選択します
- 相続人の特定:相続人全員の氏名、続柄を明確に記載します
- 相続分の指定:各相続人の相続分を明確な割合または具体的な財産で指定します
- 日付の記入:遺言書作成の年月日を記入します
- 署名・押印:自筆証書遺言の場合は、署名および押印が必要です
上記のリストは指定相続分の遺言書を作成する際の基本的な流れを示しています。公正証書遺言であれば、公証人が正確な作成をサポートしてくれるため、専門知識がなくても安心です。
指定相続分に関する注意点
指定相続分を活用する際には、いくつかの重要な注意点があります。これらを理解せずに遺言を作成すると、トラブルの原因となることがあります。
遺留分侵害のリスク
遺留分権利者の遺留分を侵害するような指定相続分を設定した場合、相続開始後に遺留分侵害額請求をされる可能性があります。これにより、被相続人の意図した相続分の実現が困難になることがあります。
遺留分を考慮した指定相続分の設定や、生前に相続人から遺留分放棄の手続きを行ってもらうなどの対策が考えられます。
相続税への影響
指定相続分によって相続財産の分配が法定相続分と異なる場合でも、相続税の計算上の基礎控除額は法定相続人の数に基づいて計算されます。ただし、実際の課税額は各人が取得した財産価額に応じて計算されます。
指定相続分によって特定の相続人に財産が集中すると、相続税の累進税率の影響で、全体としての税負担が増える可能性があることに注意が必要です。
遺言の解釈をめぐる紛争
指定相続分の内容が曖昧だと、相続人間で遺言の解釈をめぐって争いが生じる可能性があります。例えば「多めに相続させる」といった表現は具体的な割合が不明確なため、紛争の原因となります。
争いを防ぐためには、相続分を明確な数字や具体的な財産で指定することが重要です。また、公正証書遺言を利用すれば、専門家のサポートにより明確な表現での遺言作成が可能です。
よくある質問
Q1. 指定相続分と遺産分割方法の指定の違いは何ですか?
指定相続分は相続財産全体における各相続人の取り分の割合を指定するものです。一方、遺産分割方法の指定は、具体的にどの財産を誰に相続させるかを指定するものです。
例えば「長男に相続財産の3分の2、次男に3分の1」と指定するのが指定相続分、「不動産は長男に、預貯金は次男に相続させる」と指定するのが遺産分割方法の指定となります。
Q2. 相続人の一部を相続から外すことはできますか?
遺言によって相続分を0と指定することで、実質的に相続から外すことは可能です。ただし、配偶者、子、直系尊属には遺留分があるため、遺留分侵害額請求をされる可能性があります。
兄弟姉妹には遺留分がないため、兄弟姉妹については相続分を0と指定しても、遺留分侵害の問題は生じません。
Q3. 指定相続分の遺言は自分で書いても有効ですか?
自筆証書遺言として、法律で定められた形式に従って自分で書けば有効です。全文を自筆で書き、日付を記入し、署名・押印する必要があります。
ただし、自筆証書遺言は形式不備で無効になるリスクがあるため、重要な内容の場合は公正証書遺言の利用がおすすめです。また、2020年7月からは法務局での自筆証書遺言書の保管制度も始まっています。
Q4. 指定相続分の効力はいつから発生しますか?
指定相続分の効力は被相続人の死亡時(相続開始時)から発生します。生前に遺言書を作成していても、被相続人が生きている間は効力がありません。
また、遺言書は撤回・変更が可能なため、最新の遺言が有効となります。複数の遺言書がある場合は、原則として最新のものが優先されます。
Q5. 指定相続分を定めた遺言書が見つからない場合はどうなりますか?
遺言書が見つからない場合や、遺言書が無効とされた場合は、法定相続分に従って相続が行われます。遺言の存在を主張する側が、その存在と内容を証明する必要があります。
遺言書の紛失リスクを避けるためには、公正証書遺言の利用や、自筆証書遺言を法務局で保管する制度の利用がおすすめです。
指定相続分についてのまとめ
指定相続分は、被相続人が遺言によって法定相続分とは異なる割合で財産を分配できる制度です。この制度によって、被相続人は自分の意思に基づいた財産分配を実現することができます。
指定相続分を活用する際の重要なポイントは、適切な遺言書の作成です。遺言書は法律で定められた形式に従って作成する必要があり、明確な表現で相続分を指定することが紛争防止のために重要です。
また、遺留分の制限に注意する必要があります。遺留分権利者(配偶者、子、直系尊属)には最低限の相続分が保障されているため、指定相続分がこれを侵害すると、後に遺留分侵害額請求をされる可能性があります。
指定相続分は、被相続人の意思を尊重しつつも相続人の権利も保護するバランスの取れた制度です。複雑なケースでは専門家に相談し、円滑な相続の実現を目指すことがおすすめです。






