除籍謄本(じょせきとうほん)とは?
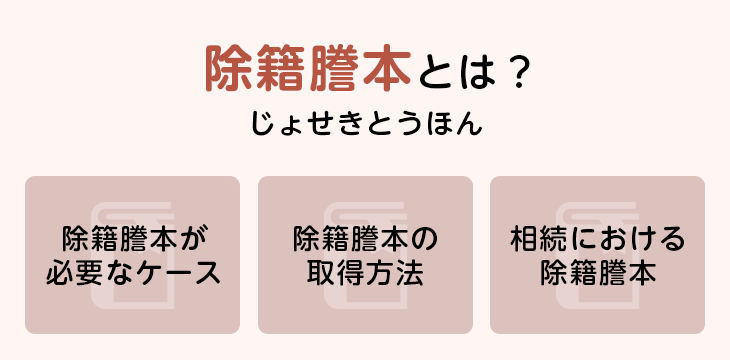
除籍謄本とは、戸籍から除かれた方(死亡や海外への転籍など)に関する戸籍情報を記載した公文書です。相続手続きでは、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍情報を収集する「戸籍収集」において重要な書類となります。
除籍謄本は相続人確定の証明書類として必須であり、相続手続きを円滑に進めるためには正しい知識を持っておくことが大切です。
除籍謄本とは
除籍謄本とは、すでに戸籍から除かれた人の戸籍情報を記載した公文書です。戸籍から除かれる原因としては、死亡、結婚(女性の場合は夫の戸籍に入る場合)、海外への転籍、帰化などがあります。
現在の戸籍には記載されていない過去の情報を確認するために利用され、特に相続手続きでは重要な役割を果たします。除籍謄本には本籍地、筆頭者、家族構成、出生、婚姻、死亡などの情報が記載されています。
除籍謄本に記載されている内容
| 基本情報 | 本籍地、筆頭者名、戸籍番号 |
|---|---|
| 身分事項 |
|
| 除籍理由 | 死亡、婚姻による転籍、海外への転出など |
| 除籍年月日 | 戸籍から除かれた日付 |
除籍謄本には上記のような情報が記載されており、被相続人の家族関係や財産権の継承者を特定するための重要な手がかりとなります。
除籍謄本が必要となるケース
除籍謄本は様々な場面で必要となりますが、特に相続手続きにおいては欠かせない書類です。以下のようなケースで必要となります。
上記のケースでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍情報を収集する必要があり、その過程で除籍謄本の取得が必要になることがあります。特に被相続人が何度か転籍を繰り返している場合は、すべての戸籍を追跡するために複数の除籍謄本が必要となることもあります。
除籍謄本の取得方法
除籍謄本は、その戸籍が保管されている市区町村役場で取得することができます。取得手続きは以下の流れで行います。
- 取得場所:除籍された本籍地の市区町村役場(戸籍課・市民課)
- 必要書類:本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 請求者の制限:直系尊属・卑属、配偶者のみ請求可能
- 手数料:1通750円程度(自治体により異なる場合あり)
- 交付方法:窓口での直接受け取り、郵送での請求も可能
除籍謄本の請求権者は制限されており、基本的には本人、配偶者、直系尊属(親・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)のみが請求できます。第三者による請求の場合は、正当な理由と委任状が必要です。
郵送での請求方法
遠方に住んでいる場合は、郵送での請求も可能です。郵送で請求する場合は、以下の書類を準備して請求先の市区町村役場に送付します。
| 必要書類 |
|
|---|---|
| 請求に必要な情報 |
|
郵送での請求は、書類の到着から処理、返送までに1〜2週間程度かかる場合がありますので、余裕を持って請求することをおすすめします。
除籍謄本と改製原戸籍の違い
戸籍関係の書類には似たような名称があり混同しやすいですが、除籍謄本と改製原戸籍は異なる書類です。それぞれの違いを理解しておきましょう。
| 除籍謄本 | 死亡や転籍などにより戸籍から除かれた人の戸籍情報が記載された書類 |
|---|---|
| 改製原戸籍 | 戸籍制度の改正により新しい様式に書き換えられる前の旧戸籍の写し |
| 主な違い |
|
相続手続きでは、被相続人の戸籍情報をたどる際に両方の書類が必要になることがあります。特に明治時代や大正時代に生まれた被相続人の場合、戸籍制度の変遷により複数の改製原戸籍と除籍謄本が存在することがあります。
相続における除籍謄本の重要性
相続手続きにおいて、除籍謄本は以下のような重要な役割を果たします。
法定相続人の確定
除籍謄本は、被相続人の婚姻歴や子の出生など、法定相続人を確定するための重要な情報を提供します。特に被相続人に複数の婚姻歴がある場合や、養子縁組などの身分変動がある場合は、除籍謄本の確認が不可欠です。
相続手続きに必要な書類として
相続登記や預貯金の名義変更、相続税の申告など、様々な相続手続きにおいて、法定相続人であることを証明するために除籍謄本が必要となります。金融機関や法務局など、手続き先によって要求される書類が異なる場合がありますので、事前に確認することをおすすめします。
戸籍の連続性の証明
相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍の連続性を証明する必要があります。特に本籍地の変更があった場合は、除籍謄本を通じて戸籍の移動を追跡することが重要です。
すべての相続手続きを円滑に進めるためには、被相続人の戸籍情報を正確に把握することが大切です。そのため、相続が発生した場合は、早めに除籍謄本を含む必要書類を収集することをおすすめします。
よくある質問
Q1. 除籍謄本はどこで取得できますか?
除籍謄本は、除籍された方の最後の本籍地があった市区町村役場(戸籍課・市民課)で取得できます。現在の本籍地と除籍された時の本籍地が異なる場合は、除籍された時の本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。
Q2. 除籍謄本の取得に必要な費用はいくらですか?
除籍謄本の発行手数料は自治体によって異なりますが、一般的に1通750円程度です。郵送で請求する場合は、手数料に加えて返信用封筒の切手代が必要です。
Q3. 亡くなった祖父の除籍謄本を取得することはできますか?
祖父は直系尊属にあたるため、孫である請求者は取得することができます。請求の際は、本人確認書類と祖父との関係性を証明する戸籍謄本等の提示が必要な場合があります。
Q4. 相続手続きで除籍謄本は何通必要ですか?
相続手続きで必要な除籍謄本の通数は、手続きの種類や金融機関・法務局などの要求によって異なります。一般的には、相続登記に1通、金融機関ごとに1通程度必要になることが多いです。手続き先に事前に確認することをおすすめします。
Q5. 除籍謄本の保存期間はどれくらいですか?
除籍謄本(除籍簿)は、除籍された日から80年間保存されることが法律で定められています。80年を経過すると、原則として除籍簿は廃棄されますが、歴史的価値があるものは引き続き保存される場合もあります。
まとめ
除籍謄本は、戸籍から除かれた方の情報が記載された公文書であり、相続手続きにおいて非常に重要な役割を果たします。被相続人の出生から死亡までの戸籍情報を収集する「戸籍収集」の過程で、除籍謄本の取得が必要になることが多いです。
除籍謄本の取得は、除籍された本籍地の市区町村役場で行うことができます。請求できるのは本人、配偶者、直系尊属・卑属などの一定の範囲の方に限られており、第三者が請求する場合は正当な理由と委任状が必要です。
相続手続きを円滑に進めるためには、被相続人の戸籍情報を正確に把握することが大切です。除籍謄本は法定相続人の確定や相続手続きに必要な書類として重要な役割を果たしますので、相続が発生した場合は早めに必要書類を収集することをおすすめします。






