法定相続分(ほうていそうぞくぶん)とは?
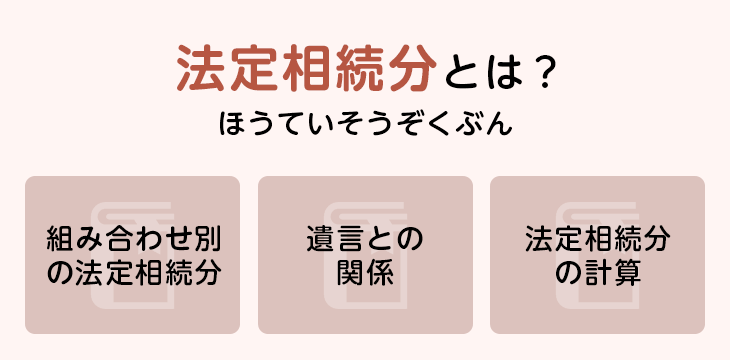
法定相続分とは、民法で定められた相続人それぞれが相続できる財産の割合のことです。
被相続人(亡くなった方)が遺言書を残さなかった場合、この法定相続分に従って遺産が分配されます。誰がどれだけ相続できるかは、被相続人との続柄によって法律で明確に定められています。
法定相続分の基本
法定相続分は、被相続人の配偶者と血族相続人の組み合わせによって決まります。配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の相続人は第一順位から第三順位まで存在します。
相続の順位は以下のように定められており、上位の順位に相続人がいる場合、下位の順位の人は相続権を持ちません。
| 第一順位 | 子(養子を含む)および代襲相続人(孫、ひ孫など) |
|---|---|
| 第二順位 | 直系尊属(父母、祖父母など) |
| 第三順位 | 兄弟姉妹および代襲相続人(甥、姪) |
上記の表は相続の順位を示しています。例えば、被相続人に子どもがいる場合、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。
相続人の組み合わせ別の法定相続分
法定相続分は、相続人の組み合わせによって以下のように定められています。
| 相続人の組み合わせ | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者のみ | 配偶者:全額(100%) |
| 配偶者と子ども | 配偶者:1/2(50%) 子ども:1/2(子どもが複数の場合は均等に分ける) |
| 配偶者と直系尊属 | 配偶者:2/3(約66.7%) 直系尊属:1/3(直系尊属が複数の場合は均等に分ける) |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:3/4(75%) 兄弟姉妹:1/4(兄弟姉妹が複数の場合は均等に分ける) |
| 子どものみ | 子ども:全額(子どもが複数の場合は均等に分ける) |
| 直系尊属のみ | 直系尊属:全額(直系尊属が複数の場合は均等に分ける) |
| 兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹:全額(兄弟姉妹が複数の場合は均等に分ける) |
この表は相続人の組み合わせによる法定相続分の割合を示しています。例えば、配偶者と子どもが相続人の場合、配偶者は財産の1/2を、子どもたちで残りの1/2を分けることになります。
兄弟姉妹の相続分の特殊性
兄弟姉妹の中でも、異母兄弟姉妹と異父兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、全血兄弟姉妹(同じ父母を持つ兄弟姉妹)の相続分の1/2となります。
例えば、全血の兄と異父の弟がいる場合、兄弟で1/4を分ける際に、兄が2/3、弟が1/3となります。
代襲相続と法定相続分
代襲相続とは、本来相続人となるべき人が被相続人より先に死亡した場合などに、その人の子どもが「代わりに」相続する制度です。
例えば、父親が亡くなり、子どもである長男が既に亡くなっていた場合、長男の子ども(被相続人の孫)が長男の代わりに相続人となります。
- 代襲相続の範囲:子と兄弟姉妹の代襲相続は何世代でも認められますが、直系尊属の代襲相続は認められません
- 代襲相続分の計算:代襲者は本来の相続人が受けるはずだった相続分を受け取ります
- 複数の代襲者がいる場合:その代襲者間で均等に分割されます
上記のリストは代襲相続の基本的なルールを示しています。代襲相続により複雑な相続関係が生じることがありますが、基本的には「本来相続するはずだった人の取り分」を代襲者が引き継ぐという考え方です。
法定相続分と遺言の関係
被相続人が有効な遺言書を残していた場合、原則として遺言の内容が法定相続分よりも優先されます。ただし、遺留分という最低限保障される相続分があります。
| 遺言と法定相続分 |
|
|---|
この表は遺言と法定相続分の関係を示しています。遺言は原則として法定相続分に優先しますが、遺留分という制限があることに注意が必要です。
遺留分について
遺留分とは、一定の相続人に最低限保障される相続分のことです。遺留分権利者は、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子ども、直系尊属)です。
| 遺留分権利者 | 遺留分の割合 |
|---|---|
| 配偶者 | 法定相続分の1/2 |
| 子ども | 法定相続分の1/2 |
| 直系尊属のみ | 法定相続分の1/3 |
| 兄弟姉妹 | 遺留分なし |
この表は遺留分権利者と遺留分の割合を示しています。例えば、配偶者と子どもが相続人の場合、配偶者の遺留分は全体の1/4(法定相続分1/2の1/2)です。
法定相続分の計算例
実際の相続において法定相続分がどのように計算されるのか、具体例を見てみましょう。
例1:配偶者と子ども2人の場合
被相続人の遺産が3,000万円、相続人が配偶者と子ども2人の場合:
- 配偶者の相続分:3,000万円 × 1/2 = 1,500万円
- 子ども1人あたりの相続分:3,000万円 × 1/2 ÷ 2人 = 750万円/人
このリストは配偶者と子ども2人の場合の具体的な相続分の計算例を示しています。配偶者が半分、残りを子どもたちで均等に分けます。
例2:配偶者、子ども1人と代襲相続人(孫)2人の場合
被相続人の遺産が4,000万円、相続人が配偶者、子ども1人、そして既に亡くなっていた他の子どもの子ども(孫)2人の場合:
- 配偶者の相続分:4,000万円 × 1/2 = 2,000万円
- 生存している子どもの相続分:4,000万円 × 1/2 × 1/2 = 1,000万円
- 孫1人あたりの相続分(代襲相続):4,000万円 × 1/2 × 1/2 ÷ 2人 = 500万円/人
このリストは代襲相続が発生した場合の計算例を示しています。亡くなった子どもの相続分を、その子どもたち(被相続人の孫)が均等に分けることになります。
よくある質問
Q1. 法定相続分と異なる割合で遺産分割することはできますか?
A1. はい、可能です。相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で遺産分割することができます。これを「遺産分割協議」といいます。
ただし、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要であり、一人でも反対すると成立しません。その場合は法定相続分に従うか、家庭裁判所での調停・審判となります。
Q2. 内縁の妻(夫)にも法定相続分はありますか?
A2. いいえ、法律上の婚姻関係にない内縁の妻(夫)には法定相続分はありません。法定相続人となるのは、法律上の婚姻関係にある配偶者のみです。
内縁関係の方に財産を残したい場合は、生前贈与や遺言書の作成が必要です。
Q3. 養子には法定相続分がありますか?
A3. はい、法律上の養子縁組が成立している養子には、実子と同じ法定相続分があります。特別養子縁組の場合は実親との法的関係が切れ、養親との間でのみ相続関係が発生します。
普通養子縁組の場合は、養親と実親の両方に対して相続権を持ちます。
Q4. 相続放棄した場合、その人の法定相続分はどうなりますか?
A4. 相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとみなされます。その結果、相続放棄した人の法定相続分は、他の相続人に移ります。
代襲相続と異なり、相続放棄した人の子どもが代わりに相続することはありません。
Q5. 遺言で法定相続分を無視して全財産を第三者に相続させることはできますか?
A5. 遺言により全財産を第三者に遺贈することは可能ですが、遺留分権利者(兄弟姉妹以外の相続人)の遺留分を侵害する場合、遺留分侵害額請求権が行使される可能性があります。
遺留分侵害額請求権が行使されると、遺留分の範囲内で財産を返還する必要が生じます。
まとめ
法定相続分は、被相続人の死亡により開始する相続において、遺言がない場合に民法で定められた割合で遺産を分配するための基準です。配偶者は常に相続人となり、その他の相続人は子ども、直系尊属、兄弟姉妹の順に優先順位があります。
相続人の組み合わせによって法定相続分は変わります。配偶者と子どもの場合は1/2ずつ、配偶者と直系尊属の場合は配偶者が2/3、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者が3/4という割合になります。
遺言がある場合は原則として遺言が優先されますが、兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分という最低限保障される相続分があり、遺言でもこれを侵害することはできません。また、相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる割合での遺産分割も可能です。
相続に関しては、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。特に複雑な家族関係や大きな資産がある場合は、トラブルを未然に防ぐためにも専門家のアドバイスを受けることが重要です。






