非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは?
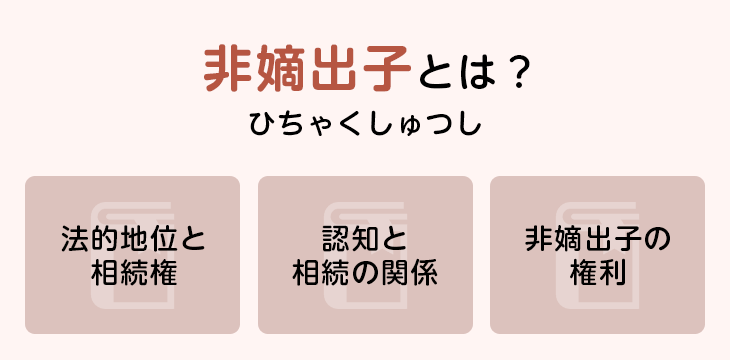
非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どものことを指します。
かつては婚外子とも呼ばれていました。2013年の民法改正前は、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1とされていましたが、現在は平等に扱われるようになっています。
非嫡出子の法的地位と相続権の変遷
日本の相続制度においては、長い間、非嫡出子(婚外子)は嫡出子(婚内子)と比べて不平等な扱いを受けてきました。民法900条4号ただし書きでは、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1と規定されていました。
この規定は「家族の秩序や倫理を守る」という理由で正当化されてきましたが、子どもの権利の観点からは問題視されていました。多くの法律専門家や国際機関からも、この不平等な取り扱いに対して批判がありました。
| 改正前の相続分 | 嫡出子:1、非嫡出子:1/2 |
|---|---|
| 改正後の相続分 | 嫡出子:1、非嫡出子:1 |
この表は、民法改正前後での嫡出子と非嫡出子の法定相続分の変化を示しています。現在は両者の相続分が平等になっています。
2013年の民法改正と最高裁判決の影響
2013年9月、最高裁判所大法廷は民法900条4号ただし書きについて、「法の下の平等」を定める憲法14条1項に違反するとの判決を下しました。この判決を受けて、同年12月に民法が改正され、非嫡出子の相続分に関する差別的規定が撤廃されました。
この改正により、非嫡出子は嫡出子と同じ相続分を得る権利を持つようになりました。相続における子どもの平等な権利が法的に保障されたことは、日本の家族法における大きな転換点となりました。
- 最高裁判決:2013年9月に最高裁が民法の規定を違憲と判断
- 民法改正:2013年12月に民法が改正され、相続分の差別が撤廃
- 施行:2013年12月11日以降に開始した相続から適用
この流れは、非嫡出子の相続権が平等化されるまでの重要な法改正のプロセスを示しています。最高裁の違憲判決が民法改正につながり、現在の平等な相続制度が確立されました。
非嫡出子の認知と相続の関係
非嫡出子が相続権を得るためには、父親による「認知」が必要です。認知とは、法律上の父子関係を成立させる手続きです。母親との関係は出生により当然に成立しますが、父親との関係は認知によって成立します。
認知には生前認知と死後認知があります。生前認知は父親の生存中に行われる認知で、死後認知は父親の死亡後に家庭裁判所に請求して認められる認知です。
- 生前認知:父親が生存中に認知届を提出する方法
- 遺言認知:遺言の中で認知の意思表示をする方法
- 死後認知:父親の死後に子が家庭裁判所に請求する方法
- 強制認知:父親が認知を拒否した場合に家庭裁判所に請求する方法
これらの認知方法があり、いずれの方法でも認知が成立すれば、非嫡出子は法律上の相続人として認められます。ただし、死後認知の場合は相続の時効などの問題が生じる場合もあります。
現在の相続制度における非嫡出子の権利
現在の日本の相続制度では、認知された非嫡出子は嫡出子と全く同じ法的地位を持ちます。相続分も平等であり、遺留分についても差異はありません。
具体的には、法定相続人となる子どもの中に嫡出子と非嫡出子が混在する場合でも、人数によって等分に相続することになります。例えば、被相続人に嫡出子2人と非嫡出子1人がいる場合、それぞれが1/3ずつ相続します。
| 相続に関する権利 | 内容 |
|---|---|
| 法定相続分 | 嫡出子と同じ(平等) |
| 遺留分 | 嫡出子と同じ(法定相続分の1/2) |
| 相続放棄の権利 | 嫡出子と同じ(相続開始を知った時から3ヶ月以内) |
| 遺産分割協議への参加 | 嫡出子と同じ(必ず参加する権利あり) |
この表は、現在の相続制度における非嫡出子の権利が嫡出子と全く同じであることを示しています。相続に関するすべての権利が平等に保障されています。
よくある質問
Q1: 非嫡出子であることは戸籍上どのように表記されるのですか?
戸籍上は「嫡出子」「非嫡出子」という表記はなく、母の戸籍に「父:記載なし」と記載されるか、認知された場合は父の氏名が記載されます。ただし、婚姻関係のない両親から生まれた子であることは、出生の記載から推測できる場合があります。
Q2: 非嫡出子の認知は相続開始後でも可能ですか?
はい、死後認知という制度があり、父親が死亡した後でも認知を求めることができます。ただし、死後認知の場合は家庭裁判所での審判が必要です。また、相続の時効(相続開始を知った時から10年、または相続開始から20年)との兼ね合いに注意が必要です。
Q3: 非嫡出子の相続分が平等になったのは何年からですか?
2013年12月11日以降に開始した相続から適用されています。それ以前に開始した相続については、原則として非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1のままですが、個別のケースによっては最高裁判決の影響を受ける可能性もあります。
Q4: 外国人との間に生まれた子どもの場合、認知手続きはどうなりますか?
基本的な認知手続きは日本人同士の場合と同じですが、国際私法(法の適用に関する通則法)の問題が絡むことがあります。子の本国法または認知する親の本国法によって手続きが異なる場合があるため、専門家への相談をおすすめします。
Q5: 非嫡出子は養子縁組することで嫡出子になりますか?
実親である父親が、その非嫡出子と養子縁組をしても、法的には嫡出子にはなりません。ただし、父親と母親が婚姻した場合、準正(じゅんせい)という制度により嫡出子の身分を取得することができます。現在は相続分に差はないため、実質的な違いはありません。
まとめ
非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どものことを指します。2013年までは、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1と定められていましたが、2013年9月の最高裁判決によりこの規定は憲法違反と判断されました。
同年12月の民法改正により、現在では非嫡出子は嫡出子と全く同じ相続権を持っています。相続分や遺留分に差異はなく、遺産分割協議への参加権も平等です。ただし、非嫡出子が父親の相続権を得るためには、認知が必要となります。
認知には生前認知、遺言認知、死後認知などの方法があり、いずれの方法でも認知されれば法律上の相続人として認められます。日本の相続制度は、出生による差別をなくし、子どもの権利を平等に保障する方向へと大きく変化してきました。






