被相続人(ひそうぞくにん)とは?
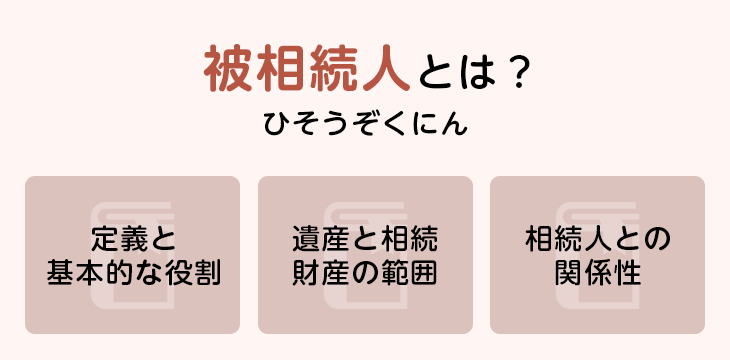
被相続人とは、死亡した人で、その財産や権利義務が相続の対象となる人のことを指します。
亡くなった方の財産や権利・義務は、法律で定められた相続人に受け継がれていきます。相続が発生するのは、被相続人が亡くなった時点であり、その死亡によって法定相続人に対して相続権が発生します。
被相続人の定義と基本的な役割
被相続人とは、亡くなることによって自分の財産や権利義務を相続人に引き継がせる人のことです。民法では「相続は、死亡によって開始する」と定められており、人が亡くなった時点でその人は被相続人となります。
被相続人の役割としては、生前に遺言書を作成することで、法定相続分とは異なる割合で財産を分配することができます。また、生前贈与を行うことで、相続時の財産分配に影響を与えることも可能です。
| 被相続人の条件 | 自然人(個人)であること |
|---|---|
| 相続開始の時期 | 被相続人の死亡時 |
| 相続の対象 |
上記の表は被相続人に関する基本情報をまとめたものです。被相続人となるのは自然人(個人)のみで、法人は被相続人になることはできません。相続が開始するのは被相続人の死亡時であり、その時点で相続財産が確定します。
被相続人に関する法律上の位置づけ
被相続人は民法第882条に基づいて定義されています。この条文では「相続は、死亡によって開始する」と規定されており、人が死亡した時点で被相続人となり、相続が開始されます。
被相続人の国籍や住所に関わらず、日本国内に財産がある場合は日本の相続法が適用されます。ただし、被相続人が外国籍の場合は、国際私法(法の適用に関する通則法)に基づき、被相続人の本国法が適用されることがあります。
- 死亡時:被相続人の死亡により相続が開始
- 失踪宣告:失踪宣告を受けた場合も法的に死亡したとみなされ相続開始
- 相続の放棄期間:被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内
- 相続税の申告期限:被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内
上記のリストは相続に関する主な法的なタイムラインを示しています。被相続人の死亡時だけでなく、行方不明者が失踪宣告を受けた場合も法的に死亡したとみなされ、相続が開始します。相続人は被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に相続の放棄をすることができます。
被相続人の遺産と相続財産の範囲
被相続人の財産のうち、相続の対象となるものを相続財産と呼びます。相続財産には、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれます。
ただし、一身専属的な権利義務は相続されません。例えば、慰謝料請求権や扶養請求権などは原則として相続の対象にはなりません。
- 不動産(土地・建物)
- 預貯金・現金
- 有価証券(株式・投資信託など)
- 自動車・貴金属・美術品
- 生命保険金(被相続人が保険料を支払っていた場合)
- 借金・ローン債務
- 税金の未払い分
上記のリストは一般的な相続財産の例です。被相続人が所有していた財産はプラスの財産もマイナスの財産も相続の対象となります。生命保険金については、被相続人が保険料を負担していた場合、みなし相続財産として相続税の課税対象となることがあります。
被相続人と相続人の関係性
被相続人と相続人は、法律で定められた血族関係や婚姻関係にある人たちです。民法では相続人の範囲と順位が定められており、第一順位は配偶者と子(直系卑属)、第二順位は配偶者と親(直系尊属)、第三順位は配偶者と兄弟姉妹となっています。
配偶者は常に相続人となり、他の親族と共同して相続します。被相続人の遺言がない場合は、法定相続分に従って財産が分配されます。
| 相続人の順位 | 相続分 |
|---|---|
| 配偶者と子がいる場合 |
|
| 配偶者と親がいる場合 |
|
| 配偶者と兄弟姉妹がいる場合 |
|
上記の表は、被相続人と相続人の関係に基づく法定相続分を示しています。被相続人が遺言書を残していない場合、この法定相続分に従って財産が分配されます。被相続人の子が既に亡くなっている場合は、その子(被相続人の孫)が代襲相続します。
被相続人が生前にできる相続対策
被相続人は生前に様々な相続対策を行うことができます。遺言書の作成は最も一般的な方法で、自分の意思に基づいて財産を分配することができます。また、生前贈与を活用することで、相続税の負担を軽減することも可能です。
家族信託や民事信託を活用して、認知症などになった場合の財産管理を事前に決めておくことも効果的な対策です。特に事業承継を考えている場合は、生前から計画的に準備を進めることが重要です。
- 遺言書の作成:自分の希望通りに財産を分配するための最も基本的な方法
- 生前贈与:年間110万円までの基礎控除額を活用して計画的に財産を移転
- 家族信託:認知症対策や事業承継に有効な財産管理・承継の仕組み
- 相続時精算課税制度:60歳以上の親から18歳以上の子への贈与に活用可能
- 不動産の共有持分調整:将来の相続トラブルを防止するための対策
上記のリストは被相続人が生前に行える主な相続対策です。それぞれの家族構成や財産状況に応じて、適切な対策を選ぶことが重要です。特に複雑な財産構成の場合や事業承継が必要な場合は、専門家への相談をおすすめします。
よくある質問
Q1. 被相続人が外国籍の場合、相続はどのように処理されますか?
被相続人が外国籍の場合、原則として被相続人の本国法が適用されます。ただし、日本国内にある不動産については日本の法律が適用されることがあります。国際相続の場合は、専門家への相談をおすすめします。
Q2. 被相続人の借金も相続しなければならないのですか?
基本的には借金も相続の対象になりますが、相続放棄をすることで借金を含むすべての相続財産を放棄することができます。相続放棄は被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
Q3. 被相続人の遺言書と法定相続分が異なる場合はどうなりますか?
原則として遺言書の内容が優先されます。ただし、遺留分(法定相続人に保障されている最低限の取り分)を侵害している場合は、遺留分侵害額請求をすることができます。
Q4. 被相続人の死亡後、いつまでに相続税の申告をする必要がありますか?
相続税の申告と納付は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。申告期限を過ぎると、延滞税や加算税がかかる場合があります。
Q5. 被相続人に遺言書がない場合、相続財産はどのように分けられますか?
遺言書がない場合は、民法で定められた法定相続分に従って財産が分配されます。配偶者と子がいる場合は配偶者が1/2、子が1/2(複数いる場合は均等分割)を相続します。
まとめ
被相続人とは、死亡によって自分の財産や権利義務を相続人に引き継がせる人のことです。相続は被相続人の死亡時に開始され、その時点で所有していた財産(プラスの財産とマイナスの財産の両方)が相続の対象となります。
被相続人と相続人の関係性によって法定相続分が決まりますが、被相続人が遺言書を残している場合は、原則としてその内容が優先されます。ただし、遺留分を侵害する内容の場合は、遺留分侵害額請求が可能です。
被相続人は生前から相続対策を行うことができます。遺言書の作成や生前贈与、家族信託の活用などが一般的な方法です。特に複雑な財産構成を持つ場合や事業承継が必要な場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
相続は家族間のトラブルになりやすい問題です。被相続人のうちに十分な対策を行い、相続人同士が争わずに円滑な相続ができるよう準備しておくことが大切です。特に遺言書の作成は、被相続人の意思を明確に伝えるための重要な手段となります。






