配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)とは?
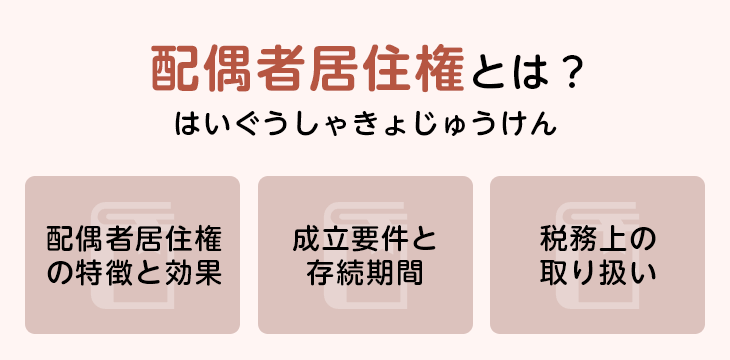
配偶者居住権とは、2020年4月に施行された改正民法で新設された権利で、配偶者が亡くなった後も、残された配偶者がこれまで住んでいた自宅に住み続けることができる権利です。
相続税評価額を下げる効果があり、配偶者の居住の安定を図ることを目的としています。
配偶者居住権とは
配偶者居住権は、2020年4月に施行された改正民法で創設された新しい法定相続制度です。配偶者が亡くなった後も、残された配偶者が自宅に住み続けることができる権利を保障するものです。
この制度が導入される前は、自宅を相続するためには相続財産の中から自宅の価値分を取得する必要がありました。そのため、自宅以外の遺産が少ない場合、残された配偶者が十分な生活資金を確保できないケースがありました。
配偶者居住権の創設により、配偶者は居住権のみを取得して住み続けることができるようになり、所有権は他の相続人が取得することが可能になりました。これにより、配偶者の居住の安定と遺産分割の柔軟性が向上しています。
配偶者居住権の特徴と効果
配偶者居住権には以下のような特徴と効果があります。
| 居住権と所有権の分離 | 配偶者は居住権のみを取得し、建物の所有権は別の相続人が取得することができます。 |
|---|---|
| 相続財産評価額の低減 | 配偶者居住権は所有権より評価額が低くなるため、相続税の負担軽減につながります。 |
| 登記の必要性 | 配偶者居住権は登記することで第三者に対抗することができます。 |
| 譲渡・担保設定の制限 | 配偶者居住権は原則として譲渡したり、担保に供したりすることができません。 |
上記の特徴により、配偶者の居住の安定を図りながら、相続財産を効率的に分配することが可能になります。特に自宅の価値が高い場合や、現金などの流動資産が少ない場合に大きな効果を発揮します。
配偶者居住権の成立要件
配偶者居住権が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。
これらの要件を満たさない場合、配偶者居住権は成立しません。例えば、被相続人の死亡時に別居していた場合や、建物が被相続人の所有ではない場合は対象外となります。
配偶者居住権の存続期間
配偶者居住権の存続期間については、以下のようなルールがあります。
- 終身(配偶者が亡くなるまで)または配偶者が指定した期間
- 存続期間を定めない場合は配偶者の終身の間
- 遺言等で別段の定めがない限り、配偶者の終身の間
- 配偶者が居住建物から退去した場合は消滅
上記の通り、原則として配偶者が亡くなるまで存続しますが、遺言や遺産分割協議によって期間を定めることも可能です。また、配偶者が自発的に退去した場合や、建物の保存に必要な修繕を怠るなど、一定の場合には消滅することがあります。
配偶者居住権と配偶者短期居住権の違い
配偶者居住権と同時に創設された「配偶者短期居住権」との違いを理解することも重要です。
| 項目 | 配偶者居住権 | 配偶者短期居住権 |
|---|---|---|
| 成立要件 | 遺産分割、遺贈、死因贈与による取得が必要 | 相続開始時に被相続人所有の建物に居住していれば自動的に発生 |
| 存続期間 | 原則として配偶者の終身 | 遺産分割確定まで、または相続開始から最大6か月間 |
| 登記 | 登記可能(第三者対抗要件) | 登記不可 |
| 相続税評価 | 評価対象(減額効果あり) | 評価対象外 |
配偶者短期居住権は、遺産分割が確定するまでの一時的な居住権を保障するものであり、配偶者居住権は長期的な居住の安定を図るためのものです。相続開始直後は短期居住権が自動的に発生し、その後遺産分割等により配偶者居住権を取得することが一般的な流れとなります。
配偶者居住権の税務上の取扱い
配偶者居住権の税務上の取扱いは、相続税の節税対策として重要な要素です。
配偶者居住権の評価方法
配偶者居住権の評価額は、以下の計算式で算出されます。
| 配偶者居住権の評価額 | 建物の時価 × (残存耐用年数 ÷ 建物の耐用年数) × 存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率 |
|---|
この計算式により、配偶者の年齢が高いほど評価額は低くなる傾向があります。そのため、配偶者の年齢が高い場合には、相続税の節税効果が大きくなります。
節税効果の例
配偶者居住権を活用した場合と、建物の所有権をそのまま相続した場合の相続税評価額の違いを示します。
| ケース | 評価額(例) |
|---|---|
| 建物所有権をそのまま相続 | 3,000万円 |
| 配偶者居住権を取得 (80歳配偶者の場合) |
約900万円 |
| 建物所有権(居住権付き) | 約2,100万円 |
上記のように、配偶者居住権と所有権を分けて相続することで、評価額の合計は変わらないものの、配偶者の取得分の評価額を大幅に下げることができます。これにより、配偶者の相続税額を軽減できるケースが多くなります。
なお、配偶者控除を活用する場合は、控除限度額の範囲内であれば配偶者居住権を設定しなくても非課税となるため、個別の状況に応じた検討が必要です。
よくある質問
配偶者居住権は誰でも取得できますか?
配偶者居住権を取得できるのは、被相続人の配偶者のみです。法律上の婚姻関係にある配偶者に限られ、内縁関係のパートナーは対象外となります。また、相続開始時(被相続人の死亡時)に被相続人所有の建物に居住していることが条件です。
配偶者居住権を取得すると、どのような費用負担がありますか?
配偶者居住権を有する者は、通常の使用に伴う費用(電気・ガス・水道などの光熱費、日常的な修繕費など)を負担します。一方、固定資産税や建物の大規模修繕費などは原則として所有者が負担します。ただし、遺言や遺産分割協議で別段の定めをすることも可能です。
配偶者居住権は譲渡できますか?
配偶者居住権は原則として譲渡できません。また、担保に供することもできません。これは、配偶者の居住の安定を図るという制度趣旨に基づくものです。ただし、所有者の承諾を得れば、建物を第三者に使用させることは可能です。
配偶者居住権は登記しなければならないですか?
配偶者居住権は登記することで第三者に対抗することができます。登記は義務ではありませんが、登記をしないと建物所有者が建物を第三者に売却した場合などに、居住権を主張できなくなるリスクがあります。安全を期すためには登記することが望ましいでしょう。
配偶者居住権と遺留分はどのような関係がありますか?
配偶者居住権も遺産の一部として遺留分算定の基礎に算入されます。配偶者居住権の価額が高額な場合、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があるため、遺留分に配慮した遺産分割を行うことが重要です。遺言で配偶者居住権を設定する場合も同様の配慮が必要です。
まとめ
配偶者居住権は、残された配偶者の居住の安定を図るために2020年に創設された重要な権利です。この制度により、配偶者は相続財産の中から自宅の価値分すべてを取得しなくても、そこに住み続ける権利を確保できるようになりました。
配偶者居住権の最大の特徴は、居住権と所有権を分離できる点です。これにより、配偶者は居住権のみを取得し、建物の所有権は子などの他の相続人が取得することができます。相続税評価額が低減されるため、特に高齢の配偶者にとっては節税効果も期待できます。
ただし、配偶者居住権を活用するためには、被相続人所有の建物に相続開始時に居住していることや、遺産分割、遺贈または死因贈与によって取得することなど、いくつかの要件を満たす必要があります。また、登記をしなければ第三者に対抗できないなど、留意すべき点もあります。
配偶者居住権を効果的に活用するためには、個別の事情に応じた検討が必要です。遺言作成時や相続対策を考える際には、専門家への相談をおすすめします。適切な活用により、配偶者の生活の安定と円滑な相続の実現に役立てることができるでしょう。






