相続税の基礎控除(そうぞくぜいのきそこうじょ)とは?
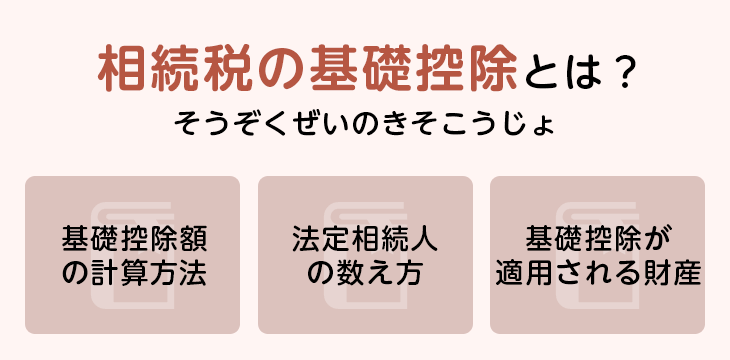
相続税の基礎控除とは、相続財産のうち一定金額までは相続税がかからない制度です。
具体的には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で算出され、この金額以下の相続財産であれば相続税は課税されません。基礎控除制度は、中小規模の財産に対する課税を避け、一般家庭の生活基盤を守る役割を果たしています。
相続税の基礎控除とは
相続税の基礎控除は、相続財産から一定額を控除して、その控除後の金額に対して相続税を課税する制度です。この制度により、一定規模以下の財産については相続税が課されないため、多くの一般家庭は相続税の申告が不要になります。
基礎控除は、被相続人(亡くなった方)の財産全体に対して適用され、相続人ごとではなく相続財産全体に対して一度だけ適用されます。そのため、相続人が多数いる場合でも、基礎控除額は変わりません。
| 基礎控除の目的 | 中小規模の財産に対する課税の回避、生活基盤の保護、相続税の負担軽減 |
|---|---|
| 適用対象 |
|
この表は基礎控除の主な目的と適用対象を示しています。基礎控除は相続税の根幹をなす制度で、すべての相続に適用されます。
基礎控除額の計算方法
相続税の基礎控除額は、以下の計算式で求められます。
- 基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
この計算式による基礎控除額は、実際の相続税申告において最初に控除される金額です。例えば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円」となります。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
この表は法定相続人の人数別に計算した基礎控除額の例です。法定相続人の数が増えるほど基礎控除額も増加します。
法定相続人の数え方
基礎控除額の計算に使用する法定相続人の数は、民法で定められた相続順位に基づいて数えます。実際に相続放棄をした人や相続欠格者であっても、法定相続人の数には含めます。
この表は法定相続人となる人の範囲を示しています。配偶者は常に法定相続人となりますが、その他の親族は順位によって法定相続人になるかどうかが決まります。
なお、養子については、実子と同様に法定相続人としてカウントされますが、相続税法上は制限があります。養子の数は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までが法定相続人の数に含まれます。
基礎控除が適用される財産
基礎控除は相続税の課税対象となるすべての財産に適用されます。具体的には以下のような財産が含まれます。
この表は相続税の課税対象となる主な財産の種類を示しています。これらすべての財産の合計額から基礎控除額を差し引いた金額に対して相続税が課税されます。
非課税財産について
一方、以下のような財産は相続税の非課税財産とされており、相続財産の合計額に含まれません。
| 非課税財産の種類 | 内容 |
|---|---|
| 公益事業用財産 | 公益法人等が公益事業の用に供する財産 |
| 墓地・仏壇・仏具等 | 祭祀用の財産で、通常必要と認められるもの |
| 国等に寄付した財産 | 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産 |
| 生命保険金の非課税枠 | 500万円×法定相続人の数まで非課税 |
| 死亡退職金の非課税枠 | 500万円×法定相続人の数まで非課税 |
この表は相続税が課税されない非課税財産の主な種類を示しています。非課税財産は相続財産の計算に含まれないため、基礎控除とは別の節税効果があります。
基礎控除の改正の歴史
相続税の基礎控除は、時代の変化や税制改正に伴い、何度か改正されてきました。直近の大きな改正は平成27年(2015年)に行われ、基礎控除額が大幅に引き下げられました。
- 昭和63年まで:2,000万円 + 400万円 × 法定相続人の数
- 平成4年~平成26年:5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数
- 平成27年以降:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
この表は相続税の基礎控除額の変遷を示しています。平成27年の改正では基礎控除額が4割減少し、相続税の課税対象者が増加しました。
平成27年の税制改正では、基礎控除額の引き下げに加えて、最高税率の引き上げ(50%から55%へ)など、相続税の負担増加につながる改正が行われました。これらの改正により、相続税の課税対象となる相続人の割合は、改正前の約4%から約8%へと倍増しました。
よくある質問
相続放棄をした人も法定相続人の数に含まれますか?
はい、相続放棄をした人も基礎控除額を計算する際の法定相続人の数に含まれます。相続税法上の法定相続人は、民法上の相続権がある人を指し、実際に相続するかどうかは関係ありません。そのため、相続放棄をした人や相続欠格者であっても、法定相続人としてカウントされます。
配偶者の税額軽減と基礎控除は併用できますか?
はい、併用できます。基礎控除は相続財産全体に適用され、配偶者の税額軽減は配偶者が相続する分に適用される別の制度です。まず全体の相続財産から基礎控除を差し引いた後、各相続人の取得分に応じて税額を計算し、配偶者については税額軽減が適用されます。
生前贈与を受けた財産も基礎控除の対象になりますか?
被相続人から相続開始前3年以内に受けた贈与財産は、相続財産に加算されます(死亡前3年以内の贈与加算)。この加算された贈与財産も含めた金額が、基礎控除額を超えるかどうかで課税対象になるかが決まります。なお、暦年課税の基礎控除(年間110万円)を利用した贈与であっても、3年以内の贈与は加算対象です。
基礎控除を超えた場合、すべての財産に相続税がかかりますか?
いいえ、基礎控除を超えた部分にのみ相続税がかかります。例えば、相続財産が5,000万円で基礎控除額が4,800万円の場合、超過分の200万円に対してのみ相続税が課税されます。また、相続財産の種類や取得者によっては、各種の税額控除や特例措置が適用される場合があります。
相続財産が基礎控除以下でも申告は必要ですか?
相続財産の合計額が基礎控除額以下であれば、原則として相続税の申告は不要です。ただし、相続時精算課税制度を利用した贈与がある場合や、特定の財産について特例の適用を受ける場合などは、相続税が発生しなくても申告が必要になることがあります。不明な点がある場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
相続税の基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で求められ、この金額以下の相続財産であれば相続税は課税されません。この制度により、多くの一般家庭は相続税の申告が不要となっています。
基礎控除額の計算に使用する法定相続人の数は、相続放棄をした人や相続欠格者も含まれます。また、養子については、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までが法定相続人の数に含まれるという制限があります。
相続税の基礎控除は平成27年に大幅に引き下げられ、それ以前の「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」から現在の金額に改正されました。これにより相続税の課税対象者は約2倍に増加しています。
基礎控除を超える財産を相続する場合は、相続税の申告が必要になります。ただし、配偶者の税額軽減や各種の特例措置を活用することで、相続税の負担を軽減できる可能性があります。相続税の節税対策や申告手続きについては、早めに税理士などの専門家に相談することをおすすめします。






