農地の納税猶予制度(のうちののうぜいゆうよせいど)とは?
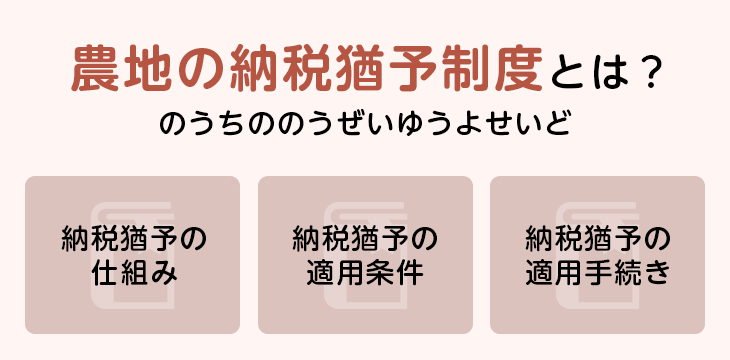
農地の納税猶予制度とは、農業を営んでいた被相続人から農地を相続した場合に、一定の要件を満たすことで相続税の納税を猶予してもらえる特例制度です。
相続した農地を引き続き農業経営に使用することを条件に、その農地にかかる相続税の納税を猶予し、相続人の負担を軽減する目的があります。
農地の納税猶予制度の概要
農地の納税猶予制度は、農業の継続と農地の維持を目的とした税制上の特例措置です。被相続人から農地を相続した相続人が、その農地で農業を続ける場合に相続税の納税を猶予する制度となっています。
この制度を利用すると、農業相続人が相続した特例農地等に対応する相続税額について、相続税の申告期限から20年間(平成21年改正前は農業相続人の死亡の日まで)、納税が猶予されます。
| 納税猶予の対象 | 相続または遺贈により取得した農地等に係る相続税額 |
|---|---|
| 猶予期間 |
|
| 猶予税額 | 農地等の価額に対応する相続税額の全額 |
上記の表は農地の納税猶予制度の基本的な内容をまとめたものです。適用期間や猶予される税額について確認できます。
農地の納税猶予制度の適用要件
農地の納税猶予制度を適用するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
被相続人の要件
- 相続開始前から農業を営んでいた個人であること
- 相続開始前から農地等を所有していたこと
被相続人は農業を営む個人である必要があり、農地を所有していることが基本条件となります。
相続人の要件
- 相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も継続すること
- 相続税の申告期限までに、特例適用農地等について農業委員会の証明を受けること
- 相続税の申告書に特例の適用を受ける旨を記載し、必要書類を添付すること
相続人は農業経営を継続する意思があり、必要な手続きを期限内に行う必要があります。
対象となる農地等の要件
- 被相続人が相続開始前から所有していた農地等であること
- 市街化区域内農地については、生産緑地地区内に所在するものであること
- 農業経営に不可欠な農機具等の減価償却資産も対象に含まれる
対象となる農地には一定の制限があり、特に市街化区域内の農地については生産緑地地区内に所在することが求められます。
納税猶予の適用手続き
農地の納税猶予制度を適用するためには、以下の手続きを行う必要があります。
- 相続税の申告期限までに農業経営を開始:相続または遺贈により農地等を取得した後、相続税の申告期限までに農業経営を開始する
- 農業委員会の証明:特例適用農地等について、農業委員会の証明を受ける
- 相続税申告書の提出:相続税の申告書に特例の適用を受ける旨を記載し、必要書類を添付する
- 担保の提供:納税猶予を受ける税額に相当する担保を提供する
上記の手続きは、すべて相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)までに完了させる必要があります。
必要書類
| 提出書類 | 内容 |
|---|---|
| 相続税の申告書 | 特例適用の旨を記載 |
| 農業委員会の証明書 | 特例適用農地等であることの証明 |
| 担保提供関係書類 | 納税猶予税額に対する担保の提供 |
| 農業経営に関する誓約書 | 継続して農業経営を行う旨の誓約 |
この表は納税猶予制度の適用に必要な書類をまとめたものです。すべての書類を揃えて期限内に提出することが重要です。
納税猶予の打ち切り(特例の終了)
以下のような場合には、納税猶予が打ち切られ、猶予されていた相続税を納付する必要が生じます。
- 特例適用農地等を譲渡した場合
- 農業経営を中止(農業をやめる)した場合
- 特例適用農地等を農業の用に供さなくなった場合
- 地区区分が変更され、市街化区域となった農地を生産緑地地区に指定しなかった場合
- 農業相続人が死亡した場合(平成21年改正前の制度の場合)
納税猶予が打ち切られた場合、猶予されていた相続税に加えて、利子税も併せて納付する必要があります。
一部譲渡の場合
特例適用農地等の一部を譲渡した場合、譲渡した部分に対応する相続税と利子税を納付する必要があります。ただし、特例農地等を公共事業のために収用された場合など、一定の場合には納税猶予は継続されます。
新しい納税猶予制度(平成21年改正)
平成21年の税制改正により、農地の納税猶予制度は大きく変更されました。主な変更点は以下の通りです。
| 区分 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 猶予期間 | 農業相続人の死亡の日まで | 相続税の申告期限から20年間 |
| 特例適用後の土地利用 | 農業経営以外の用途への転用不可 | 20年経過後は自由(条件なし) |
| 貸付け | 原則として認められない | 一定の貸付けは認められる |
この表は平成21年の税制改正による農地の納税猶予制度の主な変更点をまとめたものです。特に猶予期間と利用制限に大きな変更がありました。
改正後の制度では、20年間の営農継続後は納税が免除され、その後の土地利用に制限がなくなりました。これにより、後継者にとっての制度利用の負担が軽減されています。
よくある質問
Q1. 農地の納税猶予制度と贈与税の納税猶予制度の違いは何ですか?
農地の納税猶予制度は相続税に関する制度であり、被相続人から相続により農地を取得した場合に適用されます。一方、贈与税の納税猶予制度は生前贈与により農地を取得した場合に適用される制度です。
どちらも農業継続が条件ですが、適用要件や手続きに違いがあります。贈与の場合は、贈与者が65歳以上であることなど、追加の要件があります。
Q2. 納税猶予を受けている農地を一部売却したらどうなりますか?
特例適用農地の一部を売却した場合、売却した部分に対応する相続税と利子税を納付する必要があります。ただし、残りの農地については、引き続き納税猶予の適用を受けることができます。
Q3. 納税猶予を受けている農地を貸し付けることはできますか?
平成21年の改正後は、一定の条件を満たす貸付けについては、納税猶予が継続されます。具体的には、認定農業者等への貸付けや、特定貸付けなどが認められています。
ただし、貸付けを行う前に税務署への届出が必要です。無断で貸付けを行うと、納税猶予が打ち切られる可能性があるのでご注意ください。
Q4. 相続した農地が市街化区域内にある場合も納税猶予は受けられますか?
市街化区域内の農地であっても、生産緑地地区内に所在するものであれば、納税猶予の対象となります。生産緑地地区以外の市街化区域内農地については、納税猶予の適用を受けることができません。
Q5. 納税猶予を受けた後に相続人が死亡した場合はどうなりますか?
平成21年改正前の制度では、相続人が死亡すると納税猶予が打ち切られ、猶予されていた相続税を納付する必要がありました。
しかし、平成21年改正後の制度では、20年間の猶予期間を設けたため、その期間内に相続人が死亡した場合でも、その相続人の相続人が農業を継続する場合には、納税猶予を引き継ぐことができるようになりました。
まとめ
農地の納税猶予制度は、農業を営んでいた被相続人から農地を相続した場合に、相続税の納税を猶予してもらえる特例制度です。この制度を利用することで、相続人の税負担を軽減し、農業の継続と農地の維持を支援することを目的としています。
制度を適用するためには、被相続人と相続人、そして対象となる農地がそれぞれ一定の要件を満たす必要があります。また、相続税の申告期限までに必要な手続きを行わなければなりません。
平成21年の税制改正により、猶予期間が農業相続人の死亡の日までから相続税の申告期限から20年間に変更され、20年経過後は納税が免除されるようになりました。これにより、後継者にとって制度の利用がより利用しやすくなっています。
ただし、猶予期間中に特例適用農地等を譲渡したり、農業経営を中止したりすると、猶予されていた相続税に加えて利子税も併せて納付する必要があるので注意が必要です。
農地の相続を検討されている方は、この納税猶予制度の活用を検討するとともに、詳細については税理士や司法書士などの専門家にご相談されることをおすすめします。






