延納(えんのう)とは?
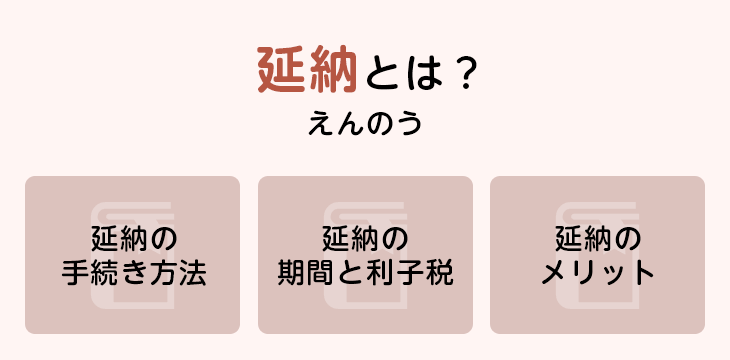
延納とは、相続税の納付方法の一つで、一定の要件を満たす場合に、相続税を一括で納めるのではなく、最長20年間にわたって分割して納めることができる制度です。
相続財産の中に不動産や事業用資産など換金しにくい財産が多く含まれる場合、一括での納税が困難なケースがあります。そのような場合に活用できる制度となっています。
延納の要件
延納の申請には、以下の要件を満たす必要があります。相続税額が10万円を超えていることが前提条件となります。
| 金額条件 | 相続税額が10万円を超えていること |
|---|---|
| 納付困難性 | 金銭で納付することが困難な事由があること |
| 担保提供 | 原則として、延納相続税額に相当する担保を提供すること |
上記の要件を満たしていることが延納申請の基本条件です。特に担保の提供は重要な条件となりますが、担保として提供できる財産には一定の制限があります。
延納の手続き
延納を希望する場合は、一定の期限内に必要な手続きを行う必要があります。具体的には以下の流れで手続きを進めます。
- 相続税の申告期限までに「延納申請書」を税務署に提出する
- 税務署による審査が行われる
- 延納が許可された場合、担保を提供する
- 延納許可通知書が交付される
- 分割納付計画に従って納税する
この手続きの流れに沿って適切に申請を行うことが重要です。特に申告期限内に申請書を提出する必要があるため、期限管理には注意しましょう。
必要書類
延納申請には以下の書類が必要です。すべて申告期限までに提出する必要があります。
- 相続税の申告書
- 延納申請書
- 担保提供関係書類
- 納付困難を証明する書類
- 延納明細書
これらの書類をすべて揃えて提出することで、延納申請の手続きが開始されます。書類に不備があると許可されない場合があるため、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
延納の期間と利子税
延納を行う場合、延納期間に応じて利子税が発生します。延納期間と利子税の関係は以下のとおりです。
| 延納可能期間 | 原則として5年以内。ただし、相続財産の中に不動産等の価額が相続税評価額の75%以上を占める場合には、最長20年まで可能 |
|---|---|
| 利子税 |
|
利子税は延納の便宜を図るための一種の利息と考えることができます。延納期間が長ければ長いほど、利子税の負担も大きくなるため、資金計画を立てる際には注意が必要です。
延納のメリット・デメリット
延納制度には以下のようなメリットとデメリットがあります。自分の状況に合わせて検討することが大切です。
| メリット |
|
|---|
| デメリット |
|
|---|
延納を選択する際は、これらのメリット・デメリットを踏まえ、他の納税方法と比較検討することが重要です。特に利子税の負担と将来の資金計画を考慮する必要があります。
物納との違い
相続税の納付方法としては、延納の他に物納という方法もあります。それぞれの違いを理解しておくことが重要です。
| 延納 |
|
|---|---|
| 物納 |
|
延納と物納は、どちらも相続税の納付が困難な場合の救済措置ですが、その性質は大きく異なります。延納は最終的に金銭で納付するのに対し、物納は財産そのもので納付する点が大きな違いです。
よくある質問
Q1. 延納が認められるのはどのような場合ですか?
相続税額が10万円を超え、相続財産の大部分が不動産や事業用資産など換金しにくい財産で構成されており、一括で納税することが困難であると認められる場合に延納が許可されます。
また、担保の提供ができることも重要な条件となります。税務署による審査があり、単に資金が不足しているというだけでは認められない場合があります。
Q2. 延納の担保にはどのような財産が利用できますか?
延納の担保として利用できる財産には、不動産、国債・地方債、上場株式、社債、納税保証保険証券などがあります。
ただし、担保価値は時価ではなく、相続税評価額に基づいて計算されます。また、担保として適さない財産もあるため、事前に税務署に確認することをおすすめします。
Q3. 延納中に一括で残りの相続税を納付することはできますか?
はい、延納中であっても残りの相続税を一括で納付することは可能です。むしろ、資金に余裕ができた場合は、利子税の負担を減らすために一括納付を検討すべきです。
一括納付する場合は、税務署に連絡して必要な手続きを行いましょう。担保の解除手続きも同時に行うことになります。
Q4. 延納が不許可になるケースはありますか?
はい、いくつかのケースで延納が不許可になることがあります。例えば、申請書の提出が遅れた場合、担保が不十分な場合、納付困難な事由が認められない場合などです。
また、過去に滞納歴がある場合や、延納計画の実現可能性が低いと判断された場合も不許可となることがあります。不許可となった場合は、原則として一括納付か物納を検討する必要があります。
Q5. 延納中に分割納付ができなくなった場合はどうなりますか?
延納中に分割納付ができなくなった場合、延納許可が取り消されることがあります。その場合、残りの延納税額を一括で納付する必要が生じます。
納付が困難な場合は担保財産が処分される可能性もあります。状況が変わり納付が困難になりそうな場合は、早めに税務署に相談することが重要です。
まとめ
延納は、相続税の納付が一時的に困難な場合に、最長20年間にわたって分割納付できる制度です。相続財産の大部分が不動産や事業用資産などで占められている場合に特に有効な選択肢となります。
延納を利用するには、相続税額が10万円を超えていること、納付困難な事由があること、担保を提供できることなどの要件を満たす必要があります。また、延納期間中は利子税が発生するため、金利負担も考慮に入れて判断することが大切です。
延納申請は相続税の申告期限までに行う必要があり、申請書や担保提供関係書類など複数の書類を提出しなければなりません。手続きが複雑なため、税理士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
延納と物納はどちらも相続税の納付が困難な場合の救済措置ですが、延納は最終的に金銭で納付するのに対し、物納は財産そのもので納付するという大きな違いがあります。自分の状況に合った納付方法を選択することが重要です。






