遺留分侵害額の請求(いりゅうぶんしんがいがくのせいきゅう)とは?
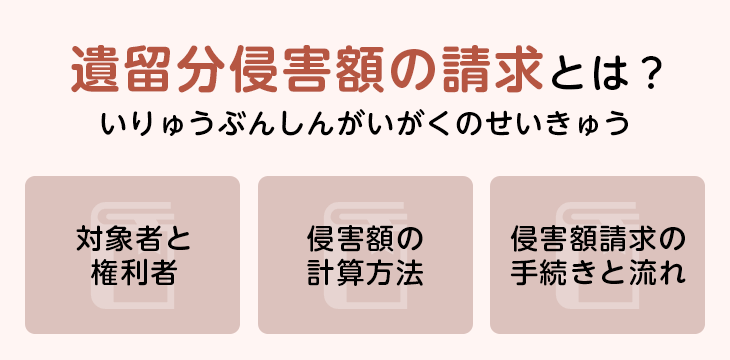
遺留分侵害額の請求とは、遺留分権利者が自分の遺留分を侵害された場合に、侵害した受遺者や受贈者に対して金銭による請求をすることができる制度です。2019年の民法改正により、以前の「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額の請求」へと名称と内容が変更されました。
遺留分とは、一定の相続人(配偶者、子、直系尊属)に保障された最低限の相続分であり、被相続人の財産処分の自由に制限を加える制度です。遺言や生前贈与によってこの遺留分が侵害された場合、権利者は金銭による支払いを請求できます。
遺留分侵害額の請求とは
遺留分侵害額の請求とは、遺言や生前贈与によって遺留分を侵害された相続人が、侵害した金額に相当する金銭の支払いを請求できる制度です。2019年7月1日施行の改正民法により、従来の「遺留分減殺請求」から変更されました。
改正前は、遺留分を侵害する遺贈や贈与の効力を失わせて物や権利そのものを取り戻す制度でしたが、改正後は金銭による請求に一本化されました。これにより、不動産などの共有状態を避け、相続トラブルの解決がスムーズになりました。
| 改正前 | 遺留分減殺請求(現物返還が原則) |
|---|---|
| 改正後 | 遺留分侵害額請求(金銭請求のみ) |
改正前後の制度の違いを示した表です。民法改正により、請求の内容が現物返還から金銭請求へと変更されました。
遺留分侵害額請求の対象者と権利者
遺留分権利者
遺留分が認められているのは、以下の相続人のみです。相続人でも兄弟姉妹には遺留分がありません。
- 配偶者(被相続人の妻または夫)
- 子(養子を含む)および代襲相続人(子の子)
- 直系尊属(両親、祖父母など)※子がいない場合
上記は遺留分権利者として認められる相続人の一覧です。兄弟姉妹は第三順位の法定相続人ですが、遺留分は認められていません。
遺留分侵害額請求の対象者
遺留分侵害額の請求は、以下の者に対して行うことができます。
- 遺贈を受けた受遺者(遺言により財産を取得した人)
- 死亡前1年以内になされた贈与の受贈者
- 被相続人の死亡により効力を生じる贈与の受贈者
- 被相続人の死亡前10年以内の、遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与の受贈者
遺留分侵害額の請求ができる対象者のリストです。請求対象となる贈与には一定の期間制限があることに注意が必要です。
遺留分侵害額の計算方法
遺留分侵害額の計算は複雑で、専門家に相談することをおすすめします。基本的な計算方法は以下の通りです。
- 遺留分算定の基礎財産を確定:相続開始時の財産+一定期間内の贈与財産-債務
- 遺留分の割合を確定:法定相続分の1/2(直系尊属のみが相続人の場合は1/3)
- 個々の遺留分権利者の遺留分を計算:基礎財産×遺留分割合×法定相続分
- 侵害額を計算:権利者の遺留分-実際に相続できる財産額
遺留分侵害額を計算するための基本的な手順です。実際の計算では相続財産の評価や特別受益の持ち戻し計算など複雑な要素があります。
計算例
| 被相続人の財産 | 3,000万円(債務なし) |
|---|---|
| 相続人 | 配偶者、子2人 |
| 遺言内容 | 友人Aに全財産を遺贈 |
この場合、配偶者の遺留分は基礎財産3,000万円×法定相続分1/2×1/2=750万円、子1人の遺留分は3,000万円×法定相続分1/4×1/2=375万円となります。友人Aに対して、配偶者は750万円、子はそれぞれ375万円の遺留分侵害額を請求できます。
遺留分侵害額請求の手続きと流れ
遺留分侵害額の請求手続きは、以下の流れで行います。
- 権利者であることの確認:遺留分権利者に該当するか確認
- 請求前の協議:できれば当事者間で話し合いを行う
- 請求の意思表示:受遺者・受贈者に対し、請求の意思表示を行う(内容証明郵便等が望ましい)
- 金額の交渉:具体的な金額について協議
- 訴訟提起:協議不調の場合、裁判所に訴えを提起
遺留分侵害額請求の一般的な手続きの流れです。請求は相続開始を知った時から1年以内、または相続開始から10年以内に行う必要があります。
請求に必要な書類
遺留分侵害額請求に必要な主な書類です。実際の手続きでは他にも書類が必要になる場合があります。
遺留分侵害額請求の効果と時効
請求の効果
遺留分侵害額請求が認められると、受遺者や受贈者は侵害額に相当する金銭を支払う義務を負います。支払いが困難な場合、裁判所に支払猶予の請求をすることができます。
支払猶予が認められると、最大5年間の分割払いや支払期限の猶予が認められる場合があります。この間、法定利息が発生します。
時効
遺留分侵害額請求権には時効があります。以下のいずれか早い方の期間内に請求しなければ、権利が消滅します。
| 短期消滅時効 | 相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年 |
|---|---|
| 長期消滅時効 | 相続開始時から10年 |
遺留分侵害額請求権の消滅時効を示した表です。権利行使は早めに行うことが重要です。
よくある質問
Q1: 遺留分侵害額請求は誰に対して行えますか?
遺留分侵害額請求は、遺贈を受けた受遺者や一定期間内の贈与を受けた受贈者に対して行えます。相続人が遺産分割で多くを取得しただけでは対象になりません。遺言や贈与によって遺留分が侵害された場合に請求できます。
Q2: 遺留分侵害額請求と遺産分割協議の関係はどうなりますか?
遺留分侵害額請求と遺産分割協議は別の手続きです。遺産分割協議は相続人間で遺産の分け方を決める手続きですが、遺留分侵害額請求は遺留分を侵害された相続人が受遺者や受贈者に対して行う請求です。両方の手続きが並行して進むこともあります。
Q3: 遺留分侵害額請求をしたいのですが、相続財産の価額がわかりません。どうすればよいですか?
まずは戸籍謄本や不動産登記簿、預金通帳などの資料を集めて財産調査をしましょう。それでも把握できない場合は、財産目録の開示請求や調査嘱託の申立てなどの法的手段があります。専門家(弁護士や司法書士)に相談することをおすすめします。
Q4: 遺留分侵害額請求は必ず裁判になりますか?
必ずしも裁判になるわけではありません。多くの場合、当事者間の話し合いや調停などのADR(裁判外紛争解決手続き)で解決します。しかし、金額に大きな隔たりがある場合や感情的対立がある場合は裁判になることもあります。
Q5: 遺留分の放棄はできますか?
遺留分の放棄は可能ですが、被相続人の生前に家庭裁判所の許可を得る必要があります。相続開始後は、遺留分侵害額請求権を放棄することができますが、これには特別な方式は必要ありません。ただし、一度放棄すると撤回はできないので注意が必要です。
まとめ
遺留分侵害額の請求は、遺留分権利者(配偶者、子、直系尊属)が自分の遺留分を侵害された場合に、侵害した受遺者や受贈者に対して金銭による支払いを請求できる制度です。2019年の民法改正により、従来の遺留分減殺請求から金銭請求に変更されました。
遺留分侵害額の計算は、基礎財産の確定、遺留分割合の適用、具体的な侵害額の算出という手順で行われます。請求権の行使には、相続開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年という時効があります。
遺留分侵害額請求は、相続トラブルの中でも特に複雑な手続きになることが多いため、早めに専門家に相談することをおすすめします。適切な権利行使により、法律で保障された最低限の相続分を確保することができます。






