遺言(ゆいごん・いごん)とは?
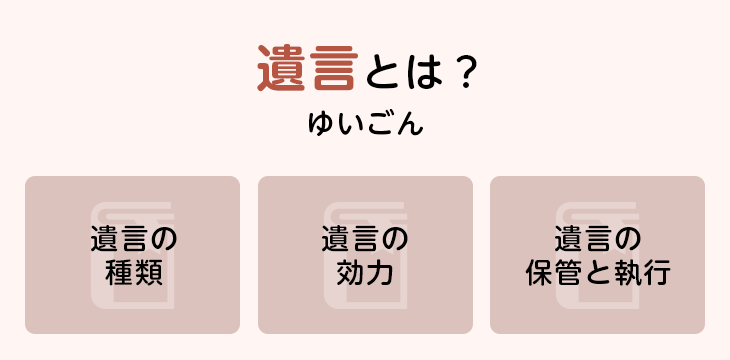
遺言とは、人が死亡した後に法的効力を持つ意思表示のことです。「いごん」と「ゆいごん」では若干意味合いが異なり、「いごん」は法律上の効力がある遺言について話をするときに用いられる読み方です。一方、「ゆいごん」は「遺言をする人が家族に対して残す言葉」という広い意味で使われることが多いです。
世間一般では「ゆいごん」という読み方が普通ですが、弁護士や司法書士などの法律家は「いごん」と読むことが一般的です。なお、専門家に相談する際はどちらの読み方でも意味は通じます。
「いごん」と「ゆいごん」の違い
「いごん」と「ゆいごん」は同じ「遺言」という漢字を使いますが、その使い分けには明確な背景があります。「いごん」は法律上の効力がある遺言について話をするときに用いられる読み方です。対して「ゆいごん」は、遺言者が家族に対して残す言葉というより広い意味で使われることが多いです。
| 「いごん」の使用場面 | 法律上の効力がある遺言について話すとき。弁護士や司法書士などの法律家が仕事で使用する際の読み方です。法律を学ぶ人は早い段階でこの使い分けについて学びます。 |
|---|---|
| 「ゆいごん」の使用場面 | 世間一般で遺言について言及するとき。「遺言をする人が家族に対して残す言葉」というより広い意味合いで使われます。 |
| 専門家への相談時 | 弁護士や司法書士などに相談する際は、どちらの読み方でも意味は通じます。詳しい相談の中で、希望する遺言の種類について具体的に話し合うことになります。 |
実務上の違いはあるものの、一般の方が専門家に相談する際は読み方について心配する必要はありません。どの種類の遺言が適しているかなど、専門家のアドバイスを受けながら決めていくことが大切です。
遺言の種類
遺言には普通方式と特別方式の2つの大きな分類があり、さらに普通方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。それぞれの遺言形式には特徴があり、状況に応じて適した方法を選ぶことが大切です。
| 自筆証書遺言 | 遺言者が全文・日付・氏名を自筆で記載し、押印する方式です。費用はかかりませんが、形式不備や紛失のリスクがあります。法務局での保管制度(自筆証書遺言書保管制度)も創設されました。 |
|---|---|
| 公正証書遺言 | 公証人が遺言者の口述を筆記し、証人2名以上の立会いのもとで作成される方式です。形式不備のリスクが低く、原本は公証役場で保管されるため、紛失や偽造のリスクも少ないのが特徴です。 |
| 秘密証書遺言 | 遺言者が作成した遺言書を封筒に入れ、公証人と証人の前で遺言書であることを申述し、封印する方式です。内容を秘密にしたい場合に適していますが、あまり利用されていません。 |
| 特別方式の遺言 |
|
遺言の種類によって必要な手続きや効力に違いがあります。公正証書遺言は専門家のサポートを受けられるため最も確実な方法とされていますが、状況や希望に応じて適切な形式を選ぶことが重要です。どの遺言が適切かは専門家に相談するとよいでしょう。
遺言で定めることができる内容
遺言では様々な内容を定めることができます。財産の承継に関することだけでなく、身分関係の変動や後見人の指定なども可能です。ただし、公序良俗に反する内容や法律で禁止されている内容は無効となります。
上記のように、遺言では財産分与だけでなく様々な事項を定めることができます。特に相続人間でトラブルが予想される場合や、法定相続とは異なる分配を希望する場合には、明確な遺言を残すことが推奨されます。
遺言の効力
遺言は遺言者の死亡時に効力が生じます。生前に何度でも撤回・変更が可能で、常に最新の遺言が有効となります。遺言の内容は法定相続に優先しますが、遺留分を侵害する場合には、遺留分権利者から減殺請求を受ける可能性があります。
- 遺言者の死亡:遺言は遺言者の死亡によって初めて効力を生じます
- 遺言の開封:自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要です(公正証書遺言は不要)
- 遺言執行:遺言執行者がいる場合は執行者が、いない場合は相続人が遺言内容を実行します
- 相続登記等:不動産などの名義変更手続きを行います
遺言の効力が発生するためには、法律で定められた方式に従って作成されている必要があります。方式に不備がある場合、無効となる可能性があるため注意が必要です。また、複数の遺言がある場合は、原則として最新のものが有効となります。
遺言の保管と執行
遺言の保管方法は遺言の種類によって異なります。自筆証書遺言は従来、遺言者自身が保管する必要がありましたが、2020年7月から法務局における自筆証書遺言保管制度が開始され、安全に保管できるようになりました。
| 自筆証書遺言 | 遺言者自身による保管か法務局での保管(自筆証書遺言保管制度)を選択できます。法務局での保管を選択した場合、検認は不要となります。 |
|---|---|
| 公正証書遺言 | 原本は公証役場で保管され、遺言者と遺言執行者には正本または謄本が交付されます。検認手続きは不要です。 |
| 遺言執行者 | 遺言で指定するか、家庭裁判所が選任します。遺言執行者は遺言の内容を実現するために必要な一切の行為を行う権限を持ちます。 |
遺言の保管方法は重要で、特に自筆証書遺言の場合は紛失や改ざんのリスクがあります。遺言執行者は遺言の内容を実現するための重要な役割を担うため、信頼できる人物を指定することをおすすめします。
遺言と遺留分
遺言の自由度は高いものの、法定相続人の最低限の取り分として「遺留分」が法律で保障されています。遺言で遺留分を侵害する内容を定めた場合、遺留分権利者は遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)ができます。
| 遺留分権利者 | 兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、直系尊属) |
|---|---|
| 遺留分の割合 |
|
| 遺留分侵害額請求 | 遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。請求期間は相続開始と侵害を知った時から1年以内、または相続開始から10年以内です。 |
遺言で財産をすべて第三者に贈与するなど、法定相続人の遺留分を侵害する内容を定めた場合、遺留分権利者から請求を受ける可能性があります。遺言を作成する際には、遺留分についても考慮することが大切です。
よくある質問
「いごん」と「ゆいごん」は何が違うのですか?
「いごん」は法律上の効力がある遺言について話をするときの読み方で、弁護士や司法書士などの法律家が使用します。「ゆいごん」は「遺言をする人が家族に対して残す言葉」というより広い意味で使われることが多く、一般的な呼び方です。ただし、専門家に相談する際はどちらの読み方でも意味は通じます。
遺言書はいつ作成するべきですか?
遺言書は成年(18歳以上)であれば、いつでも作成することができます。特に高齢になってからではなく、判断能力が十分なうちに作成しておくことをおすすめします。財産が増えた時、家族構成が変わった時など、ライフイベントのタイミングで見直すと良いでしょう。
遺言書は自分で作成できますか?
自筆証書遺言であれば自分で作成することができます。ただし、方式に不備があると無効になるリスクがあるため、専門家(弁護士・司法書士・行政書士など)に相談することをおすすめします。公正証書遺言の場合は公証役場での作成が必要です。
遺言書の変更や撤回はできますか?
遺言は生前であれば何度でも変更・撤回が可能です。新たな遺言を作成することで以前の遺言を撤回したり、一部を変更したりできます。ただし、変更・撤回する場合も遺言の方式に従う必要があります。
弁護士や司法書士に相談する際、「いごん」と「ゆいごん」どちらの読み方で話せばよいですか?
どちらの読み方でも意味は通じますので、普段使い慣れている呼び方で大丈夫です。専門家は相談内容から、自筆証書遺言なのか公正証書遺言なのかなど、希望する遺言の種類について詳しく話を伺いながらアドバイスしてくれます。
まとめ
遺言(ゆいごん・いごん)は、人の死後に法的効力を持つ意思表示です。「いごん」は法律上の効力がある遺言について話をするときに用いられる読み方で、法律家が使用します。一方「ゆいごん」は、遺言者が家族に残す言葉というより広い意味で使われることが多く、一般的な呼び方です。
専門家に相談する際はどちらの読み方でも意味は通じますので、気にせず相談してください。遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの種類があり、それぞれに特徴があります。状況や希望に応じて適切な形式を選ぶことが重要です。
遺言では財産分配だけでなく、遺言執行者の指定、認知、後見人の指定など多岐にわたる内容を定めることができ、法定相続に優先して効力を持ちます。ただし、遺留分権利者の遺留分を侵害する場合は、遺留分侵害額請求を受ける可能性がある点に注意が必要です。相続トラブルを未然に防ぎ、自分の意思を確実に伝えるためにも、早めに遺言の検討をし、専門家に相談することをおすすめします。






