みなし相続財産(みなしそうぞくざいさん)とは?
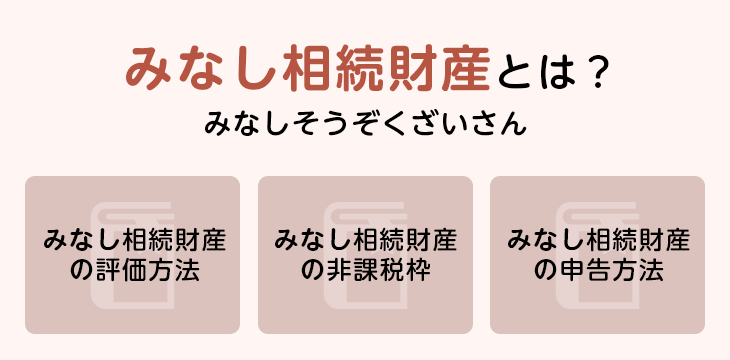
みなし相続財産とは、被相続人(亡くなった方)の死亡により相続人が受け取る財産のうち、法律上は相続財産ではないものの、相続税法上では相続財産とみなして相続税の課税対象となる財産のことです。生命保険金や死亡退職金などが代表的な例です。
これらの財産は本来、契約によって受け取る権利が発生するため厳密には相続財産ではありませんが、被相続人の死亡を原因として取得する財産であることから、相続税の公平性を確保するために「みなし相続財産」として課税対象とされています。
みなし相続財産の種類
相続税法では、以下の財産がみなし相続財産として定められています。これらは被相続人の死亡によって取得するものであり、相続税の課税対象となります。
| 生命保険金 | 被相続人が契約者で、被相続人の死亡により相続人等が受け取る生命保険金です。保険契約の受取人が相続人等になっている場合に該当します。 |
|---|---|
| 死亡退職金・弔慰金 | 被相続人の死亡によって、勤務先から遺族に支払われる退職金や弔慰金が該当します。 |
| 定期金 | 被相続人の死亡後に、相続人等が継続して受け取ることができる年金などの定期的な給付金です。 |
| 生命保険契約に関する権利 | 被相続人が保険料を負担し、被相続人以外の者が保険金を受け取る場合の保険契約に関する権利です。 |
| 信託に関する権利 | 被相続人の死亡によって相続人等が受益者となる信託に関する権利です。 |
上記の表は主なみなし相続財産の種類です。生命保険金と死亡退職金が最も一般的で、相続税申告の際に注意が必要な項目です。
みなし相続財産の評価方法
みなし相続財産の評価は、財産の種類によって異なります。基本的な評価方法は以下のとおりです。
生命保険金の評価
生命保険金は、実際に受け取った金額を評価額とします。ただし、後述する非課税枠があるため、全額が課税対象となるわけではありません。
死亡退職金・弔慰金の評価
死亡退職金や弔慰金も、実際に受け取った金額が評価額となります。これらにも一定の非課税枠が設けられています。
定期金の評価
定期金(年金など)は、将来にわたって受け取る権利の現在価値を計算し、評価額とします。年金の種類や受取人の年齢などによって計算方法が異なります。
- 給付事由発生:被相続人の死亡により年金等の給付が始まる
- 現在価値計算:将来受け取る年金の総額を法定利率で割り引く
- 評価額確定:計算された現在価値がみなし相続財産の評価額となる
上記の流れで定期金の評価額が決まります。評価方法が複雑なため、専門家に相談することをおすすめします。
みなし相続財産の非課税枠
みなし相続財産には、一定の非課税枠が設けられています。これによって、全額が相続税の課税対象となるわけではありません。
| 生命保険金の非課税枠 | 500万円 × 法定相続人の数 |
|---|---|
| 死亡退職金の非課税枠 | 500万円 × 法定相続人の数 |
上記の表は主なみなし相続財産の非課税枠です。例えば、法定相続人が配偶者と子2人の合計3人の場合、生命保険金は1,500万円まで、死亡退職金も1,500万円まで非課税となります。
非課税枠を超える部分が相続税の課税対象となるため、みなし相続財産が高額な場合は税負担が発生する可能性があります。法定相続人の数によって非課税枠が変わるので、正確に把握することが重要です。
みなし相続財産の申告方法
みなし相続財産は、相続税の申告書に記載して申告する必要があります。申告の流れは以下のとおりです。
- みなし相続財産の把握:生命保険金や死亡退職金などの金額を確認する
- 非課税枠の計算:法定相続人の数に基づいて非課税額を計算する
- 課税価格の算出:非課税枠を超える部分を課税価格に算入する
- 相続税申告書への記載:相続税申告書の所定の欄に記入する
上記の手順でみなし相続財産の申告を行います。申告漏れがないよう、生命保険会社や勤務先から受け取った書類を確認することが大切です。
相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。みなし相続財産を含めた相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合は、必ず申告が必要です。
よくある質問
Q1: 生命保険金は全額相続税の対象になりますか?
いいえ、全額が対象になるわけではありません。生命保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。この非課税枠を超える部分のみが相続税の課税対象となります。
例えば、法定相続人が3人で生命保険金が2,000万円の場合、非課税枠は1,500万円(500万円 × 3人)なので、課税対象額は500万円となります。
Q2: 死亡退職金と生命保険金の非課税枠は合算されますか?
いいえ、死亡退職金と生命保険金の非課税枠は別々に計算されます。それぞれに「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が適用されます。
例えば、法定相続人が2人の場合、生命保険金は1,000万円まで、死亡退職金も1,000万円まで、合計2,000万円が非課税となります。
Q3: 個人年金は相続税の対象になりますか?
被相続人の死亡によって相続人が受け取る権利を得た個人年金は、みなし相続財産として相続税の対象になります。将来受け取る年金の現在価値が評価額となります。
ただし、被相続人が生前から受け取っていた年金で、被相続人の死亡により打ち切られる場合は、みなし相続財産には該当しません。
Q4: 法定相続人とは誰のことですか?
法定相続人とは、民法で定められた相続権のある人のことです。配偶者、子、父母、兄弟姉妹などが該当し、順位があります。
非課税枠の計算に使用する法定相続人の数は、実際に相続を放棄した人も含めて計算します。また、相続を受ける権利のない人(相続欠格者や廃除された者)は含まれません。
Q5: 養老保険の満期金はみなし相続財産になりますか?
いいえ、養老保険の満期金は被相続人の死亡を原因として受け取るものではないため、みなし相続財産には該当しません。
ただし、被相続人の生前に満期を迎え、その満期金が被相続人の預貯金などになっていた場合は、通常の相続財産として相続税の対象となります。
まとめ
みなし相続財産とは、法律上は相続財産ではないものの、被相続人の死亡によって取得する財産として、相続税法上では相続財産とみなされ課税対象となるものです。生命保険金や死亡退職金が代表的な例で、相続税申告の際に見落としがちな項目です。
これらのみなし相続財産には「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠が設けられており、この非課税枠を超える部分のみが相続税の課税対象となります。生命保険金と死亡退職金はそれぞれ別々に非課税枠が適用されるため、法定相続人が多いほど非課税となる金額も大きくなります。
みなし相続財産の申告漏れは相続税の追徴課税や加算税のリスクがあるため、生命保険会社や勤務先からの書類をきちんと確認し、相続税申告書に正確に記載することが重要です。相続税の申告が必要かどうか判断に迷う場合や、みなし相続財産の評価方法がわからない場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。






